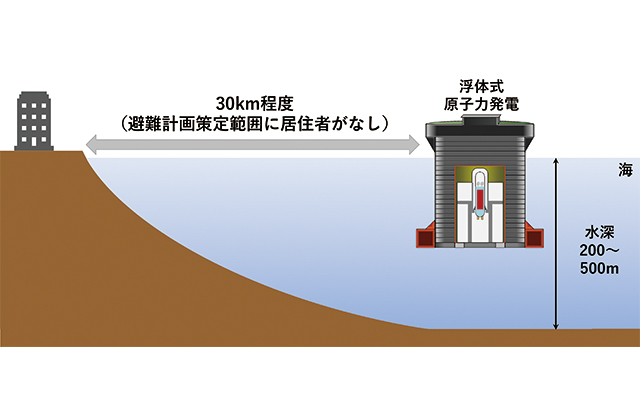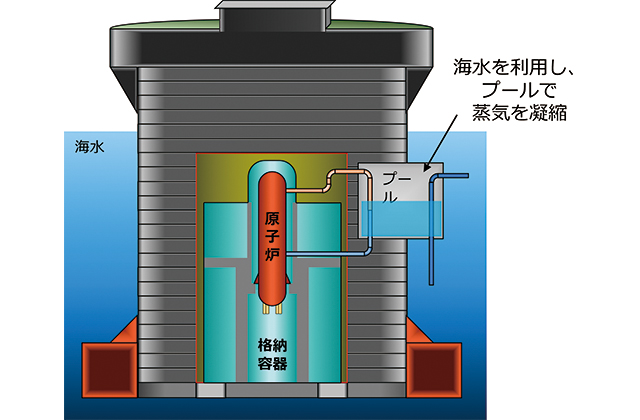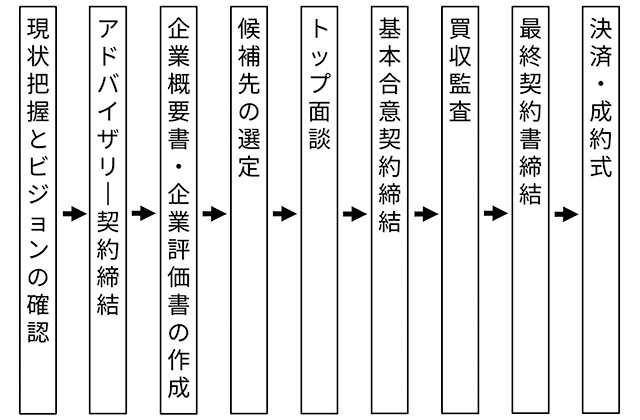【原子力の世紀】晴山 望/国際政治ジャーナリスト
核保有国は核兵器や原子力潜水艦など軍事用の核ごみ処分に手を焼く。
米国では処分先が決まらない核ごみを軍用施設に仮置きしている。
93基の原子力発電所が稼働する世界一の原発大国アメリカ。しかし、その米国でも核のごみ処分を巡っては、日本と同様に最終処分場の建設にめどが立たない状態が続く。 米国は、西部ネバダ州ユッカマウンテンの山中に処分場建設を決め、1978年に調査を始めた。だが地元の根強い反対があり、2008年の米大統領選で激戦区であるネバダ州を制したい民主党のオバマ候補(後の大統領)が、計画撤回を公約した。新たな処分場は設定されないままの状態にあり、7万t以上に達した核のごみは、原発敷地内などに設けたドライキャスクに保管されている。
 原潜から取り除かれた原子炉(2024年9月)
原潜から取り除かれた原子炉(2024年9月)
提供:米国防総省
軍事専門の核ごみ処分場 MOX燃料への加工断念
米国はロシアと並ぶ核兵器大国でもある。核兵器に使うプルトニウムを製造するため核燃料を再処理、これにより生じた大量の核のごみがある。ただ、処分場は民生用とは切り離し、メキシコ国境に近いニューメキシコ州の核廃棄物隔離試験施設(WIPP)に設けた。
1999年春に操業を始めたWIPPは、フィンランドのオンカロなどと同様に地下地層処分場だ。地下655mの岩塩層が処分場所となる。過去に何度も事故があり、最大だった2014年の事故では放射性物質が施設を汚染する事態にまで至り、3年近く作業中止に追い込まれた。現在の計画では70年まで廃棄物を受け入れ、その後、1万年管理する。
WIPPは、核燃料再処理で発生した半減期が20年よりも長い超ウラン(TRU)廃棄物の処分を想定していた。しかし、時代を経るにつれ、受け入れる核物質の範囲を拡大、最近は核軍縮で余剰になった軍事用プルトニウムも運び込まれている。
米露両国は00年、核兵器削減により余剰となった軍事用プルトニウムについて、核兵器1万7000発分に相当する34tずつを双方が削減することに合意した。核兵器用の高濃縮ウランを希釈して核燃料に使ったのと同様に、軍用プルトニウムも混合酸化物(MOX)燃料にして使うことが決まる。当初は軽水炉での使用を想定していたが、紆余曲折を経て、ロシアはMOXを高速炉の燃料に使うことになった。
米国は南部サウスカロライナ州サバンナリバーにMOX燃料工場の建設を始めた。だが、工期の大幅な遅れや建設費の高騰で計画がつまずく。16年にオバマ政権が建設を止め、翌17年にトランプ政権が計画中止を決めた。代替案として、処分費用が最も安く済むWIPPへの直接処分案が浮上した。 ところが、課題が浮上する。処分場や輸送中に敵国やテロリストなどにプルトニウムが強奪され、核爆弾が製造される事態を阻止する必要がある。そのための手法の検討が進んだ。
プルトニウムを「魔改造」 原潜や空母の処理も課題
米国はプルトニウムに「混ぜ物」をする手法で解決を図ることにした。ただ、この混ぜ物が何であるかは極秘で、詳細は公表されていない。
ロシアは「混ぜ物をしても、核兵器に使えるプルトニウムである点に変わりがない」と批判、米国がプルトニウム削減合意を守っていないとしている。米国が「廃棄」の名を掲げながら、プルトニウムを隠し持とうとしているとの主張だ。
プルトニウムに「混ぜ物」をする作業は、サバンナリバーのMOX工場予定地を再利用した。グローブボックス内で、プルトニウムを10%未満に希釈するため混ぜ物をして小さな缶に詰める。それをドラム缶に梱包し、輸送用のコンテナに詰める。大型トレーラーに載せ、数千㎞も西にあるニューメキシコ州のWIPPに陸上輸送する。
トレーラーは2人乗り。過去にも横転事故など20件もの事故を起こしている。保安対策のため全地球測位システム(GPS)を装着、絶えず衛星が動向を監視しているが、警備車両も付けずに時速約100㎞で単独走行している。米国は長年の間、核物質をこうしたトレーラーでの輸送を続けてきた歴史がある。日本人にとっては意外に映るが、核専門家からは「輸送面で大きな問題が起きたことはない」との評価が定着している。
前代未聞のプルトニウム廃棄輸送は、22年12月に始まった。
だが、トランプ米政権は今年5月になって、突然、方針の変更を打ち出す。同政権は50年までに原子力発電所の容量を4倍増とする新たな原子力政策を発表し、その中で、プルトニウムを重視する政策への変更も打ち出した。余剰プルトニウムの廃棄計画を中止するほか、1976年にフォード政権が核拡散防止のため国内での実施を禁止した民生用の核燃料再処理も再開する考えを示した。ただ、過去にも81年にレーガン政権が再処理モラトリアムを停止した例がある。当時は「採算が合わない」ことを理由に、再処理に乗り出す企業は出なかった。今回は、どうなるのだろうか。
米国など核保有国は、原子力潜水艦や原子力空母の処理・処分にもてこずっている。
原潜は退役が決まると造船所に回航される。まず、原子炉内にある使用済み核燃料を引き抜く。次いで、船体を解体して原子炉を切り取る。米国では太平洋に面する西部ワシントン州の造船所が「原子力海軍の墓場」の役割を務める。取り出した原子炉は前後を密閉した上でバージ(はしけ)に載せ、約1200㎞もコロンビア川をさかのぼり、ハンフォードに運ぶ。86年以後、160基以上の原潜の使用済み原子炉が運び込まれ、野積みされている。
英国では、昨年まで海軍基地2カ所に、初代の原潜を含めて23隻全ての退役原潜が係留されていた。このうち11隻は、使用済み核燃料を抜き出しイングランド北部にあるセラフィールド原子力複合施設に移送した。だが、残りの12隻には現在も核燃料や原子炉も据え付けたままの状態にある。ようやく今年6月に1隻目の解体作業が始まった。
核のごみとの戦いは、民生にとどまらず軍事面でも難航している。