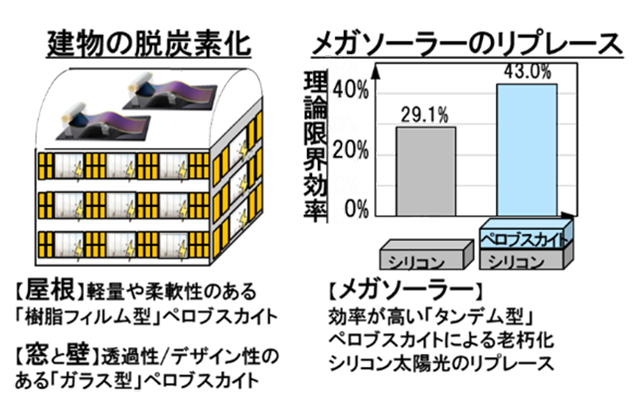NEWS 01:台湾で「原発ゼロ」当面継続へ 世界的な活用の潮流に乗れず
台湾で当面、「原子力ゼロ」の状態が続く見通しとなった。8月23日に実施された第三原子力発電所(PWR、95万1000kW×2基)の再稼働の是非を問う全有権者投票が不成立となったためだ。
台湾の原発を巡っては、1978年以降、第一~三原発の原子炉各2基が順次稼働したが、2011年の東京電力福島第一原発事故を契機に脱原発の機運が高まった。40年の運転期間に達した原発を段階的に停止し、今年5月に唯一稼働していた第三原発2号機を停止。台湾で稼働する原発はなくなった。
 投票率の低迷が不成立につながった
投票率の低迷が不成立につながった
ただ、原子力利用継続を求める世論は根強く、5月に最大野党・国民党が主体となり40年超運転を可能にする法改正を実施。その後、第2野党の民衆党が第三原発の再稼働を問う今回の有権者投票を提案していた。
可決要件は「賛成票が反対票を上回る」とともに、「賛成票が有権者の4分の1を超える」こと。だが、賛成票が反対票を大幅に上回っていたにもかかわらず、後者の要件を満たすことができなった。要因は投票率の低さだ。この結果は法的拘束力を持ち、今後2年は同じ議題を扱うことができない。
頼清徳現政権は、小型モジュール炉(SMR)など次世代原発導入の議論は排除しない方針だ。ただ、具体的な議論は進んでおらず、原発活用に動く世界の潮流に乗り切れない状況にあることは間違いない。
NEWS 02:苫小牧沖で初の試掘許可 官民一体でCCS推進へ
官民が一体となり、2030年までのCCS(CO2回収・貯留)事業開始に向けた動きが加速している。経済産業省は2月に、出光興産、北海道電力、JAPEXの3社が参画する北海道苫小牧沖を「特定区域」に指定。9月17日には、JAPEXに対し試掘を許可したと発表した。特定区域の指定と試掘許可はいずれも国内初だ。
JAPEXはCO2の貯留ポテンシャルを正確に見極めるため、区域内の2カ所で井戸を掘削し、砂岩などから成る「貯留層」とその上部で封じこめの役割を担う「遮蔽層」から試料を採取し、成分分析を行う。掘削リグは海岸近くに設置し、深度1540ⅿまで掘り進める。期間は1本目の試験が11月から来年5月まで、2本目は来年6月から27年1月までを予定。得られたデータを基に、26年度内に最終投資判断を下す見通しだ。
苫小牧沖では、出光興産の北海道製油所(苫小牧市)と北海道電力の苫東厚真発電所(厚真町)から排出されるCO2をそれぞれ回収し、パイプラインを通じて地下深部に圧入する計画が進む。JAPEXはパイプラインの建設のほか、貯留作業やモニタリングに必要な設備設計を担う。
懸念材料であった地元合意も整っている。CCSは環境団体の批判や地震時の風評被害など、社会受容性の低さが課題だったが、道側が提出した意見書にも「反対」の声はなかった。
経産省は、千葉県九十九里沖の一部地域を2カ所目の特定区域に指定した。こちらは東京湾沿岸の工業地帯から排出されるCO2を貯留する構想で、「首都圏CCS」として検討が進んでいる。
苫小牧と九十九里の両案件は、国内CCS事業の成否を占う試金石となるか。
NEWS 03:オランダで大規模な系統制約 EU諸国は教訓を生かせるか
オランダで深刻な系統制約が生じている。家庭や産業分野の急速な電化の進展に対し、送電網の整備が追いついていないためだ。同国の送電網事業者協会ネットベヘール・ネーデルラントによると、7月時点で1万1900を超える企業に加え、病院や消防署といった公共施設までもが新たな電化設備の系統への接続が待機状態にある。半導体大手ASMLなどが拠点を置き、先端技術産業の集積地として知られる南部アイントホーフェンのブレインポート地域でも、系統への投資が進まず今後の産業活動に影響を及ぼしかねない。
同国は2023年、欧州最大規模の北部フローニンゲン・ガス田の生産停止を決定し、電化を推進してきた。ロシアによるウクライナ侵攻を契機としたエネルギー価格の高騰が背景にあり、電化を促すことでガス依存からの脱却を図ることが狙いだ。
しかし、急速な電化に対し、送電インフラの整備は明らかに遅れている。発電側においても送電線に空きがなく、系統接続ができない事態が発生しており、風力や太陽光といった再生可能エネルギーの導入拡大の妨げとなっている。国営送電会社テネットは7月13日付の英フィナンシャル・タイムズ紙で、オランダがガス資源に長年依存してきたことが送電網の近代化を遅らせたと説明した。
このような事象は、十分なインフラを整えずに電化や電源の脱炭素化を急速に進めるリスクを浮き彫りにした。脱炭素化を野心的に進めるEU(欧州連合)諸国は、これを他山の石とするべきだ。
オランダ政府は下院総選挙を10月29日に実施する方針で、電力の系統問題は争点の一つになると見られている。エネルギー政策の転換点となるのか―。有権者の判断が注目される。
NEWS 04:上関中間貯蔵は建設可能 関電は「35年末」の新目標
中国電力は8月29日、山口県上関町で関西電力とともに建設を検討している使用済み燃料の中間貯蔵施設について、技術的に建設可能との調査結果を西哲夫町長に報告した。調査は2023年8月に開始していた。
 瀬戸内海に面する上関町
瀬戸内海に面する上関町
同日、関電は懸案となっている使用済み燃料の県外搬出を巡り、今年2月に見直した搬出計画の実行状況などを福井県に報告。各サイトの敷地内に乾式貯蔵施設の建設を決め、28~30年頃に搬入開始を予定する。今回、新たに乾式施設から中間貯蔵施設への搬入期限を「35年末」に定めた。青森県むつ市の中間貯蔵施設の場合、現地調査の開始から貯蔵建屋(1棟目)の完成まで8年近くを要した。上関も同等に見積もれば31年頃の完成が見込まれ、35年末は余裕を持った目標と言える。
ただ、六ヶ所再処理工場や東通、大間原発が立地する青森県と異なり、山口県には原発関連施設がない。今年3月に近隣町議会が建設反対を決議するなど、今後は県や周辺自治体の理解が鍵を握る。
中間貯蔵施設は、再処理工場への搬出までの「つなぎ」の役割に過ぎない。周辺自治体が気を揉むのは、施設が最終処分地になる不安があるからだ。こうした懸念を払しょくするには、やはり再処理工場のしゅん工しかない。日本原燃が目指す26年度中のしゅん工まで、残された時間は1年半だ。