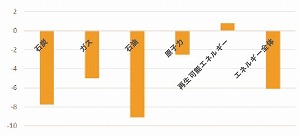舛添要一/国際政治学者
新型コロナウイルスの感染が世界中に拡大し、多数の犠牲者を出している。パンデミックの怖さだが、ワクチンが開発されない限り、第二波、第三波が到来する可能性があり、警戒を怠ってはならない。
私は、2009年に厚生労働大臣として新型インフルエンザの流行に対応したが、その経験が活用できることもあれば、そうでない場合もある。「新型」と言われるように、このウイルスの特質は十分には解明されていない。複数の型があり、また変異もしている。
自然災害の時には、厚労省は上水道を担当する。各地で断水などないか、全力をあげて情報を収集し、国民の命を守った。14年から約2年半にわたって東京都知事の職にあったが、近年の異常気象の影響で都市型の集中豪雨に襲われるなど、防災の観点からさまざまな見直しを行った。若い頃、欧州で安全保障や危機管理について研究し、とくにスイスでの生活から国民皆が防災対策を講じることが重要だという認識を持っていた。

デング熱感染は終息 災害の同時発生は想定外
スイスでは、戦争や災害に備えるためのマニュアルが、政府によって全世帯に配備されている。『民間防衛』という本であるが、邦訳も出ており、コンパクトながら、有事の際の行動規範から日常生活での危険回避方法まで、具体的に記されている。これを参考にして、一家に一冊常備するために、完全東京仕様の防災ブック『東京防災』を完成させ、15年9月に全世帯に無料で配布した。
この本の中には、避難先の確認、防火防災訓練への参加、家具類の転倒防止、非常用持ち出し袋の用意、災害情報サービスへの登録、日常備蓄の開始などが細かく説明してある。この防災ブックには、感染症についても記述してあるが、わずか2ページであり、今回のような未知のウイルスによるパンデミックに対する細かい指示までは書いていない。
14年の夏に、デング熱の国内感染が70年ぶりに起こったが、感染源とされる代々木公園の蚊の駆除を徹底的に行い、早期に終息させることができた。ワクチンもなく、治療は対処療法のみであるが、蚊を媒介しての感染であり、ヒトからヒトへの感染ではなく、今回の新型コロナのようなパンデミックではなかった。そのために、デング熱患者の発生を防災と同様な観点から記述するという発想にはならなかったのである。
今はまだ、新型コロナウイルスが生き続けている。その状況で、台風や集中豪雨によって河川が氾濫したり、地震によって建物が崩壊したりすると、大変な状況に陥る。感染症は、私たちが今経験しているように、尊い人命を奪う怖い病気のまん延である。そのため、外出禁止などの隔離生活を強いられ、経済社会活動が阻害される。しかし、病原体は生活に必要なインフラまでは襲わない。
これに対して、地震や台風は、電気、ガス、水道、道路、鉄道、空港、港など生活インフラを直撃する。家屋の倒壊、火災など甚大な被害をもたらす。人命も奪う。
昨年9月には台風15号が日本を襲い、千葉県では停電の長期化という想定しない事態に住民も大変な苦痛を強いられた。
その後に来た台風19号もまた、大きな被害をもたらした。64もの河川が氾濫し、2万3000ヘクタールもが浸水し、4000人を超える人々が避難生活を余儀なくされた。ライフラインの機能を95%回復させるのに、電力で7日、通信で14日、上下水道で30日、都市ガスで60日かかる。そのため、商品の流通に支障が出て、生活必需品が入手困難となる。また、経済的な被害も計り知れない。
感染症と自然災害、いずれの被害が甚大かの評価は難しい。しかし、ウイルスや細菌という病原体は、生活インフラまでは攻撃しないだけ、少しはましかもしれない。
単一発生より数倍の努力 避難訓練の想定変更を
問題は、両者が同時に到来する場合である。自然災害のケースについては、『東京防災』に、事前備蓄、避難場所の確認、室内外の備えなど対処法を記している。
昨年5月下旬に、東京都江戸川区が「江戸川区水害ハザードマップ」を発表したが、一昨年8月22日には、江東、江戸川、葛飾、足立、墨田の江東5区広域推進協議会が、高潮や河川の氾濫による水害について、「江東5区大規模水害広域避難計画」を、ハザードマップとともに発表している。
この江東5区は荒川と江戸川という二つの大河川の流域にあり、同時に氾濫した場合、最悪のケースで9割以上、つまり250万人の住む地域が水没し、約100万人が住む江戸川区西部と江東区東部などでは2週間以上浸水が続く。
上記二つのハザードマップは、水害を想定したものであり、感染症の同時発生は想定していない。そこで、自然災害と感染症まん延が同時発生した場合、住民の命を預かる政府や地方自治体としては、単一発生の場合に比べ、何倍もの努力が必要になる。
第一は、避難所を倍増させねばならないことである。密閉空間を避け、人と人との間隔を2m空けるとなると、避難所の数を2〜3倍にせねばならない。
第二に、暑い夏、寒い冬の場合、冷暖房が必要であるが、体育館などでは、その設備がないところがある。また、あったとしても、頻繁に換気が必要になってくる。さらに言えば、停電になったら電気製品は使えない。
第三に、そもそも避難する際に、迅速さと感染防止を両立させることが困難なケースが多発するであろう。河川の堤防決壊が迫っているときには、緊急で集団避難せざるを得ないからである。
第四に、医療崩壊をどう防ぐかという問題である。感染症の治療とほかの病気や怪我の治療を同一の場所で行うことはできない。今回のコロナでも、医療機関のみならず、高齢者施設、福祉施設などでも院内感染が起こり、大きな問題になっている。避難所で感染症患者が発生したときの対応マニュアルが必要である。
これまで訓練してきた地震や台風への備えに加えて、感染症同時発生のケースは、さらなる人的、物的支援が必要となる。一自治体で対応できる課題ではなく、中央政府の強力な支援と自治体間の協力が不可欠である。同時に、今回の新型コロナの感染拡大の教訓から、国民一人ひとりが日ごろから複合災害に備える必要がある。自治体での避難訓練も、複合災害対応に変えていかねばならない。

ますぞえ・よういち 1948年福岡県生まれ。
東京大学法学部卒。2001年参議院議員に初当選。
参議院自民党の政策審議会長、厚生労働大臣などを歴任。
10年4月新党改革の代表に就任。14年2月~16年6月東京都知事を務める。