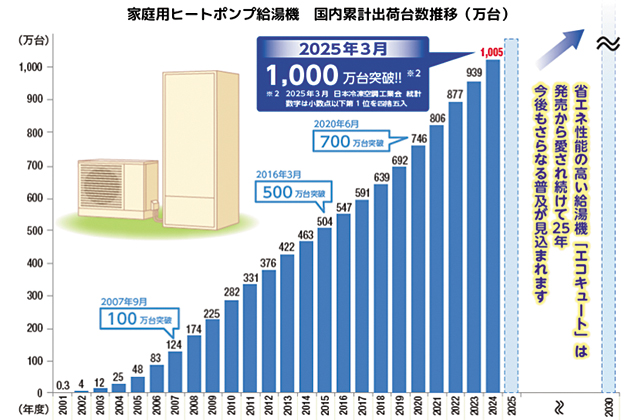エネルギー事業者が扱う商材は機器やサービスなど多岐にわたる。各社が顧客ニーズを汲み取った営業戦略を展開する。
PPA契約でエネファームを拡販 使い方指南で満足度向上を図る
静岡ガスは、グループ全体でカーボンニュートラルの実現に向けて取り組んでいる。その一つが家庭用コージェネレーションシステム、エネファームの拡販だ。業界全体の販売台数が累計50万台を突破する中、静岡ガスは昨年12月末時点で、5500件ほどを導入している。
「最近では資機材価格の高騰が影響し、万単位の部品で構成されるエネファーム本体価格も値上がり基調だ。そのため、太陽光発電の導入モデル『ソラーレ』という独自のサービスとのセット販売に注力している」。営業本部くらしデザイン部ルート開発グループ本部の山本大輔グループリーダーはこう話す。
ソラーレとは静岡ガスがエンドユーザーと10~13年の長期契約を結ぶPPA(電力販売契約)モデルだ。静岡ガスが家の屋根にPVを設置し、資産としてPVを所有・管理することで、ユーザーは初期費用ゼロでPVを導入できる。PPA契約終了以降、PVはエンドユーザーの資産となる。こうした仕組みでエネファームの初期費用の割高感を緩和させる。静岡ガスではパナソニック機(PEFC)とアイシン機(SOFC)のエネファームを販売している。
「エネファームは他の給湯器にはない発電機能が備わっており、竜巻や台風などによる停電に対する備えになることから、災害対策として関心が集まる傾向が高まっている」(山本リーダー)
メンテナンスにも配慮している。静岡ガステクニカルセンターでは、エネファーム導入後の3カ月目と1年目にカスタマーサービス巡回を実施している。実際にアポイントを取ってエンドユーザー宅に訪問し、エネファームのメリットを感じてもらえるように、発電量や実際の運転状況を伝えているそうだ。また、使い方のアドバイスを実施し、より効率的に使用してもらうことで満足度の向上を図っているという。小回りの利く、地域に密着した静岡ガスならではの取り組みと言える。
三菱地所との連携により、家のスマート化に向けた取り組みも行っている。25年には三菱地所が提供する「HOMETACT(ホームタクト)」というサービスの利用を開始した。これはいろいろな家電機器をスマホ端末のアプリでまとめて操作できるスマートホームサービスだ。
総合デベの強み活用 市販の家電などとも連携可
「家電機器メーカーも同様のサービスを展開しているが、どうしても同一メーカーの自社製品利用が前提となってしまう。総合デベロッパーが提供することで、エアコンや照明など、メーカー不問のサービスになっている」とルート開発グループの白鳥晶識氏は話す。また、市販の家電だけでなく、給湯や床暖房といったガス機器とも連携可能だ。「他の地方と同様、政令指定都市を持つ静岡県でも人口減少に悩まされている。市場が縮小する中、地域の課題解決に取り組み、お客さまとともに持続可能な社会の実現と地域社会の発展に貢献していきたい」。二人はこう口をそろえる。

ショールームでホームタクトを体感できる