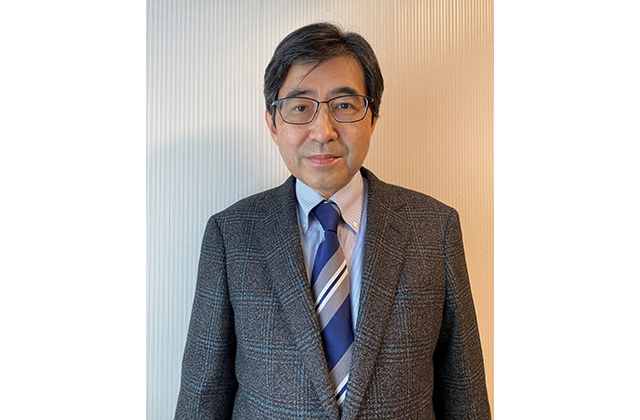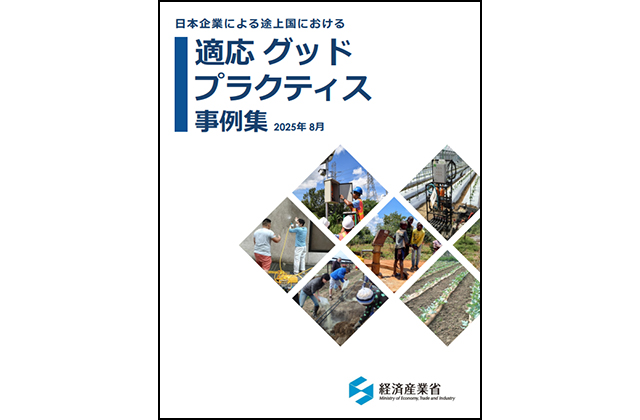NEWS 01:導入目標は堅持するも 相次ぐeメタン戦略見直し
都市ガスのカーボンニュートラル(CN)化の鍵を握るeメタン製造を巡り、世界に先駆けて取り組んできた東京ガスや大阪ガスが相次いで戦略の見直しに踏み切っている。
東ガスなど4社は、米キャメロンLNG基地近傍で検討してきた「ReaCH4プロジェクト」の解散を決めた。インフレに伴う資機材価格や建設コストの上昇を受け、事業の経済性確保が難しいとの判断だ。東ガスはカナダでのプロジェクトを有力候補とし、30年度までの製造開始を目指す。
一方、大ガスなどは、米中西部ネブラスカ州で進む「LIVE Oakプロジェクト」への参画を決めた。これまで先行して検討を進めてきた米トールグラスとのプロジェクトに代わる、「最有力」との位置付けだ。
こうした各社の戦略見直しに、「eメタン導入機運の大きな後退だ」と指摘するのは、橘川武郎国際大学学長。というのも戦略見直しにより、東ガスは年間13万tから3万t規模に、大ガスも20万tから7・5万tに生産規模が縮小するからだ。
都市ガス業界は、30年にeメタン1%の導入を中間目標に据えるが、日本ガス協会が2025年6月に策定した「ガスビジョン2050」では、50年時点でeメタン・バイオガスの割合を「90~50%程度」と高い目標を掲げたばかり。日本勢が世界のeメタン転換をけん引できるのか。正念場だ。
 eメタンの導入目標を堅持できるか
eメタンの導入目標を堅持できるか
NEWS 02:エネ庁が「核融合室」設置 商用化実現には疑問符も
資源エネルギー庁が2025年11月、核融合スタートアップ企業への支援を実施する「フュージョンエネルギー室」を設置した。かねて核融合に強い関心を示してきた高市早苗首相の肝いり政策と言っていい。
政府は6月、実証目標時期を30年代へと前倒しした。高市政権となった11月には予算や税を重点支援する「国家戦略技術」の6分野の一つに指定。実際に12月に成立した補正予算では、関連予算の規模を従来の200億円から1000億円を念頭に組んだ。
高市氏に近い自民党議員は「1000億円に持っていけたことには満足している。核融合分野で日本は勝ち筋がある。補正予算で重点投資する戦略17分野の中でも、世界を取れる可能性が最も高い」と語る。
地方でも核融合を巡る動きは活発化している。12月には核融合ベンチャーの一社、ヘリカルフュージョンが、愛知県を地盤とするアオキスーパーと核融合発電による電力の売買契約を結んだ。また同月、青森県の宮下宗一郎知事は六ヶ所村に発電実証を行う原型炉の誘致を目指すと表明した。
一方、政府やスタートアップの前のめりな姿勢を疑問視する向きもある。事実として、日欧共同プロジェクトであるフランスの国際熱核融合実験炉(ITER)では、エネルギーを取り出すどころか核融合状態の長時間維持すら成功していない。事情通は「50年になっても脱炭素に貢献できるレベルでの発電など絶対に不可能だ。いま資金集めに奔走している企業は、投入したエネルギーに対して1Wでも多く発電できれば『発電できた』と言い張るのだろうが、詭弁以外の何物でもない」と手厳しい。
過度な期待は禁物か。
NEWS 03:ETSの実施指針取りまとめ 上下限価格水準も提示
2026年度のGX―ETS(排出量取引制度)導入を前に、経済産業省・産業構造審議会の小委員会が、排出枠の割当の実施指針や、26年度の上下限価格水準を取りまとめた。上限はCO21t当たり4300円、下限は1700円とする。
上下限価格は、価格安定化を目指し設定するもので、制度の重要なポイントだ。毎年度、年度開始前に設定する。上限価格は、産業や国民生活を守るセーフティーバルブの役割として導入する。他方、市場価格が一定期間下限価格を下回る場合は「リバースオークション」で排出枠の流通量を調整する。事務局は12月9日の会合で、上限価格は既存のJクレジットなどの価格水準とは独立的に設定する考えを示していた。
割当方法についてはこれまで示された通り、エネルギー多消費分野などは業種ごとにベンチマーク(BM)を設定。これに基づき、企業ごとに割当量を算定する。例えば発電事業はBMで、化石燃料を使う発電設備の直接排出が対象となる。特定供給を含む自己託送や自家消費、熱・蒸気に関する排出は除く。まずは燃種別BMとし、徐々に全火力BMへ移行する。
他方、BMの設定が困難な業種は、一定比率で削減していくグランドファザリング(GF)方式とする。ただ、今後の展開として、過去の削減努力を適切に評価し、業種特性を踏まえ割当を行う観点から、GFの対象業種もBMへの移行を検討することとした。
また、BMについても今回設定した水準が機能しているかなどを点検し、必要に応じて31年度以降の割当方法を見直す。
排出枠取引市場はGX推進機構が設置・運営し、27年度秋ごろの開設を予定する。その設計は26年度に進める。
NEWS 04:FIT・FIPを見直し 事業用太陽光の支援廃止も
北海道・釧路などの不適切メガソーラー開発に端を発した規制強化の動きがまた一歩進んだ。自民党政務調査会が経済産業部会や環境部会などの合同会議で政府への提言を12月15日に取りまとめ、メガソーラーについてFIT(固定価格買い取り)・FIP(市場連動買い取り)での支援の廃止を視野に検討するよう求めた。さらに新設する関係閣僚会議でも議論を深める方針だ。
 太陽光支援の在り方が変わる
太陽光支援の在り方が変わる
提言では、①不適切事案に対する法的規制強化、②地域の取り組みとの連携強化、③地域共生型への支援重点化―の3本柱を掲げた。特に③では、メガソーラーは現状を踏まえればFIT・FIPで支援する必要性が乏しく、廃止を含めた検討を行うよう提案。今後は地域共生型や次世代型電池を重点支援するよう求めた。
さらに16日、経済産業省が調達価格等算定委員会を開き、事業用太陽光(地上設置)の2027年度以降の扱いを議論。コスト低減が進み、FIT・FIPによらない案件形成もみられ、「自立の時期が到来しつつある」とし、支援の必要性を検討するとした。今後、最新のコストデータを踏まえて議論する。併せて地域共生を図る事業への支援重点化も検討する。
規制強化を巡っては、25年秋から関係省庁連絡会議でも検討を進めてきた。政府は、25年内に施策を取りまとめる予定としている。