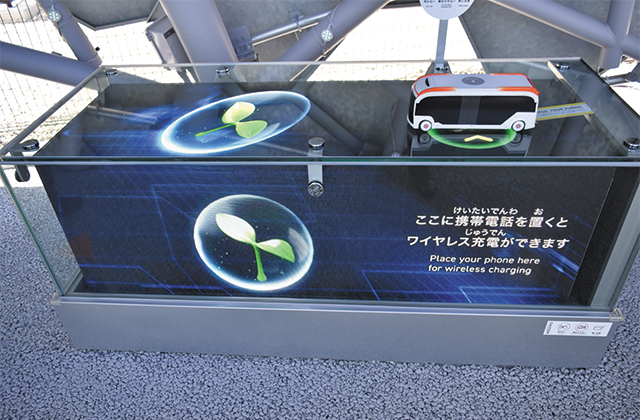【関西電力】
関西電力は万博会場を舞台にさまざまな実証を行っている。
カーボンニュートラル実現に向けた交通分野と電力供給の取り組みに注目だ。
関西電力は「大阪・関西万博」で、「Beyond 2025」と題し、未来社会の「あたりまえ」をコンセプトに次世代エネルギーの取り組みを披露している。
EVバスの充電計画を検証 ピーク電力の最小化目指す
会場でまず目を引くのがEVバスの取り組みだ。会場内の移動手段として運行するEVバスは東ゲートと西ゲートの間を大屋根リングの下などを通過しながら移動していく。関電は大阪市高速電気軌道(OM)とダイヘン、大林組、東日本高速道路などとともに経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) が進めているグリーンイノベーション基金の助成を受け、EVバスの大規模実証を行っている。具体的には100台以上(会場内で運行するのは30台)のEVバスを導入し、①運行管理システム(FMS)と一体となったエネルギーマネジメントシステム(EMS)の実証、②道路の一部に充電用コイルを埋設した走行中給電システムに関する実証―の二つを実施中だ。
 走行給電を行うEVバス
走行給電を行うEVバス
充電器を独立して運用すると、車両を接続した時点で充電が開始となる。複数台でタイミングが重なると電力消費のピークが立ってしまう。①の実証ではFMSとEMSを組み合わせ、運行計画に基づき、充電の優先度を考慮する。また、負荷平準化した充電計画を作成し制御することで、ピーク電力の最小化を目指している。目標は70%以上のピーク電力削減とのことだ。
②走行中給電では、バス停や会場西側の道路にコイルを埋設し、この上を停止・通過する際にワイヤレスで給電する。ソリューション本部eモビリティ事業グループの奥畑悠樹課長は「約50mの道路区間に給電用コイルを10セット設置した。この上を通過すると最大で30 kWの電力を送ることができる。実運用ではバス停や駅のロータリーなど、車両がしばらく停車する場所での活用が有望」と説明する。
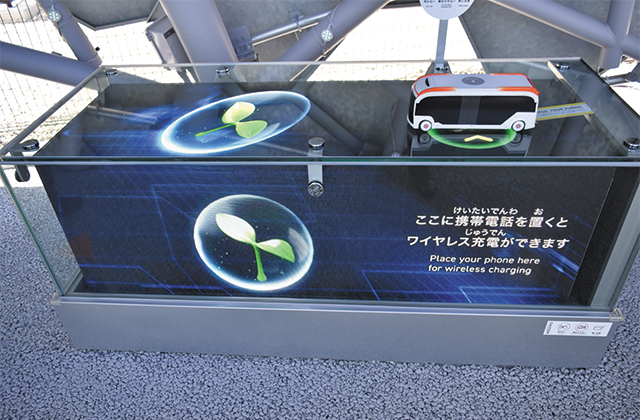 ワイヤレス給電をスマホ充電で説明
ワイヤレス給電をスマホ充電で説明
EVバスに関する他の取り組みとしては、バス停を情報発信ステーションと位置付け、未来社会をイメージした映像を流すなど、演出を施したものを会場内3カ所に展開する。「東ゲート北停留所」は、近くに位置する電力館と同じボロノイ形状を採用しデザインの一体感を演出。バスの停車位置にはコイルが埋設され、乗降中に充電できるようになっている。同バス停には、この仕組みをトリックアートやスマートフォンのワイヤレス充電を用いて解説する仕掛けが工夫されている。
他のバス停では、木材を基調とした持続可能な未来社会を表現したものや、国内最大規模の「3Dホログラムサイネージ」を採用した未来的な演出を行うものがある。3カ所三様のデザインと演出が見ものだ。
空飛ぶクルマの急速充電 冷却装置で性能低下を防止
 冷却しながら空飛ぶクルマを充電
冷却しながら空飛ぶクルマを充電
万博の目玉となる展示の一つでもある空飛ぶクルマのデモフライトは、会場内のモビリティエクスペリエンスで行われている。関電は同プロジェクトに参画するSkyDriveに充電設備を提供している。両社は22年に資本業務提携を締結。25年には提携を拡充し、充電システムの開発などで協業する。会場には充電器と冷却装置で構成する関電の充電設備が設置された。同グループの古田将空課長は「空飛ぶクルマはEV充電器の2~3倍の高電圧・大電流で急速充電を行う。バッテリーの温度上昇は性能低下などの原因になるため、冷却装置でバッテリーの温度管理を行うことが望ましいとの考えからこの構成となった」と話す。SkyDriveの機体は現在テスト中で、7月頃に会場で飛行する予定だ。
このほか、水素発電の取り組みでは姫路第二発電所(兵庫県)のガスタービンコンバインドサイクル発電1基(約48・65万kW)を使い、最大30 vol%の混焼率を目標に水素混焼を実施中。信頼性・安全性などを確認しながら、万博会場まで発電した電気の一部を送り届けている。
水素燃料電池船「まほろば」の運航ではエネルギーマネジメントなどを担当。同船は燃料電池と蓄電池で稼働する。同社南港発電所(大阪市住之江区)に水素充填と電気充電の設備を設置してエネルギー供給を行い、最適な方法を検証中だ。
 バス停で水素発電をアピール
バス停で水素発電をアピール
このように、関電は次世代エネルギー実証やその情報発信を万博という檜舞台で繰り広げている。カーボンニュートラル実現に向けた機運の高まりと相まって、同社の先進的な取り組みはさらに加速していく。