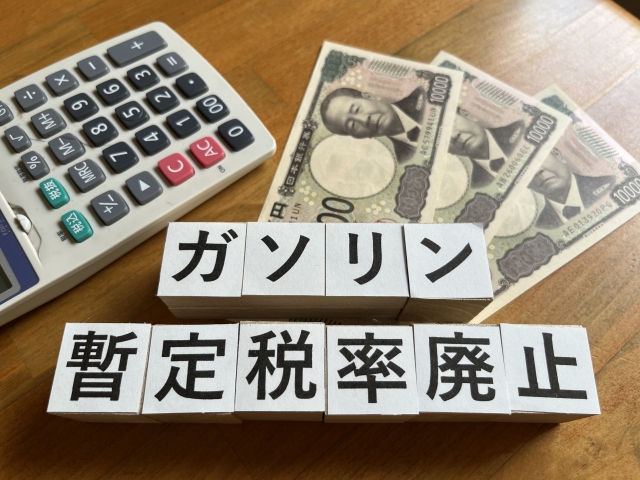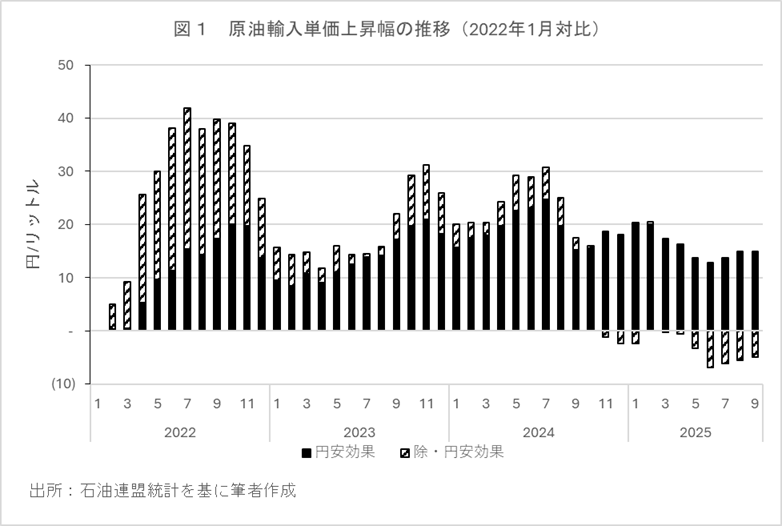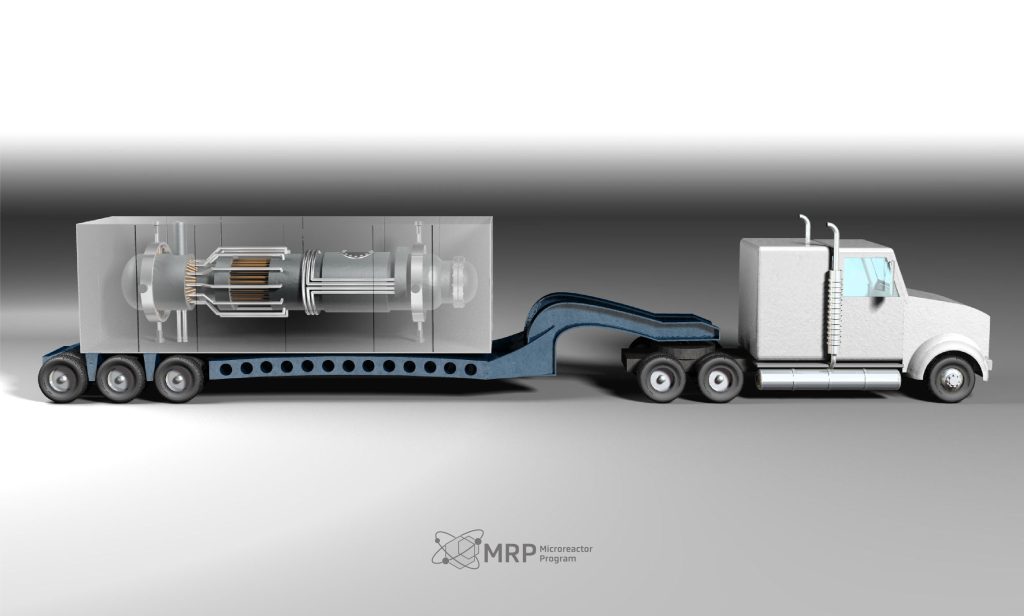【参考1】自民党「立地に寄り添うエネルギー政策推進議員連盟」 総裁選候補者にエネルギー政策を調査 高市候補・小林候補の回答
【参考2】自民党・日本維新の会 連立政権合意書 6.エネルギー政策
【参考3】高市首相の閣僚への指示書 ~エネルギー・環境に関する部分~
【参考4】高市首相 所信表明演説 ~「エネルギー安全保障」に関する部分~

【参考1】
自民党「立地に寄り添うエネルギー政策推進議員連盟」 総裁選候補者にエネルギー政策を調査 高市候補・小林候補の回答
滝波宏文議連事務局長 フェイスブックより (抜粋)
1.わが国におけるエネルギーの現状を踏まえた、原子力を含む現実的かつ責任あるエネルギー政策の推進
●高市候補
日本企業の国内回帰を促し国内のものづくり基盤を守るためにも、特別高圧・高圧の電力を安価に安定的に供給できる対策を講じていく必要がある。特に、AIの社会実装、それに伴うデータセンターの拡大などDXの進展により、電力需要が拡大すると指摘される中、それに応えられる脱炭素エネルギーを安定的に供給できるかが国力を左右するといっても過言ではない。一方で、わが国は国産エネルギー源に乏しく化石燃料の太宗を海外に依存している中で、ロシアのウクライナ侵略や中東地域の不安定化など、資源・エネルギーをめぐる情勢は、複雑かつ不透明な状況。エネルギー自給率を向上させ、強靭なエネルギー需給構造への転換を進めることが必要。供給サイドにおいては、将来にわたってわが国のエネルギー安定供給を確実なものにするため、あらゆる選択肢を確保しておくことが重要であり、自給率向上に貢献し脱炭素効果の大きい原子力を最大限活用する。まずは、安全性の確保を大前提に、原子力規制委員会による審査・検査を踏まえ、地元の理解を得た原子炉の再稼働を進める。さらに、地域の理解確保を大前提に、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設の具体化を推進する。さらには、ウランもプルトニウムも使わず、高レベル放射性廃棄物も発生しない核融合(フュージョンエネルギー)について、世界に先駆けた2030年代の発電実証を目指す。一方、需要サイドにおいては、徹底した省エネルギーに取り組む。冷媒適用技術や光電融合技術など、わが国の優れた省エ技術の研究開発・実用化を進め、国内の省エネ、更には、わが国の省エネ製品・技術の輸出拡大にも取り組む。
●小林候補
第7次エネルギー基本計画にある通り、すぐに使える資源に乏しく、国土を山と深い海に囲まれるなどの地理的制約を抱えている我が国の固有事情を踏まえれば、エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指していく必要がある。特に、DXやGXの進展による電力需要増加が見込まれる中、再エネか原子力かといった二項対立的な議論ではなく、原子力をはじめエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用していかなければならない。その中で、原子力は、エネルギー安全保障の確保、将来増加する電力需要や経済成長・産業競争力の強化に必要な脱炭素電源の拡大、電力料金抑制や燃料価格の影響を受けにくい経済構造への中長期的な転換、50年カーボンニュートラル実現のためにも、最大限活用すべきと考える。
2.リスクを負って安定安価な電力を供給してきた、「原子力立地地域に寄り添う」諸政策の強力な推進(原子力避難道の整備、最終処分地の確保、立地地域の振興など)
●高市候補
わが国の原子力利用は、原子力立地地域の関係者の安定供給に対する理解と協力に支えられてきた。今後も原子力利用を進めていく上で、立地地域との共生に向けた取り組みが必要不可欠である。立地地域の実情やニーズに即した地域振興支援や、新産業・雇用創出を含む将来像を自治体・国・事業者が共に描く取組など、対象地域から高い評価を得たグッドプラクティスの他地域への横展開などを進める。また、災害に対する地域住民の不安の声や自治体の業務負担の増大なども踏まえ、人材育成を含めた自治体の取組への支援、避難道の整備など防災対策の見直しと不断の改善に向けた官民連携などを進め、防災対策の一層の充実・強化を図る。最終処分の実現に向けた取組に関しては、最終処分事業に貢献する地域への敬意や感謝の念が社会的に広く共有されるよう、国主導での国民理解の促進や自治体などへの主体的な働きかけを抜本強化するため、政府一丸となって、かつ、政府の責任で、最終処分に向けて取り組んでいく。
●小林候補
わが国の原子力利用は、原子力立地地域の関係者のご理解とご協力に支えられてきた。立地地域に感謝の念を持って、課題に真摯に向き合い、産業振興や住民福祉の向上、防災対策のための予算措置、避難道路の多重化・強靭化など、立地地域に寄り添って、ともに歩む。
3.脱炭素社会実現と国力維持・向上のために必要な、我が国の原子力技術・人材・立地を保つ、最新型原子炉によるリプレース実現。そのための長期投資を可能とする事業環境の整備
●高市候補
将来にわたってわが国のエネルギー安定供給を確実なものとするため、あらゆる選択肢を確保していくことが重要。原子力に関しても、今後とも、革新技術による安全性向上、エネルギー供給における「自己決定力」の確保、GXにおける「牽引役」としての貢献といった原子力の価値を実現していくため、そして足下から安全向上に取り組んでいく技術・人材を維持・強化していくためにも、地域の理解確保を大前提に、六ケ所再処理工場の竣工などのバックエンド問題の進展も踏まえつつ、安全性の確保を大前提として、新たな安全メカニズムを組み込んだ「次世代革新炉」の開発・建設の具体化に取り組む。特に、大型電源については投資額が大きく、総事業期間も長期間となるため、事業期間中の市場環境の変化などに対応できるような事業環境の整備を推進する。同時に、研究開発や人材育成、サプライチェーン維持・強化に対する支援を拡充する。同志国との国際連携を通じた研究開発推進、強靭なサプライチェーン構築、原子力安全・核セキュリティ確保にも取り組む。次世代革新炉としては、革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、フュージョンエネルギーといった研究開発が進んでいる。特にフュージョンエネルギーはウランもプルトニウムも使わず、高レベル放射性廃棄物も発生しないことから、わが国のエネルギー問題を解決する切り札として期待される。わが国は、フュージョンエネルギーに関して技術的優位性を持っており、その実現は、産業振興を通じた産業競争力の強化およびエネルギーを含むわが国の自律性の確保を通じた経済安全保障の強化に資することから、戦略、法制度、予算、人材面での強化が必要である。 野心的な目標ではあるが、世界に先駆けた30年代の発電実証を目指していく。
●小林候補
原子力は、エネルギー安全保障の確保や脱炭素電源の拡大、電力料金抑制などの観点からも、最大限活用すべき。 安全性の確保を大前提に再稼働を進め、廃炉を決定した原子発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への建て替えなどについても進めていく。それを支える我が国の優れた原子力産業基盤や人材の維持・強化に取り組むとともに、電力システム改革によって競争が進展した環境下においても、予見性を持って投資が可能となるような事業環境整備を進める。
4.核燃料サイクルを堅持し、民主党政権の二の舞を避ける
●高市候補
わが国は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減などの観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウムなどを有効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針としており、これを堅持する。具体的には、使用済燃料の再処理について、日本原燃は六ケ所再処理工場の新たな竣工目標実現に向けて、規制当局との緊密なコミュニケーションなどにより、安全審査などへの対応を確実かつ効率的に進める。また、プルサーマルの推進や使用済燃料の貯蔵能力の拡大などに向けて、電力事業者が連携し、地元理解に向けた取組を強化するとともに、国もこうした取組をサポートし、主体的に対応する。
●小林候補
核燃料サイクル政策を堅持する。使用済燃料の再処理をはじめとする核燃料サイクル、円滑かつ着実な廃炉、高レベル放射性廃棄物の最終処分といったバックエンドへの対応はいずれも原子力を長期的に利用していくにあたって重要な課題。原子力に対する様々なご懸念の声があることを真摯に受け止め、それぞれの課題にしっかりと取り組み、丁寧に説明を行いながら、原子力を活用していく。
5.リプレースに向けた最新型原子炉の建設に必要な規制基準の迅速な設定とそのための事前審査など、適正手続(デュープロセス)などを踏まえた原子力規制委員会の規制行政の改善。および、政府のエネルギー政策との整合性確保に向けた原子力規制委員会の改革
●高市候補
原子力規制委員会は、科学的・技術的見地から、公正・中立に、かつ独立して意思決定を行う機関であり、いかなる事情よりも安全性を全てに最優先させるとの前提の下、同委員会が、次世代革新炉の安全確保について、適切な判断を行えるよう、必要な体制の整備に向けた取組を進めていく。また、事業者・ATENA(原子力エネルギー協議会)による、原子力規制委員会との共通理解の醸成・改善への協働を促していく。
●小林候補
原子力の最大限活用のためには、安全性の確保を大前提に再稼働や次世代革新炉の開発・設置などを加速化させていく必要がある。そのためには、原子力規制委員会や原子力規制庁による行政の改善・改革(審査の効率化や審査体制充実など)は根幹的に重要。安全の確保を最優先にしつつ、審査プロセスの継続的な改善に取り組む。
6.太陽光・風力など再エネにおける立地共生の推進
●高市候補
あらゆる電源に共通して、地域の理解や地域との共生は大前提。私たちの美しい国土を守るため、法令に違反する太陽光パネルが設置されることのないよう、地域の声を丁寧に聞きながら政府が前面に立って取り組んでいく。これまでの仕組みありきとせず、関連する規制・制度を総点検する。また、間もなく耐用年数を迎える初期に設置された太陽光パネルの安全な廃棄にも取り組む。同時に、特定の国にサプライチェーンを依存することなく、エネルギー自給率を向上させながら、わが国の産業競争力強化と経済安全保障を確保する観点から、ペロブスカイト太陽電池の普及を進める。日本で開発された技術であり、薄くて曲がることから建物への導入が可能で、主要な材料であるヨウ素は国内調達が可能であることから、日本国内はもとより海外にも展開していく。また、エネルギーを地産地消にすることで自然災害などによる広域大規模停電を防止する手段にもなるため、国産バイオマスや中小水力発電の活用、次世代型地熱発電の実用化に向けた取組なども進める。
●小林候補
再生可能エネルギーの導入に当たっても、立地地域との共生は大前提であり、関係法令の遵守を厳格に求めるとともに、適切な事業規律を一層確保するなど、関係省令や地方公共団体が連携した施策の強化に取り組む。その上で、高くて不安定な再生可能エネルギーは、その政策を見直していく必要がある。特に、太陽光については、地域住民の方々との摩擦やサプライチェーン上のリスクもあり、立ち止まる必要があると考える。
7.火力における脱炭素に向けた現実的なトランジションの推進、そして、立地地域の意見を踏まえた跡地活用
●高市候補
現状、火力発電は電源構成の7割を占めており、今後の電力需要の拡大が見込まれる中で安定供給をないがしろにすることのないよう、したたかなエネルギー転換を進める。具体的には、火力発電全体で安定供給に必要な発電容量は維持しつつ、非効率な石炭火力を中心に発電量を減らしていく。また、LNG火力は現実的なトランジションの手段として有効であり、将来的な脱炭素化を前提とした新設・リプレースを促進する。火力発電所を休廃止する場合には、地域経済や雇用への影響を最小化すべく、跡地活用のあり方を含め、事前に立地地域と十分にコミュニケーションを行う。
●小林候補
火力発電は、引き続き、供給力や再エネの変動を担う調整力として重要な役割を担う。石炭火力は、CO2の排出量が多いため、非効率な石炭火力を中心に発電量を減らしていくが、必要な供給力が十分に確保されていない段階で、直ちに急激な抑制策を講じることになれば、電力の安定供給に支障を及ぼしかねない。 従って、非効率な石炭火力のフェードアウトを着実に進めるとともに、水素・アンモニアやCCUSなどを活用した火力の脱炭素化を引き続き進めていく。また、火力発電所のトランジションに際しては、こうした燃料転換による脱炭素化のほか、発電所を廃止して跡地を産業用途などに有効活用する事例も見られる。火力発電が地方税収、雇用、地元企業への外注などを通じて地元経済に貢献している中で、地域経済や雇用への影響などを踏まえながら、地域の実情などに応じたトランジションの検討を推進する。
【参考2】
自民党・日本維新の会 連立政権合意書10月20日(抜粋)
6.エネルギー政策
◇電力需要の増大を踏まえ、安全性確保を大前提に原子力発電所の再稼働を進める。また、次世代革新炉および核融合炉の開発を加速化する。地熱などわが国に優位性のある再生可能エネルギーの開発を推進する。
◇国産海洋資源開発(エネルギー資源および鉱物資源)を加速化する。
【参考3】
高市首相の閣僚への指示書 ~エネルギー・環境に関する部分~(抜粋)
●松本文部科学相
◇原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介など、東京電力福島原子力発電所事故による損害の迅速な損害が講じられるよう、引き続き関係大臣と協力して対応する。
●赤沢経済産業相
◇関係大臣と協力して、東京電力福島第1原子力発電所の廃炉・汚染水・処理水対策、帰還困難区域の避難指示解除に向けた取組、原子力災害被災者の生活支援や生業再建などに全力で推進する。
◇国民生活や経済活動の基盤となるエネルギーの安定供給に万全を期す。S+3E(安全、安定供給、経済効率性、環境適合)の観点から、資源・エネルギーの多様で多角的な供給構造を確立する。安全を大前提とした原発の利活用、国内資源の探査・実用化、日本が潜在力を持つ再生可能エネルギーの最適なエネルギーミックスを実現し、日本経済をエネルギー制約から守り抜く。
◇エネルギー安全保障と脱炭素を一体的に推進する中で、産業競争力の強化、新たな需要・市場創出を通じた成長フロンティアの開拓を図り、強靭な経済構造を構築することを目指す。50年カーボンニューラルおよび30年度の温室効果ガス排出削減の実現に向け、グリーントランスフォーメーション(GX)2040ビジョンなどを踏まえ、官民協調による10年間で150兆円超のGX関連投資を推進する。
●石原環境相
◇放射性物質を含む廃棄物の処理、特定帰還居住区域における除染など、東日本大震災からの復興・再生の取組を着実に実施する。
◇50年カーボンニュートラルおよび30年度の温室効果ガス排出削減目標を実現し、世界の脱炭素を主導するため、GX実行推進担当大臣など関係大臣と協力して、地球温暖化対策を推進する。
◇関係大臣と協力して、40年までに追加的なプラスチック汚染ゼロを目指す。
◇原子力規制委員会における原子力安全規制および体制の強化を強力にサポートする。
◇関係大臣および原子力規制委員会と協力しつつ、原子力防災体制の抜本的強化を図る。
◇内閣府の事務のうち、原子力災害対策本部および福島第一原子力発電所事故調査に係るフォローアップに関する事務を担当させる。
◇原子力防災会議に関する事務を担当させる。国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP)をはじめとする気候変動問題に係る国際会議などへの対応を円滑に推進するため、行政各部の所管する事務の調整を担当させる。
【参考4】
高市首相所信表明演説~「エネルギー安全保障」に関する部分~10月24日(抜粋)
国民生活および国内産業を持続させ、さらに立地競争力を強化していくために、エネルギーの安定的で安価な供給が不可欠です。特に、原子力やペロブスカイト太陽電池をはじめとする国産エネルギーは重要です。GX(グリーントランスフォーメーション)予算を使いながら、地域の理解や環境への配慮を前提に、脱炭素電源を最大限活用するとともに、光電融合技術などによる徹底した省エネや燃料転換を進めます。また、次世代革新炉やフュージョンエネルギーの早期の社会実装を目指します。こうした施策を直ちに具体化させてまいります。我が国の総力を挙げて、強い経済を実現していこうではありませんか。