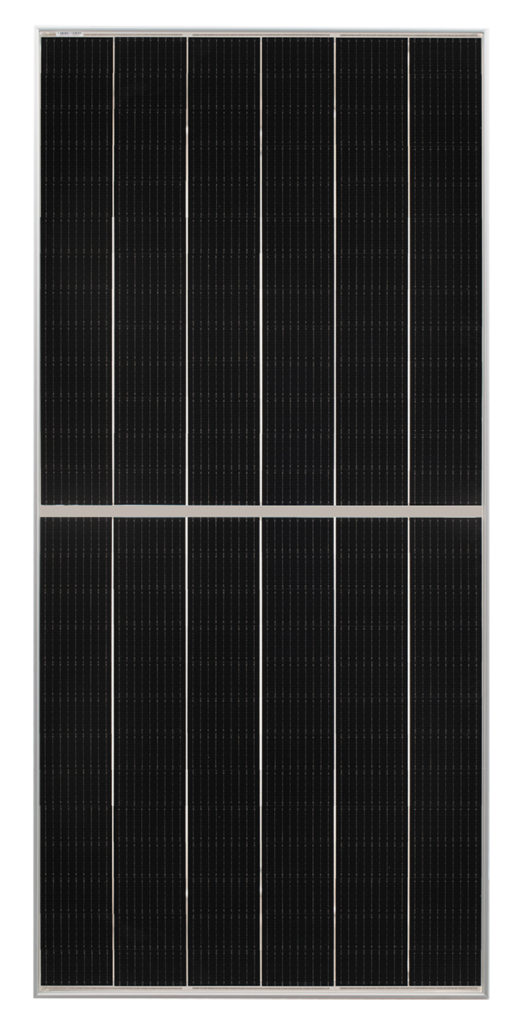【TOKAI】
大規模災害が発生したとき、まず優先的に確保すべきは、電気やガスなどエネルギー、そして生活水だ。水は飲料水としてだけでなく、入浴やトイレなど、多くの生活シーンで欠かせないものとなる。

そんなエネルギーと水のBCP(事業継続計画)対策に優れた先鋭的な住宅として注目を集めているのが、TOKAIが提供する「OTSハウス」だ。電気を太陽光発電と蓄電池、水を独自開発の浄化装置を核とした生活水循環システムにより賄い、完全自給自足する従来にない住宅となっている。2011年から9年の歳月をかけて開発・実証が行われ、19年から販売を開始した。
鈴木辰麻理事・新規事業開発部長は「太陽光発電と蓄電池は多くのメーカーが取り扱っていますが、水まで扱って完全自給自足できる家を販売するのは当社しかありません。その独自性から昨年12月に住宅系の展示会に出展した際も、多くの方から関心を寄せていただきました」と反響を口にする。
OTSハウスは全6タイプをラインアップする。最上位クラスの「アドバンス」は、電気を系統電力に頼らずに太陽光発電と蓄電池で賄う。生活用水は建物敷地内に降る雨水を集め、最大1万7000ℓを貯水。この水を独自開発したRO(逆浸透膜)浄化装置を通して浄化、塩素消毒して生活水として利用している。キッチン・トイレを除いた生活排水も合併浄化槽で一次浄化した後、雨水と一緒にタンクに戻され、生活水として循環することを実現している。
昨年6月には、新たな方式で生活水を確保する「ウォーターコンシャススタンダード」を追加した。経済的な活性炭フィルターによるろ過システムを採用するもので、一次ろ過器で砂や鉄サビなど、二次ろ過器で色や臭いの原因物質を除去する。RO装置と同様に浄化後に塩素消毒で一般細菌を除去し水道水と同等レベルにする。

このほか、水道水を貯める大容量貯水タンクで断水に対応する「バリュー」に3日間自立する「バリュー3」を新たに加えるなど、導入しやすい低価格帯も追加している。
コンソーシアムを設立 仲間を全国から募る
昨年6月には、これまで静岡県内で進めてきたOTSハウスの販売を全国規模に広めるため、「雨と太陽で暮らす家。On The Spot コンソーシアム(共同事業体)」を設立した。住宅コンサルタントとして実績のある清水英雄事務所と協業し、全国で事業パートナー(代理店)と販売パートナー(会員)を募集。共同でOTSハウスの普及を推進していく構えだ。事業・販売パートナーは「OTSハウス」をはじめTOKAIが提供する規格住宅商品および水と電気の自給自足に必要な設備の取り扱いが可能となるとともに、毎年発表を予定する新商品の取り扱いも可能となる。「これまで当社単独で販売してきましたが、全国展開となると仲間が必要になります。OTSハウスのコンセプトに共感してもらえる企業の参加を募っていきます」と鈴木理事はアピールする。
昨年からの新型コロナウイルス感染拡大で、大規模災害が発生した場合、避難所に身を寄せるリスクもあることから、自宅でライフラインを確保することが従来にも増して重要になってきている。エネルギーと水を自給自足するOTSハウスのコンセプトはそうした新しい生活様式にもマッチすることから、今後より脚光を浴びていくだろう。