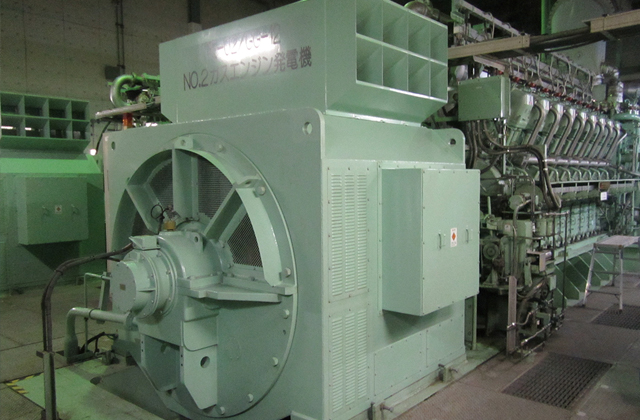【アーガスメディア=週間原油概況】
国際エネルギー機関(IEA)が、世界各国で経済回復が遅れていることを背景に、今年の石油需要予測を下方修正。また、OPECは、今年の需要予測に下方修正を加える一方、非加盟国の生産量予測を上方修正した。他方、米国の7月経済指標は、再度の経済活動自粛を受けて悪化。石油需要後退への懸念が強まり、欧米先物価格に下方圧力を加えた。
ただ、米国の週間在庫統計は減少。同国の石油ガスサービス会社ベーカー・ヒューズが発表する国内の石油ガス採掘リグ稼働数も減少し、過去15年で最低を記録した。さらに、米エネルギー情報局(EIA)が、今年の国内生産量予測に下方修正を加えたが、欧米先物を支えるには至らなかった。
一方、中東原油を代表するドバイ現物は、前週比で上昇。サウジ・アラムコが、経済活動の再開にともない、今年後半は石油需要が回復するとの見方を示した。加えて、サウジアラビアでは、新規の製油所が稼働開始。中国でも、新たな製油所が試運転を開始しており、需要回復への期待感が、より強く上方圧力として働いた。
【8月7日現在の原油相場(原油価格($/bl))】
WTI先物(NYMEX)=41.22ドル(前週比0.79ドル安)、ブレント先物(ICE)=44.40ドル(前週比0.40ドル安)、オマーン先物(DME)=44.01ドル(前週比0.27ドル高)、ドバイ現物(Argus)=43.68ドル(前週比0.56ドル高)