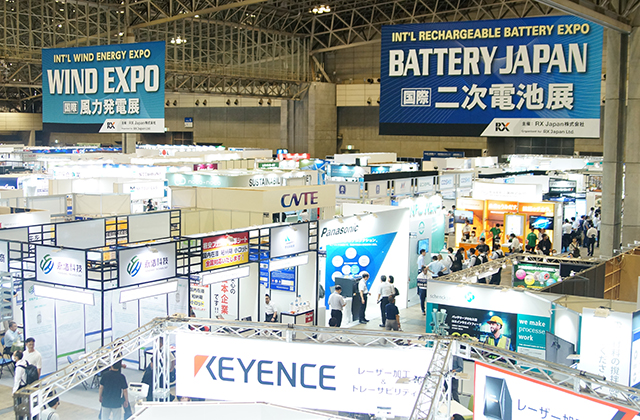【東京ガスエンジニアリングソリューションズ/独自の水処理技術で排水ソリューション提供】
東京ガスエンジニアリングソリューションズの子会社である東京ガスケミカルは、日本金属の板橋工場に、東京ガスグループ独自の水処理技術による排水処理ソリューションの提供を開始した。排水回収率の約60%向上を可能とし、大幅な節水により省コスト化・省資源化する。同工場では老朽化していた設備を更新し、フッ素含有排水回収システムと汚泥返送制御システムの導入により、排水回収率や排水処理効率の向上と、薬剤使用料の削減を目指す。加えて、中央監視システムの導入により、工場オペレーションの省力化や運営管理の高度化も実現。東京ガスグループは顧客の幅広い経営課題を解決し、環境価値向上や事業継続性強化、事業生産性向上に貢献していく。
【ベックジャパン/省エネ行動変容の研究成果を一挙紹介】
気候変動・省エネルギー行動会議(代表=中上英俊・住環境計画研究所会長)が主催する省エネシンポジウム「ベック・ジャパン」が都内で開催された。企業や団体が省エネの行動変容に関する研究成果を発表。「環境意識が高い若者の特長分析」(東京ガス)、「ネットゼロゴール達成に向けた電気自動車の役割」(日本オラクル)、「学校向け脱炭素WEBアプリの開発と実証について」(トインクス)など多様な研究成果が紹介された。電力中央研究所は「住宅用蓄電池やVTOHの導入拡大に向けた情報提供手法の模擬実証」を実施。卒FITを控える世帯では、蓄電池による経済的便益の詳報が蓄電池導入への関心度を高める結果となったとの成果を発表した。
【川崎市/地域新電力でエネ地産地消目指す】
川崎市はNTTアノードエナジーや東急グループなど7社と設立発起人会を開き、地域新電力「川崎未来エナジー」を10月に設立すると発表した。地域新電力は全国に60以上あるが、神奈川県内では初となる。これまで売電により市外に流出していた廃棄物発電などの再生可能エネルギー電源を活用し、市内の公共施設や民間事業者、一般家庭などに電力を供給する。年間発電量は国内最大規模となる見通しだ。資本金1億円のうち、市が51%を出資。NTTアノードエナジーが18.5%のほか、東急、東急パワーサプライや、金融機関パートナーとして川崎信用金庫やJAセレサ川崎など四社が出資している。同市は、地域自立型の脱炭素化・再エネ地産地消を実現するとしている。
【九州電力/米国で賃貸集合住宅の開発に参画】
九州電力は米国現地法人Kyuden Urban Development America社を通じて、三菱商事子会社のDiamond Realty Investments社と共同で、テキサス州ダラスの賃貸集合住宅開発事業に参画している。米国のデベロッパー、ウッドパートナーズ社と共同で、木造5階建て、総戸数280戸の賃貸集合住宅の開発を行う。高速道路に近く、ダラス・フォートワース空港や、ダラス中心部へのアクセスも良い。周辺には商業施設や病院、小学校などがある。2024年3月に完成予定だ。
【ENEOS/系統用蓄電池を設置 VPP事業体制に寄与】
ENEOSは8月、大型蓄電池を根岸製油所(横浜市)内に設置し、充放電の遠隔制御を開始した。蓄電池出力は5MW、容量10MW時だ。同社はVPP事業の体制構築に向け、2020年から喜入基地(鹿児島市)と中央技術研究所(横浜市)で産業用蓄電池を活用した実証実験に取り組んできた。これらの知見を基に、同社初となる系統用蓄電池を導入した。蓄電池の制御は、自社開発したAIを活用する。同社は根岸製油所に続き、室蘭事業所(出力50MW)や千葉製油所(出力100MW)でも蓄電池の設置を進めている。
【平田バルブ工業/液体水素用製品を拡充 独自の仕切弁を発売】
平田バルブ工業は、液体水素プロセスライン用仕切弁の独自開発に成功し、液体水素用の製品ラインアップを拡充した。液体水素実液で漏えい試験を行い、ほぼ無漏えいの優れた締切力を持つバルブであることを確認した。今後も高圧化、大口径化、逆止弁開発を含むラインアップを拡充するとともに、供給体制を整備し、拡大する液体水素関連施設への需要に応える構えだ。同社の液体水素プロセスライン用玉形弁は、JAXA種子島宇宙センターのロケット燃料供給設備に採用され、今日まで使用され続けている。
【エクサウィザーズ/中国電力の「広島エコシステム」を構築】
AIを活用したサービスを提供するエクサウィザーズ社は、中国電力が運営する地域特化のビジネスサイト「広島エコシステム」を構築した。広島県内の企業や団体の連携を目的とし、同社の企業検索に特化したAI検索エンジン「exaBase企業検索」を活用することで、自由なキーワードによる意図に沿った、連携先企業などの探索ができる。「コンサルティング」や「生成AI」といったワードによる検索も可能。その結果を活用して中国電力が広島銀行と連携し、地域企業のサポートも行う。
【関西電力/停電費用保険を販売 生保との協業は国内初】
関西電力は日本生命の子会社であるニッセイプラス少額短期保険と協業し、7月に「停電費用保険」の販売を開始した。近年、自然災害は増加傾向にあり停電リスクが高まる中、停電により思わぬ費用が発生したという声から開発された。電力会社と保険会社が連携して個人の顧客に対し停電時の補償をする保険を提供するのは国内では初となる。
【NextDrive/EV充電パターンを推定 ステーション設置に活用】
NextDriveはe―Mobility Power、東京大学と共同で、EVユーザーの自宅での基礎充電行動の推定に関する共同研究を開始した。研究にはスマートメーターのBルートデータの消費電力(W)と累積電力量(kW時)を用いる。家庭での充電頻度や充電量などを把握し行動推定モデルを構築。充電ステーションの設置検討や新サービス開発などへの活用を目指す。
【ヤンマーHD/船舶の脱炭素化実現へ 燃料電池システムを構築】
ヤンマーホールディングスのグループ会社であるヤンマーパワーテクノロジーは、船舶の脱炭素化を実現する「舶用水素燃料電池システム」を商品化した。同社は水素燃料電池を搭載した試験艇での実証運航試験や70MPa高圧水素充てん試験の実施など、水素燃料電池船の社会実装に向けたさまざまな取り組みを進めてきた。こうした技術や知見と舶用エンジン事業のノウハウを融合し、蓄電や電力制御、水素貯蔵などのシステムを含む設計を行い、船舶全体の脱炭素化とデジタル化に対応するシステムを提供していく構えだ。
【凸版印刷/電極部材の量産で水素エネ市場に参入】
凸版印刷はこのほど、水素エネルギー市場への参入に向け、燃料電池などで中核となる重要な部材のCCM/MEAの量産を始めた。世界初となる独自の製造方式で、触媒層付き電解質膜の生産設備を高知工場に導入。8月から販売している。この設備は、同社がこれまで大型カラーフィルターの製造で培ってきた大サイズ均一塗工技術や、枚葉基板搬送技術などの製造技術を活用しており、CCM/MEAを枚葉式で量産できる。年間生産枚数は最大6万枚で、車やドローンなどの移動体用燃料電池向CCM/MEAに換算すると、年間約60万枚分に当たる。同社は今後、水素を「つくる」「ためる・はこぶ」「つかう」の全領域にCCM/MEAを展開し、水素社会の実現に貢献する方針だ。