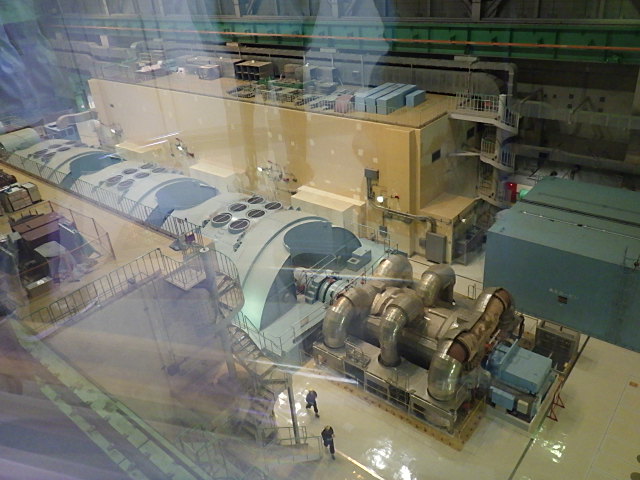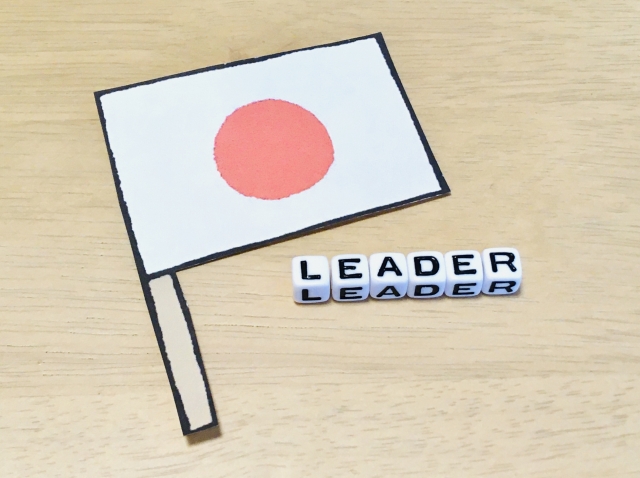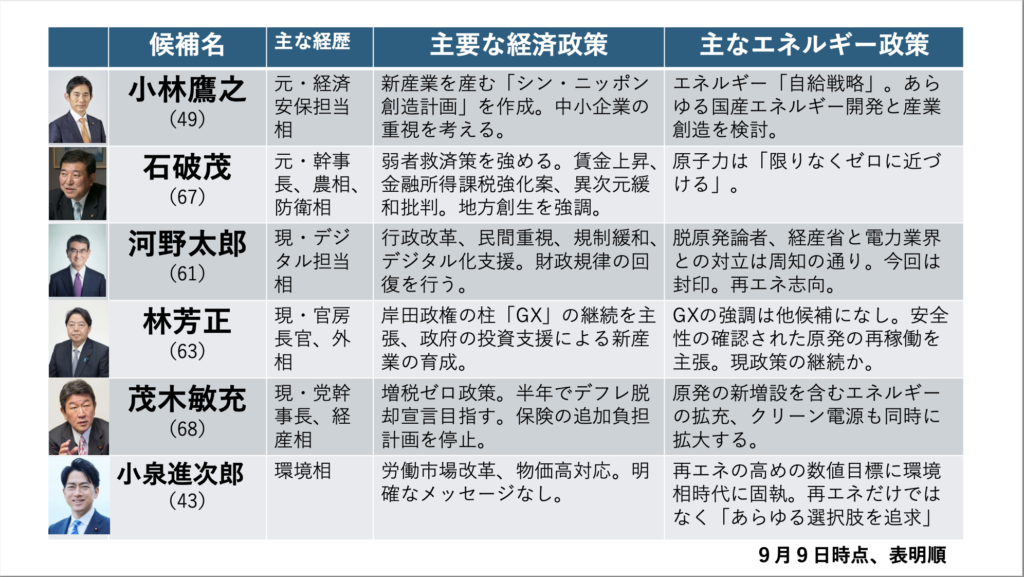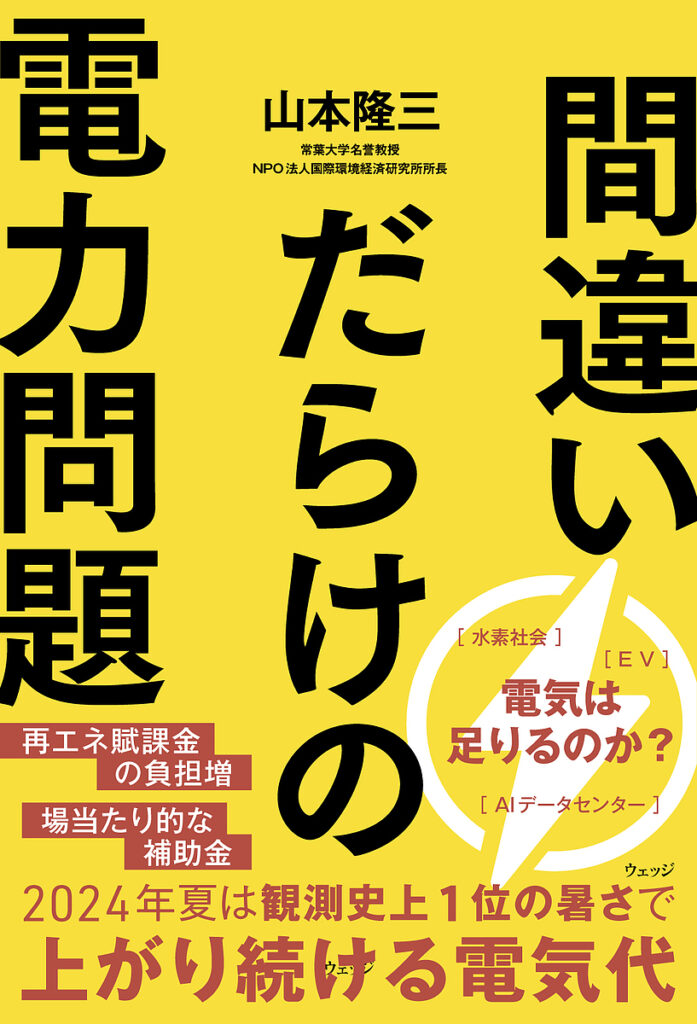米国大統領選挙は11月5日の投開票日に向け、民主党・ハリス副大統領と共和党・トランプ前大統領がしのぎを削り合う展開が続く。両者の支持率は拮抗しており、また各州に配分された代議員票を競う方式から、事実上ペンシルベニア、ジョージアなど、接戦7州の帰趨が勝敗を決し、どちらに転んでもおかしくない。

石油・エネルギーに関しては、脱炭素化政策の継続を目指す民主党・ハリス陣営に対し、共和党・トランプ陣営がその即時全面撤廃を唱え、厳しく対立する。ただし、米国の石油開発・生産は民間・市場主導で、政府の直接的な影響力は限定的。むしろ、政策が将来の需要見通しに影響を与え、それが上流部門投資に反映される間接効果が大きいだろう。事実、最も鮮明な争点は電気自動車普及を巡るもので、民主党は自動車排出ガス規制などを通じて強制的な普及策を採り、これを共和党が緩和・撤廃しようとする。
いずれにせよ、脱石油政策はあっても石油政策不在の民主党・ハリス陣営。「脱炭素化からの解放」を石油・エネルギー価格抑制策として、あくまで国内本位に主張する共和党・トランプ陣営。この両者に共通して欠落する視点は、「産油国アメリカ」が国際石油供給において現実に果たし、また、果たすべき役割である。世界が分断の危機に面している今日、現実の国際石油・エネルギー供給秩序の維持は重要な戦略課題であり、その中で「産油国アメリカ」の役割を適確に位置付ける必要がる。
ダイナミックな国際プレーヤー
米国の「シェール革命」は、2000年代半ば以降の石油高価格に対する供給側の応答として起こり、10年代に米国原油生産量を倍増させ、同国を世界最大の産油国に押し上げた。一般に、石油価格が低位安定期から継続的な高騰期へと移行する時期は、豊富低廉の中東原油への依存度が高止まりし、本格的な新規供給源の開発及び需要抑制・代替が課題となる。米国シェール革命は生産技術突破によってこれに応え、2015年以降に価格高騰を終息させる主因となった。
一方、米国の石油需要は、NGL(天然ガス液)由来のエタン・LPGが石油化学原料として増勢にあるが、燃料油需要は既に05年までに飽和期を迎え、総量として漸減の趨勢にある。
したがって、石油純輸入量が劇的に減少した。NGLを含む広義の石油は、05年に日量1200万バレル超の純輸入だったのが20年に純輸出へと転じ、23年は日量170万バレルの純輸出量を記録。NGLを除く狭義の石油の純輸入量も、05年の日量1200万バレル超から23年には日量80万バレルへと激減した。単純に、日量2000万バレル超(NGL由来を除けば1650万バレル)の米国石油需要量と対比すれば、自給は十分に達成されている。
自給率の向上は、自給自足という、海外の影響を受けず国内需給が自己完結する静態的なイメージで論じられやすい。在任中しばしば「アメリカはもはや中東の石油を必要としない」と言明したトランプ前大統領がその好例である。
しかし実態は遥かに動態的で、米国は輸出入ともに旺盛である。昨年、日量170万バレルの純輸出は、日量850万バレルの輸入と日量1000万バレル強の輸出の結果だ。輸入の過半は原油・日量650万バレル。輸出は原油・日量400万バレル強、石油製品・日量300万バレル強、LPG・エタンが日量300万バレル弱。原油は国内製油所の高度分解能力に適合する重質油を輸入する一方、軽質の国産原油を輸出。LPG・エタンおよび石油製品は輸出に傾斜している。狭義の石油の場合、米国の輸出は基本的に石油製品主導であり、精製者が製品輸出を梃子として処理量を上げ、これに合わせて国内外から柔軟に原油を選択する姿が浮かび上がる。
23年の輸出・輸入量を合計した米国石油貿易量を05年時点と対比すると、広義の石油は日量400万バレル弱、狭義の石油も日量100万バレル増大。国内生産が倍増以上となる中で、米国の石油貿易はむしろ活発化し、国際市場への関与を深めてきた。「シェール革命」は米国を新たな石油貿易センターとして台頭させたのであり、静態的な自給自足へと退却させたのではない。
民主主義のための石油
米国の国際石油供給者としての台頭は、米国および西側全体の安全保障上の立場を強めた。
ロシアのウクライナ侵略に西側が正面から対峙する上で、米国の石油供給力が果たした役割は大きい。もし05年当時と同様、米国が国内生産量の2倍に相当する日量1000万バレルの原油を輸入し、そのうちの45%が中東・アフリカ産であったとすれば、西側のロシアへの対抗措置はより慎重にならざるを得なかっただろう。欧州が石油供給の対露依存脱却を図り、輸入源を中東、アフリカ、中南米に振り替えようとしても、大手輸入者としての米国とそこで競合すれば、実現が難しい。ロシアは対西側・石油輸出削減によって外交上の恫喝を加えることが容易となり、これが西側の姿勢をより融和的なものとしただろう。
しかし実際には、昨年の米国の原油輸入・日量650万バレルのうち、7割以上を北米(カナダおよびメキシコ)産が占め、中東およびアフリカ産は合わせて17%、日量約100万バレルに過ぎない。他方、欧州向け原油輸出量は21年の日量110万バレルから昨年・日量180万バレル、今年上半期・日量190万バレルと伸び、軽油輸出量も2021年の日量8万バレルから昨年・日量18万バレル、今年上半期・日量28万バレルと増大。欧州のウクライナ危機後の対露依存脱却、およびフーシ派による紅海攻撃に伴う中東産石油輸入の減少を、米国が対欧輸出増によって支えている。このように米国の石油供給力は、米国のみならず西側全体の安全保障に大きく寄与している。
1985年末にサウジアラビアが原油固定価格制を放棄して市場連動方式を採り、90~91年の湾岸戦争で米国率いる多国籍軍がイラクのクウェート侵略を撃退して以来、米国の安全保障の傘の下で、西側消費国の協調的備蓄放出とサウジアラビアの生産余力の機動的運用を組み合わせて不測の供給ひっ迫に備える、市場本位の開放的な国際石油供給体制が確立した。冷戦終結時に誕生したこの秩序は、約40年の歳月を経て、国際社会が分断の時代に転落しつつある中で、次々と試練に直面している。
米国・西側は、国際石油秩序という高次の理念を掲げつつ、分断の現実の中で、先ず民主主義陣営内で市場本位の開放的な石油供給を維持・強化せねばならない。その中で、米国の石油供給力は大きな柱であるが、西側全体の需要を満たすには全く過小であり、他地域、特に中東・サウジアラビアとの連携が不可欠である。そのような広い連携の中に位置付けてこそ、米国の供給力も有効に活用できる。そもそも米国の原油輸入に占める中東産の比率は2000年代でも25%前後であり、米国一国の石油供給確保のみが目的であるならば、中東の地域安全保障を担う必要はない。中東の石油が世界全体、とりわけアジア太平洋地域の供給源として必須であればこそ、米国がこの地域を安定させ、連携して自由世界のエネルギー供給を確保しつつ、国際秩序を維持する戦略的理由がある。
しかしロシアのウクライナ侵略に際し、西側は脱炭素化の目標堅持を唱えるだけで、石油高価格を梃子とした積極的な石油増産と需要抑制という石油政策の基本を無視してきた。中東では、イスラエルによる酷薄なガザ侵攻によってパレスチナ側の死者が4万人を数え、さらにレバノンのヒズボラ、イエメンのフーシ派、加えてイランに対して軍事攻撃が拡大するのを、米国は制御できずにいる。加えて中国が南・東シナ海における軍事圧力を強める中で、米国とサウジアラビア・中東湾岸の石油資源を、開放的な国際供給体制の下で連携させて自由世界のエネルギー供給を確保する、いわば「民主主義のための石油」という戦略的思考が必要だが、脱炭素化を金科玉条とする民主党、米国第一に拘泥する共和党、いずれもそのような発想から遠い。
であれば、通商国家・日本から、市場本位の開かれた国際石油供給という大枠の中で、「産油国アメリカ」とサウジアラビア・中東湾岸との連携を柱とする自由世界のエネルギー確保を図る、現実的・戦略的な構想を積極的に打ち出し、西側全体の議論をリードしていくべき時、ではなかろうか。
石油アナリスト 小山正篤