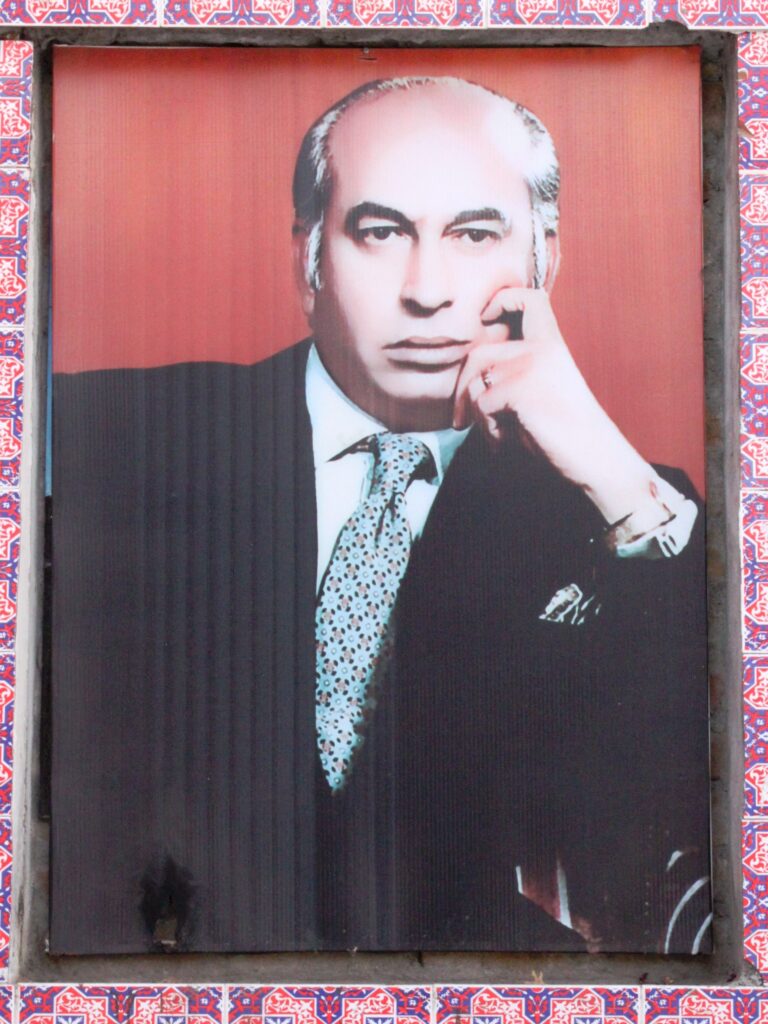◆人事院有識者会議 国家公務員の人材確保に向けた提言
1.「人事行政諮問会議 最終提言」の問題意識
3月24日、人事院の有識者会議「人事行政諮問会議」は、国家公務員の人材確保に向けた「最終提言」をまとめた。「最終提言」本文の「はじめに」の部分では、大要、次のように指摘する。〈近年の国内外のさまざまな情勢の変容を受けて、人材獲得の面でも状況変化が甚だしく、公務組織の各層において人材確保が危機的な状況に陥っている。人材獲得の競合相手となる民間企業がニーズに沿った変革を講じている一方、国家公務員の人事管理はこの状況変化に十分応えられていない〉
●「人事行政諮問会議 最終提言」本文より 3月24日
「はじめに ~未来をつくるための改革を、今~」(抜粋)
国家公務員は、国民の安全・安心な暮らしを守り、この国を一層発展させる、そして未来への責任も担っている。しかし今、その人材確保が公務組織の各層において危機的な状況に陥っている。……複雑化・多様化する国際情勢、生成AIを始めとしたテクノロジーの急速な進展、わが国の生産年齢人口の減少、公的分野における企業活動のプレゼンスの拡大など、国内外においてさまざまな変容が生じている。組織を支える人材に目を向ければ、公務の人材獲得の競合相手となる企業では、働き方やキャリア形成に対する意識の変化に対応し、採用手法、職場環境、雇用慣行や処遇などの面で、特に若年層を中心としたニーズに沿った変革が講じられている。いかにして優秀な人材を集め、強靭で持続可能な組織をつくり、事業を展開していくか工夫を重ねている。公務組織においても、近年、採用試験の見直し、長時間労働の是正や柔軟な働き方の推進、初任給の引上げや諸手当の見直しを含む給与制度のアップデートを講じてきた。しかしながら、国家公務員志望者数が増加に転じているとは言えず、若手職員の離職は増加傾向にある。
……官民を問わず、今の若年層は一つの組織で定年まで働くことを当然と考えていない。自身の市場価値を高めるべく、仕事を通じて早い段階から成長できる環境があるかを重視する傾向がある。国家公務員の人事管理は、この状況変化に十分応えられていない。
参考=「人事行政諮問会議 最終提言」 全体の要約 3月24日(抜粋)
「公務の危機は、国民の危機」
国家公務員の人材確保は危機的な状況
◇採用試験申込者数の減少
10年前と比べ、総合職試験・一般職試験いずれも約3割減
参考=22歳人口は、近年大きな変動なく推移
2015年115.9万人→23年116.3万人
◇若年層職員の離職の増大
直近では、総合職試験採用者が200人超離職
これら2点の主な背景
・生産年齢人口の減少
・勤務環境、処遇面での魅力の低下
・若年層のキャリア意識の変化
↓
・国民生活に大きな影響
・国際社会での日本の影響力低下
↓
公務組織の生産性を高めつつ、国の未来を支えるため、人材マネジメントのパラダイムシフトを
〇使命感を持って意欲的に働ける公務
「国家公務員行動規範」の策定と周知・啓発
・“国民を第一”に考えた行動
・“中立・公正”な立場での職務遂行
・“専門性と根拠”に基づいた客観的判断
〇年次に縛られず実力本位で活躍できる公務
・官民給与の比較対象となる企業規模の引上げ
・政策の企画立案、調整などの職務に見合った外部労働市場も考慮した給与水準の設定
・納得感と成長につながる評価の実効性向上とマネジメント力の養成
・初任管理職の給与水準の引上げ/在級機関の廃止
〇働きやすく成長を実感できる公務
・業務効率化と長時間労働の改善
・短時間勤務の拡大と裁量勤務の導入
・資格取得の支援や兼業・副業の後押し
・転勤する職員へのインセンティブの充実
〇多くの人から“選ばれる”公務
・オンライン試験の導入/採用プロセスにおけるインターンシップの活用
・地元志向のニーズに応える採用スキーム
・公務の戦略的ブランディングの推進
・公務内外の人材に魅力的な公務の実現
かつて中央官庁のキャリア官僚は、「ホテルおおくら」「通常残業省」などと言われるほどの過重な業務をこなしてきた。その中で行政機構も、デジタル化などでの業務効率化、長時間労働の是正などに取り組んできた。しかし、行政を取りまく最近の情勢は、安全保障(国際政治、経済安保)、財政状況、気候変動、人口減少・高齢化など、一層厳しさを増している。また、国会対応(議員説明、議会質問対応など)などはなお残り、少数与党下では政策が政治の動きに翻弄される面もある。こうした状況が影響している面もあるのか、上記「人事行政諮問会議 最終提言」は、国家公務員の人事管理の現況を次のように指摘する。〈官民を問わず、今の若年層は一つの組織で定年まで働くことを当然と考えていない。自身の市場価値を高めるべく、仕事を通じて早い段階から成長できる環境があるかを重視する傾向がある。国家公務員の人事管理は、この状況変化に十分応えられていない〉
「最終提言」は一方で、人材獲得で競合する民間企業では、〈働き方やキャリア形成に対する意識の変化に対応し、採用手法、職場環境、雇用慣行や処遇などの面で、特に若年層を中心としたニーズに沿った変革〉を講じているとする。企業では、自社を退職した人間を改めて受け入れる制度(アルムナイ採用)の活用が広がる。官においても人材が官公庁と民間企業の間で流動的に出入りするリボルビングドア(回転扉)の取組み促進が必要であろう。また、女性活躍の拡大などに伴い勤務・転勤の在り方も課題である。「最終提言」は次のように指摘している。〈ワークスタイルやライフスタイルが大きく変わるような転勤の必要性を改めて見直すべきである。転勤を伴う人事異動は、育児や介護など個人の置かれた事情を最大限斟酌する必要がある〉