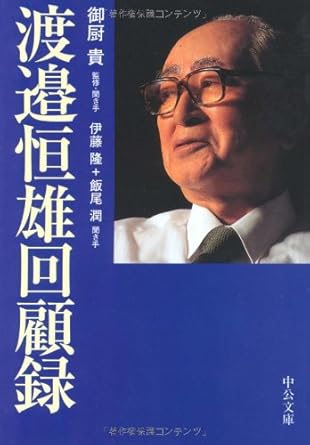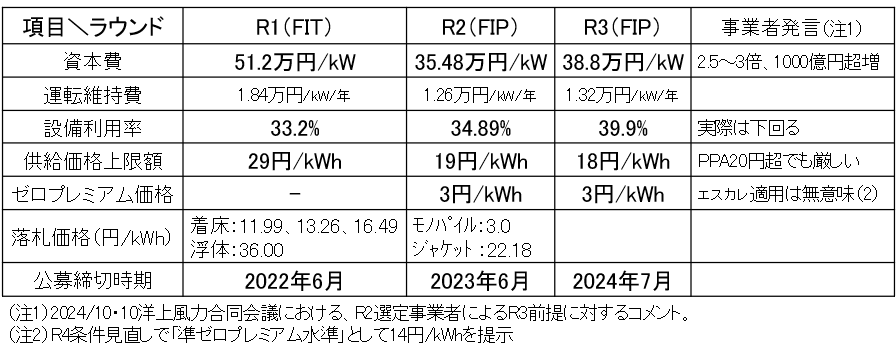2日後の1月17日、1995年の阪神・淡路大震災発生から30年を迎える。この阪神・淡路大震災において、都市ガス事業者である大阪ガスは、最終的な供給停止戸数が85万7400戸という未曽有の復旧作業に全国のガス事業者の支援を得て取り組んだ。都市ガス業界は、この激甚災害における復旧作業などの経験も糧として、以降、保安の高度化、災害時の対応力の強化の取組をより加速させた。また大阪ガスはその後、被災地域の復興にインフラ事業者として参画した。1月17日が近づくにつれ、年末から、メディアでは社会面などで大震災後のこの30年を振り返る記事が増えてきた。大震災から30年ということは、他のインフラ事業者においてもそうだが、現在60歳の社員は当時30歳、復旧作業に従事した経験者は減ってきている。メディアにおいても現地での取材を経験した人は少なくなっているであろう。その中で、いま企業広報としては、記者クラブの人たちに、当時の復旧作業に携わった者の経験談、その後の都市ガス業界の保安の高度化、災害時の対応力強化への取組などを説明していることであろう。今回、筆者は、エネルギーフォーラム誌より大震災30年を受けて経験談を書くようにというご依頼を受けた。大震災時、筆者は36歳の大阪ガス社員。本社企画部門におり、現地での復旧業務に直接携わったわけではなく、本社で中央官庁対応などに関わっていた。現場での復旧対応の過酷さと比べることのできるものでは全くないが、大震災対応の一側面として記憶を辿ることをお許しいただきたい。
復旧作業中、被災者から激励を受けることも(写真提供:大阪ガス) ◆阪神・淡路大震災における都市ガスの復旧作業(振り返り)
まずは阪神・淡路大震災における都市ガスの復旧について振り返っておきたい。(当時のことを鮮明にご記憶の方は読み飛ばしていただけば結構です。)さて、内閣府の「防災情報のページ」 にある「災害史・事例集」 の中に、内閣府(当時の国土庁)が97~99年に実施した「阪神・淡路大震災の教訓情報分析・活用調査」 の成果として、「阪神・淡路大震災教訓情報資料集」 という項目がある。この資料集において、「ガス事業者の緊急対応」「ガスの復旧」 についても取り上げられており、災害発生から復旧完了までの要点がまとめられている。
参考= なお大阪ガスにおいても、95年10月19日に創業90周年を迎えたのを機に社史「大阪ガスこの10年 1986-1995」(以下、大阪ガス社史とする)を編纂している。その第7章は「阪神大震災と復旧活動」 にあてられており、当然ながら同様の内容が記載されている。
内閣府 「阪神・淡路大震災教訓情報資料集」より
◎第1期・初動対応(初動72時間を中心として)
●ガス事業者の緊急対応 ( )内は筆者による補足
1 .地震発生直後から、大阪ガスの本社および各地区に対策本部が設置され、被害状況の調査・情報収集が始められた。地震翌日には、日本ガス協会に対し応援要請が出された。
・地震発生直後、テレメータや被害通報などによる被害情報の収集が行われた。
・地震当日10時30分に社長が本社災害対策本部長に就任するまで、中央指令室チーフ、(その後早々に到着した)取締役、常務、副社長(代表取締役)の順でそれぞれ代行した。
メモ……当時の領木新一郎社長の自宅は西宮市。地震発生直後に運転手が自宅に赴き、被害が大きかった阪神高速ではなく、地道を通って本社に到着した。この間、西宮市、尼崎市などの被害状況を目視、これはその後の供給停止エリアの判断に生かされた。
・地震発生直後から本社と各地区対策本部を結ぶTV会議システムが設けられ、被災状況把握と対策の検討に貢献した。
・ポートアイランドの兵庫供給部は建物自体は機能していたが、交通アクセスなどの問題から地区対策本部を西宮市に移動した。 大阪地区では、交通渋滞を回避するために大阪供給部十三保安基地を前線基地とした。
・地震当日中には、復旧日数1カ月半、必要な復旧人員7500人との判断が下され、地震翌日の1月18日、日本ガス協会に対して応援要請が出された。
2 .被害の状況と供給停止による影響を勘案しての検討が行われ、ミドルブロック単位での供給停止が順次決断された。最終的には85 万7400 戸の供給停止となった。
・当初は正確な状況把握は困難だったが、行政機関、テレビ・ラジオの情報、顧客の通報、さらにヘリコプターからの目視により、被害情報が収集された。
・午前11時現在の漏洩通報件数の増加傾向から判断して、神戸地区の2ブロックの遮断が決定された。以後、当日中に(神戸1、2、3、4および大阪北7の)5ブロック計83万4千戸のガス供給が停止された。
・18日以降には、神戸5ブロック内で二次災害防止のため三つの団地への供給を停止するとともに、ガス管内に水が流入したため14カ所で局部的に供給を停止、最終的に供給停止戸数は85万7400戸となった。
◎第2期・被災地応急対応(地震発生後4日~3週間)
●ガスの復旧
1 .都市ガスの復旧には、日本ガス協会を通じて全国のガス事業者からの応援体制がとられた。大阪ガスおよび関係会社を含めた作業者数は、最大時で約1 万人体制となった。
・1月19日の第1次応援隊1704名を皮切りに、日本ガス協会を通じて全国のガス事業者の応援体制がとられた。
・震度7の被害甚大地区に着手する3月からは3712名の応援隊と大阪ガスの復旧作業員6000名を合わせた約1万人体制での復旧作業が行われた。
2.復旧作業は交通渋滞に悩まされたため、被災地域内に車両基地・前進基地を確保するなどの工夫もとられた。衛星通信やMCA無線が活用され、またコンピューターによるデータベース、復旧シミュレーションも行われた。
多くの応援隊が 集結した大阪ガスの前線基地(写真提供:大阪ガス)・復旧作業は交通渋滞に悩まされたため、被災地域内に車両基地・前進基地を確保したほか、早朝に移動するなどの工夫をこらして、復旧作業が進められた。
・前進基地の設置にあたっては、衛星通信用小型可搬局が有効だった。全国のガス会社は、同一のガス事業用無線を所有しているため、MCA無線も活用された。
・航空写真および実踏査による被害把握を行ってデータベースを作成し、投入班数、復旧完了時期のシミュレーションなどが行われた。
3 .長期化が予想されたことから、停止による影響の大きい公共施設、病院などの調査、復旧手配、代替燃料の確保などが図られた。病院、ごみ焼却場、斎場などに直結する中圧導管は2 月上旬にほぼ全面復旧した。
・長期化が予想されたことから「特需隊」を編成し、停止による影響の大きい公共施設、病院などの調査、復旧手配、代替燃料の確保が図られた。
・ガス復旧の遅れに対処するため、病院など重要施設200カ所余りへの代替エネルギー供給、避難所などへのカセットコンロの配布、入浴支援なども行われた。行政からの情報が実際の状況と異なっていることなどの苦労もあった。
・大手病院やごみ焼却施設などに直結する中圧導管は、2月上旬にほぼ完全復旧した。
メモ……大阪ガス社史は次のように記載する。〈病院など、社会的に重要な施設に対しては、LPG、LNG(液化天然ガス)、CNG(圧縮天然ガス)などを利用して、代替エネルギーの提供を行った〉ガス事業者の場合、日頃から病院の設備担当などとのコミュニケーションが取られていることも多く、ニーズの把握にもその強みが発揮されるといえる。
4 .低圧導管の復旧は、管内に侵入した水・土砂の排出に手間取った。大阪ガスの完全復旧は当初予定からは大きく遅れた4 月11 日となった。
・低圧導管の復旧は、管内に流入した水や土砂に妨げられたため、吸引式水抜き機が開発されたほか、下水管の洗浄に用いられる高圧洗浄機、バキュームカーなどが動員された。水道事業者との作業工程に関する打ち合わせも行われた。
・倒壊家屋により復旧活動が妨げられたため、復旧先行隊、復旧フォロー隊などが設けられ、効率的な復旧作業が行われた。
・2月末には65.2%、3月末には96.8%と復旧は進捗し、4月11日に一部地域をのぞき復旧作業は完了、4月20日までに不在顧客を除く全てのガス供給を再開した。管内に侵入した水・土砂の排出に手間取ったため、当初予定の1カ月半からは大きく遅れた。
※エネルギーフォーラム誌12月号の特集
エネルギーフォーラム誌は、2024 年12 月号 で「阪神・淡路大震災の記憶つなぐ ガス復旧に見る保安・防災の進化」と題する特集を組んだ。「今につながる 30 年前の経験 関係者が明かす当時の奮闘記」 の項では、〈地震発生直後、都市ガス・LPガス業界は数々の工夫を凝らしながら復旧に向けて奮闘した。震災から30年の節目が近づく今、この経験から得られた教訓と、その後の取組を振り返る〉として、大阪ガスと伊丹産業の復旧作業を改めて紹介した。
◎エネルギーフォーラム24年12月号〈大阪ガス 都市ガス業界85日間の軌跡 大災害が残した教訓〉〈……(復旧に向けてのガス業界あげての活動を紹介した後、)~阪神以降の対策が効果発揮 一層の強靭化が進行中~ 大震災を機に、業界は地震対策を強化した。ガス導管事業を承継した大阪ガスネットワークでは、供給停止する範囲を抑えるために更なる供給ブロックの細分化を図り、当時の55ブロックから727ブロックに分割。被害のないブロックは供給を継続するとともに、供給停止ブロックを最小限に抑えることで早期復旧につなげる。加えて、低圧導管網にはPE管を積極的に導入し、新設低圧管には原則PE管を全数採用。PE管は震災時の約1200kmから約1万8300kmに延長し、耐震性が大幅に向上した。こうした取り組みが功を奏し、18年6月、大阪府高槻市などで最大震度6弱を記録した大阪府北部地震では、発災から1週間で完全復旧することができた。阪神・淡路大震災は都市ガス業界にとって未曽有の大災害であったが、多くの教訓を得ることとなった。30年を経た今、この経験を糧に業界は前進を続け、更なる強靭化を追求している。〉
このエネルギーフォーラム誌の特集の中には、当時、『ガス事業新聞(現ガスエネルギー新聞』の若手記者であったエネルギーフォーラムの井関晶編集主幹 の現地での取材経験を記したものもある。長年メディアの人たちとお付き合いしていると、世代や担当分野で異なるが、特に若い頃のある出来事についての鮮烈な取材体験が語られることがある。阪神・淡路大震災も、そして東日本大震災での被災地取材もそうであったろう。東日本大震災では、当時、関西から応援に入った記者たちも大きなショックを受けて帰ってきた。また、ある世代の大阪社会部の記者にとっては、若手時代のグリコ森永事件の取材経験が共通体験になり、後年、各社の社会部長を務めた人たちが集う「同窓会」が開かれていた。井関氏の手記には、阪神・淡路大震災の取材で「エネルギーはとにかくライフラインなんだ」という強い思いの原点が形成されたことが語られている。
◎エネルギーフォーラム24年12月号エネルギーフォーラム井関晶編集主幹〈地震翌日から現地取材を敢行 ライフラインの重要性を痛感〉〈……当時、私は25歳で、都市ガス業界紙「ガス事業新聞(現ガスエネルギー新聞)」の編集部に所属する駆け出しの記者だった。……(1月17日、当時の専務と)東名高速を夜通し飛ばして、大阪ガス本社に到着。そこを拠点に21日までの4日間、ガス復旧隊に随行する形で兵庫支社、今津事務所の地震対策本部、西宮市などの被災現場を取材した。大阪市内の様子は平時とほぼ変わりなかったが、西に向かうにつれ、衝撃的な光景が広がる。……そこから85日間に及ぶ都市ガス業界挙げての復旧活動が始まったわけだが、取材の中で痛感したのは「エネルギーはとにかくライフラインなんだ」との思いだ。新潟中越沖、東日本、熊本、胆振東部、能登半島……。その後も大震災は相次いだ。南海トラフや首都直下に備えるための教訓はそこにある。〉