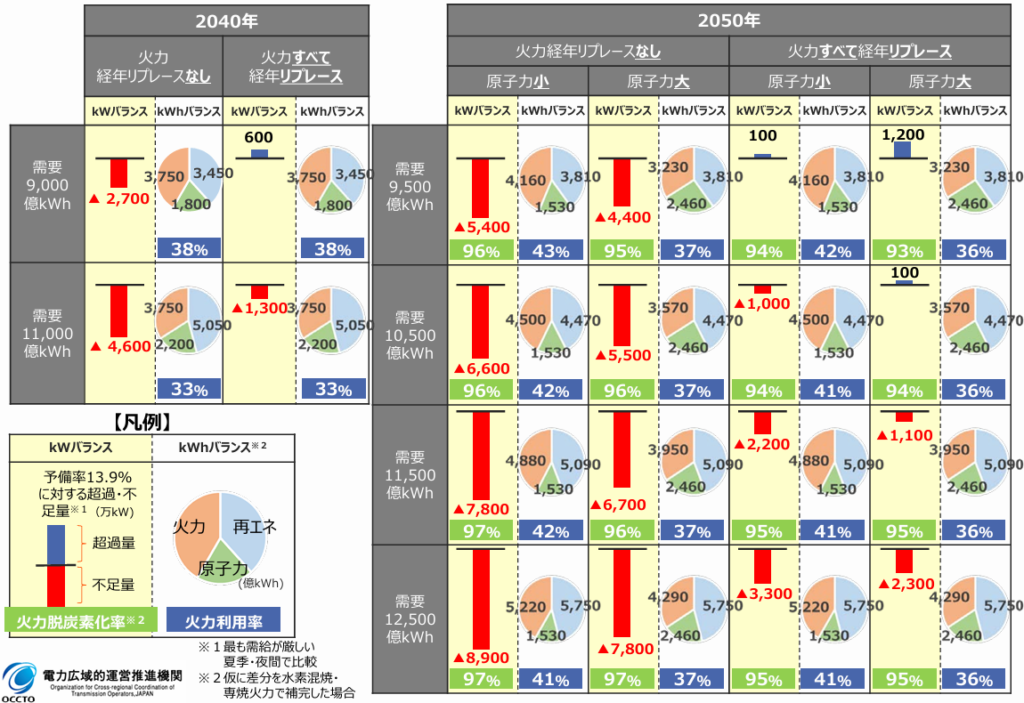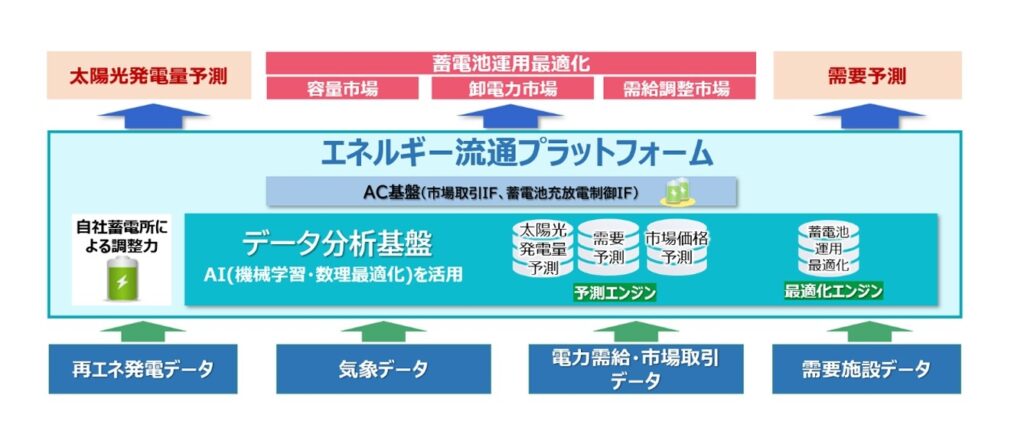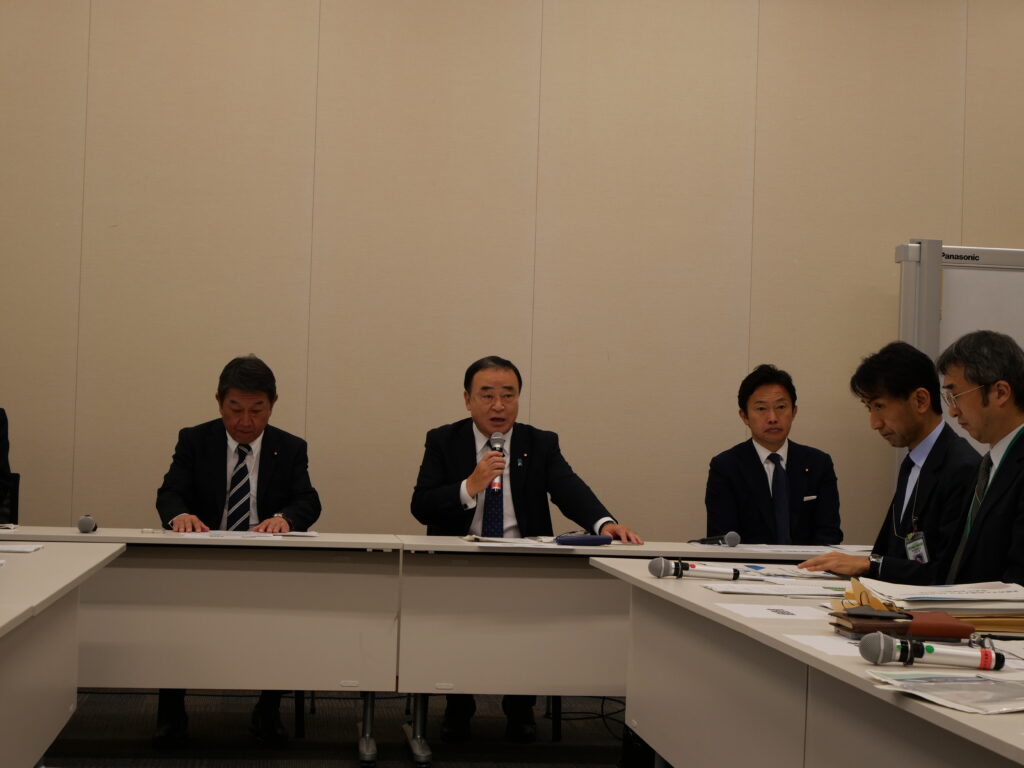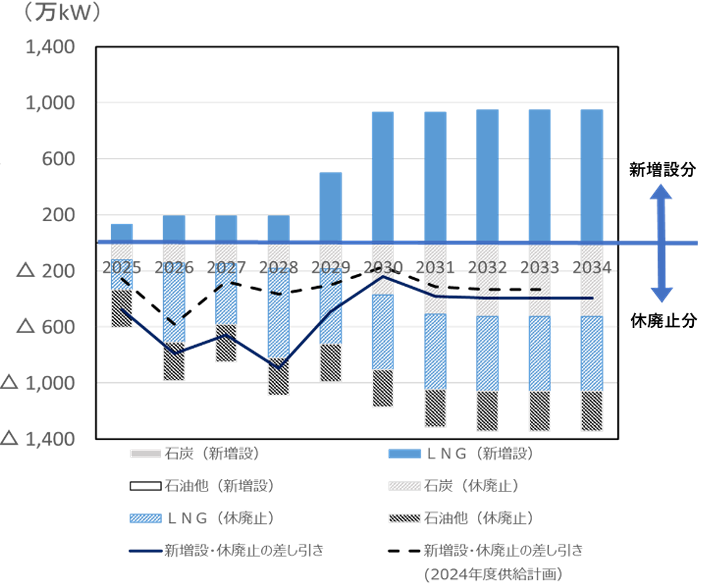東京ガスは10月、新たな組織として地域共創カンパニーを発足させた。自治体の脱炭素化ニーズの高まりにどう対応していくのか。小西雅子カンパニー長に聞いた。
【インタビュー】小西雅子/東京ガス常務執行役員地域共創カンパニー長
―10月1日に地域共創カンパニーが発足しました。その狙いを教えてください。
小西 自治体の脱炭素化ニーズに迅速に応え、これまで以上にスピード感のある脱炭素化の提案を実現し、地域の課題解決をお手伝いしていくことをミッションとしています。
当社グループが2月に発表した中期経営計画「Compass Transformation23-25」では2023~25年をビジネス変革の期間と位置付け、その主要戦略の一つに「カーボンニュートラル(CN)実現に向けたまちづくりの取り組みによる地域課題の解決」を掲げています。これは創業以来培ってきた「社会を支える公益事業者としての信頼」「地域密着力」を生かし、強靭で魅力あふれる持続可能なまちづくりのためのソリューションを地域・コミュニティーに提供していこうというものです。
そのためには、都市ガス普及拡大の推進だけではなく、脱炭素ソリューションを本格展開することによるBtoG(地域行政対応)機能の充実を図ることが極めて重要だと考えます。当社がハブとなり、自治体や大学、卸先ガス事業者を含む地元企業、金融機関、商工会議所といったステークホルダーをつなぎ、エネルギーをコアに地域のさまざまな課題解決を通じて価値を共創しながら経済循環の創出に貢献し、地域・コミュニティーとともに発展・成長していくことをパーパス(存在意義)として活動していきます。
 こにし・まさこ 1988年お茶の水大学家政学部卒、東京ガス入社。
こにし・まさこ 1988年お茶の水大学家政学部卒、東京ガス入社。
執行役員地域本部広域営業部長、カスタマー&ビジネスソリューションカンパニー法人営業本部長、
常務執行役員サステナビリティ推進部担当などを経て2023年10月から現職
自治体のパートナー企業に 豊富なソリューションが強み
―年度の途中に新組織が立ち上がるのは異例です。
小西 エネルギー企業のみならず、コンサルタント会社やデータ関連企業など、この自治体のパートナーポジションを狙う競合企業は数多くあります。脱炭素先行地域の第三回目の選定において、提案の実現可能性を高めるために民間事業者との共同提案が必須とされたこともあり、自治体側も民間のパートナーを探していて、勝負は今後1~2年でついてしまいます。競合会社が選ばれてしまうと、当社はご提案の機会を永遠に失う可能性もありますから、さまざまな組織に散在していた脱炭素のソリューションを集約し、スピード感を持って提案が行える体制を早期に整える必要がありました。
当社グループが関係する自治体は120ほどありますので、その中でどの自治体で当社のソリューションがお役に立てるのか分析した上で、まずはパートナーポジションを獲得するべく提案活動を始めています。25年には、その中の10エリア以上で地域・コミュニティー事業を開始することを目指しています。
 10月10日に包括連携協定を結んだ国分寺市の井澤邦夫市長(左)と小西氏
10月10日に包括連携協定を結んだ国分寺市の井澤邦夫市長(左)と小西氏
―具体的にどのようなソリューションを提案するのでしょうか。
小西 実は21年以降、自治体や周辺ガス事業者と「CNのまちづくりに向けた包括連携協定」の取り組みを進めており、9月末までに29件の協定を締結しました。地域脱炭素のパートナーとして自治体の相談を受け、実際にさまざまなソリューションをスタートさせています。
その中でも多いのが、CN都市ガスや実質再生可能エネルギー100%の電気の自治体施設への供給、EV(電気自動車)やEV充電マネジメントの導入、太陽光PPA(電力販売契約)事業などです。こうした再エネやEV関係はどのエネルギー会社でも提案できますが、当社の強みはハード・ソフト合わせて44種類ものソリューションから、自治体が抱える課題やニーズに応じた支援が行えることです。
―ソフト面の支援とは?
小西 避難所のレジリエンス強化やナッジ理論を用いた省エネ教育プログラム、環境教育サービスなどがあります。例えば茨城県守谷市では、東京ガスコミュニケーションズが手掛ける「カーボンストックファニチャー」のコンセプトに基づき、県内で使用した木材のCO2吸収量を可視化した玩具を制作し、市の出生児に配布。市民の環境意識の醸成につながることも期待されています。
環境意識の醸成がなかなか難しい中、市民の行動変容につながるような環境教育への関心も高まっています。神奈川県秦野市、東京都昭島市の公立小中学校では、ナッジ理論を活用した省エネ教育プログラムを展開。これは、東京ガス都市生活研究所と住環境計画研究所が、17~20年度の環境省の実証事業で開発したプログラムで、この学びを通じて家庭のCO2排出量が5%削減されることを確認しています。こうした取り組みを通じて、政府や自治体と連携し、省エネ教育の普及や環境意識の向上を促すことで、CO2排出量削減に貢献していきたいと考えています。
 守谷市が出生児に配布する木製玩具。木材が吸収したCO2の量を印字している。
守谷市が出生児に配布する木製玩具。木材が吸収したCO2の量を印字している。
―なかなか他社にはない取り組みですね。
小西 他社には真似することができないソリューションをどれだけ持てるかが、大きな差別化の要素となることは間違いありません。ハード面では、熱の分野ではさまざまな脱炭素のノウハウがありますし、また、都市生活研究所を中心に、暮らしや食に関する研究の蓄積を長年積み上げてきました。単なる社会貢献では持続可能な事業にはなりません。こうしたノウハウやソリューションを生かし、自治体にとってもメリットがあり当社としても事業の成長につながる提案を行うことで、ビジネスパートナーとしてお役に立つことを目指します。