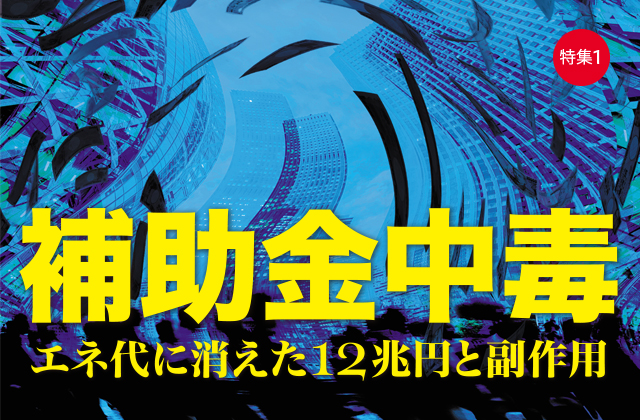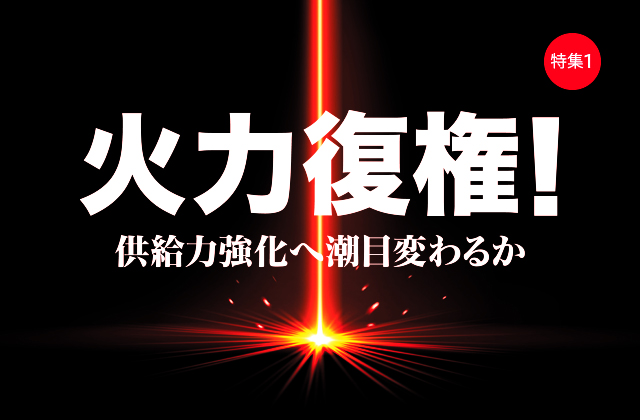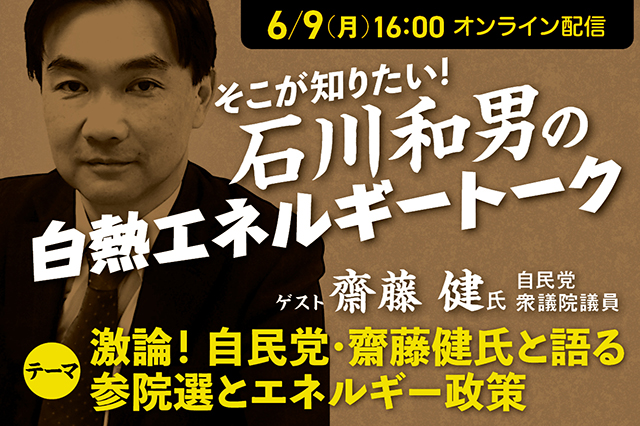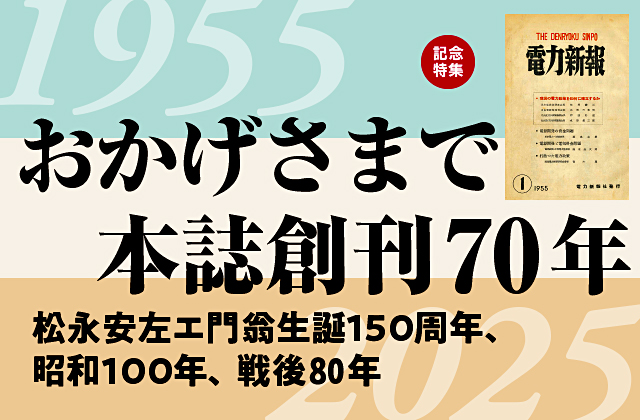脱炭素への現実的な歩みを着々と進めつつ、急拡大するDX需要に応えるべく、新たな供給モデルを提案する。
GXによる地方創生にも本腰を入れ、エネルギー事業者という殻を破りつつある。
【インタビュー:奥田久栄/JERA社長CEO兼COO】
 おくだ・ひさひで 1988年早稲田大学政治経済学部卒、中部電力入社。グループ経営戦略本部アライアンス推進室長、JERA常務執行役員、取締役副社長執行役員などを経て2023年4月から代表取締役社長CEO兼COO。
おくだ・ひさひで 1988年早稲田大学政治経済学部卒、中部電力入社。グループ経営戦略本部アライアンス推進室長、JERA常務執行役員、取締役副社長執行役員などを経て2023年4月から代表取締役社長CEO兼COO。
井関 6月下旬の会見で、地方創生・ 産業高付加価値化と一体となるGX(グリーントランスフォーメーション)開発に向けた新たな試みを発表しました。まさに産業政策とエネルギー政策は絡め合いながら考えるべき問題であり、注目しています。
奥田 例えば英国は製造業主体から、金融とデジタル主軸のモデルに脱皮し、エネルギーは原子力と再生可能エネルギー、天然ガスで賄い、電気料金が上がってもこの産業構造で世界と伍していく戦略です。われわれも相応のコストがかかる脱炭素を現実的に進めていくには、環境価値の高いエネルギーを使っても競争力が落ちないような産業・社会構造の変革が必須です。そして、GXは地域の関係者との連携なしには成し遂げられないと思います。
井関 洋上風力や水素・アンモニアの拠点で地域の産業振興を図る方針ですが、具体案は?
奥田 地方創生や工業地帯の再開発とセットで、各地域のニーズをくんだGXで地方も潤う流れを定着させたい。既に、各地には付加価値の高い製品が存在します。一から新しいモノを作るのではなく、既存のモノを適切な価値で売れる仕組みづくりが有効ではないか、という仮説に基づき、今後ショーケースを順次お見せする予定です。
例えば当社の洋上風力開発拠点である秋田県は魅力的な食の宝庫ですが、国内ではその利益が地元へ十分に還元されていません。日本で売られている日本酒が、欧州などでは数十倍で売られていることがあり、その差額は欧州側の利益となります。マーケティングやブランドストーリーの工夫によって、利益が日本の生産者に還元される仕組みを作り上げることが必要です。その点、ピュアな地産地消のクリーンエネルギーである洋上風力を使って製造し、付加価値をさらに高めれば良い循環が生じるのではないか。また、人手不足の問題には最新のデジタル技術による支援も考えています。
井関 地方創生を重視する現政権の方針にも合致しますね。 奥田 地方で開発した再エネの電気を全て東京に持ってくるという昭和のモデルのままでは、地方で持続的な雇用が生まれません。これでは地方での再エネ開発は行き詰まるでしょう。
着々と火力リプレース 袖ケ浦はアセス準備中
井関 それにしても今年は6月から連日の猛暑続きで、需給への影響が懸念されます。元々、端境期は定期点検中の火力が多いですが、足元の運用ではどんな工夫を行っていますか。
奥田 ここ数年、夏の需要ピークが早まる傾向にあり、冬もピークが早まる、あるいは長期化しています。定検の時期をなるべく前倒し夏冬フル稼働できるよう工夫していますが、それでも需給が厳しくなる場面があります。一方で再エネが大量に普及し、出力変動に応じて日常的に火力の起動停止を行っており、それに伴って故障が増え、計画外停止につながっています。古い設備はどうしても金属疲労が起きやすく、リプレースを着実に進めることがやはり重要です。JERA設立以降、リプレースを経て営業運転に至った設備は700万kW以上、計画中も含めると1000万kW以上です。多くが計画より前倒しで運開し、需給ひっ迫の際には試運転の設備も含めて供給力としてできる限り提供してきました。
 リプレースが完了した五井火力
リプレースが完了した五井火力
井関 再エネの拡大により、火力の運用は様変わりしましたね。
奥田 五井や姉崎はコンバインドサイクル発電ですが、ガスタービン単体のシンプルサイクル運転も可能で、実はこれがミソ。太陽光の出力変動に合わせる上で、スチームタービンも動かすと迅速性に関しては劣ります。供給力としての役割はもちろん、しわ取りとしてのガス火力の機能をフルに発揮できるよう、時代に合った火力発電所に変えていくことを意識しています。
井関 デジタル技術の活用にも力を入れていますね。
奥田 起動停止が頻発する中、機器の傷み度合いを正確に把握することが重要です。「予兆管理」と呼んでおり、AIで予兆を見つけ、早めに部品を交換することで計画外停止を防いでいます。こうしたDPP(デジタルパワープラント)化は、姉崎など最新鋭設備から導入し、徐々に拡大しています。
井関 6月中旬には袖ケ浦のリプレースに向け環境アセスメントの準備を開始。2032年度以降の運開を目指しています。
奥田 運転開始から50年たち計画外停止の蓋然性が高まる中、現役で稼働する2~4号機の計300万kWを260万kWの最新鋭に入れ替えました。引き続き安定供給に貢献していきます。
井関 近隣では東京ガスの袖ケ浦火力の新設も進行中ですが、今後両者が連携する可能性は?
奥田 今はまだそこまで考えていません。アセスの準備を始めたばかりで、その結果を踏まえてから、さまざまな可能性を考えることになるかと思います。