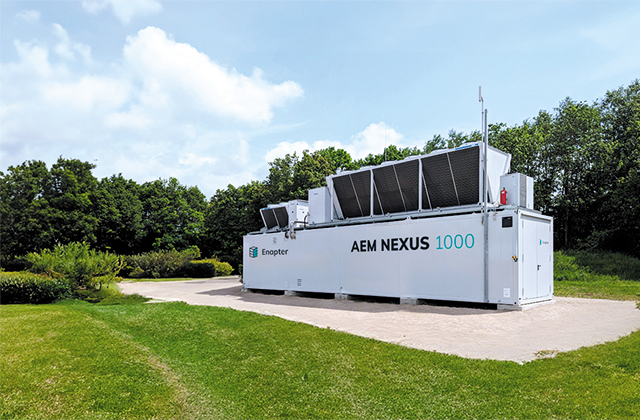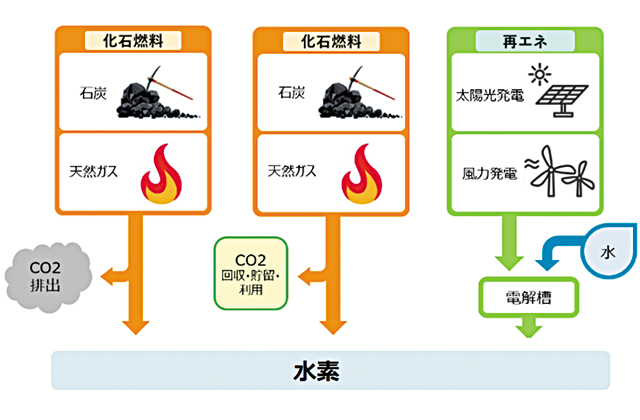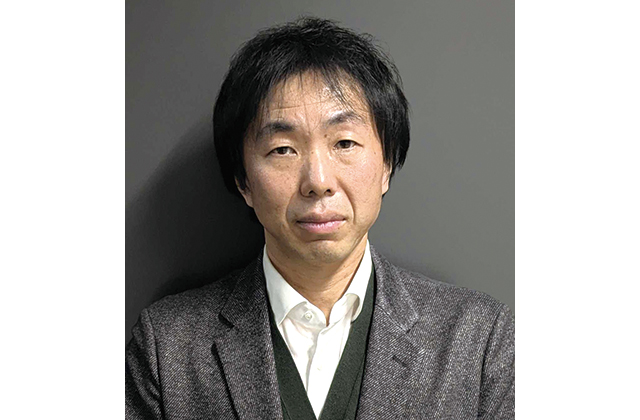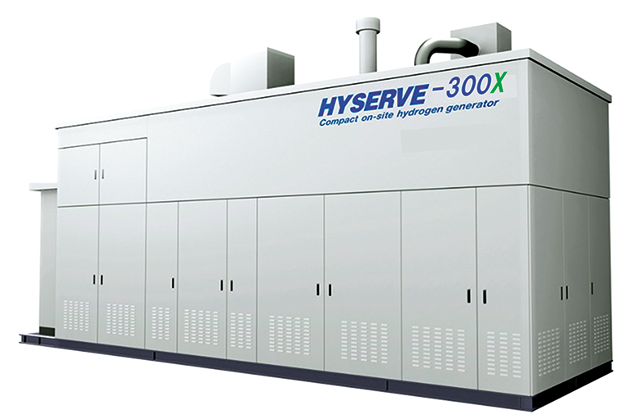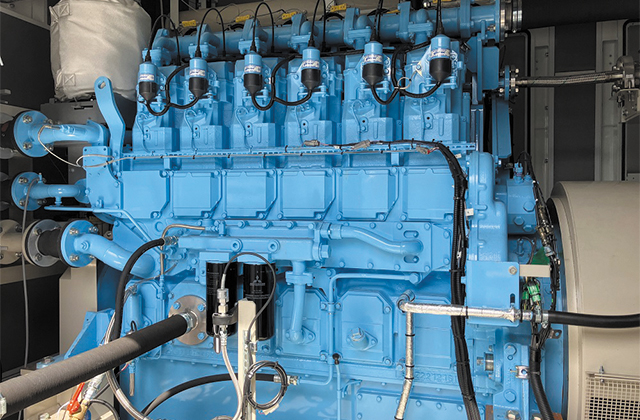木藤俊一/石油連盟会長
このたび、「エネルギーフォーラム」が、創刊70周年を迎えられましたことを心よりお喜び申し上げます。
貴誌の前身である「電力新報」が、創刊25周年を機にエネルギーフォーラムに改題されてから半世紀近くが経ちます。この間、人々の生活に欠かせない石油を含めたエネルギー全般について的確に報じられたことに敬意を表します。
平時・有事問わず安定供給 変わらぬ液体燃料の重要性
奇しくも、私ども石油連盟も、貴誌とともに歩み続け、今年で創立70周年を迎えます。この間、平時・有事を問わず、一貫して消費者の皆様にとって必要とされるエネルギーの安定供給に努めてまいりました。可搬性・貯蔵性に優れ、エネルギー密度が高い液体燃料である石油の重要性・有用性は、今後も変わることはありません。石油業界は、エネルギー供給の担い手として、液体燃料が将来の長きにわたって消費者の皆様に選ばれるよう、既存の製油所を、カーボンニュートラル燃料を製造する拠点に転換していくことなどを目指しています。貴誌には、このような石油業界の取り組みについて繰り返し報道いただき、改めて深謝しております。
今年は、2月に「GX2040ビジョン」「地球温暖化対策計画」「第7次エネルギー基本計画」といったエネルギーの重要政策が閣議決定されました。
エネルギー基本計画にも記載されている通り、無資源国である日本にとっては「S+3E」がエネルギー政策の基本です。第7次計画の策定にあたり、エネルギーのベストミックスなど様々な議論が尽くされました。石油は一次エネルギー供給の3割以上を占めていますが、2040年度においても一定のシェアを維持する見通しが示されました。一方、50年カーボンニュートラル社会の実現に向けては、再生可能エネルギーの多様化、国際的な資源獲得競争、革新的な技術開発など、エネルギー分野に影響を及ぼすさまざまな不確定要素があり、事業者側の投資予見性を高めることや、国民理解を醸成することが必要です。国民にとっての関心も一段と高まることが想定される中、これらを調査・分析し、的確に情報発信する報道機関としての「エネルギーフォーラム」の役割は、より一層強まるものと拝察いたします。
引き続き、エネルギー全般の専門誌の先駆者として、70年にわたり築き上げられた知見を基に、メディアとして公平・中立な報道と、貴誌ならではの鋭い視点がベストミックスされた誌面作成を大いに期待しています。
今後の貴誌のますますのご発展を祈念申し上げますとともに、エネルギー産業のさらなる発展に向けて今後ともご尽力賜りますようお願い申し上げます。