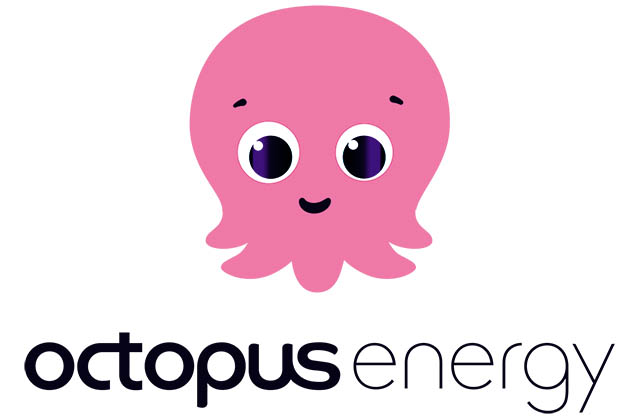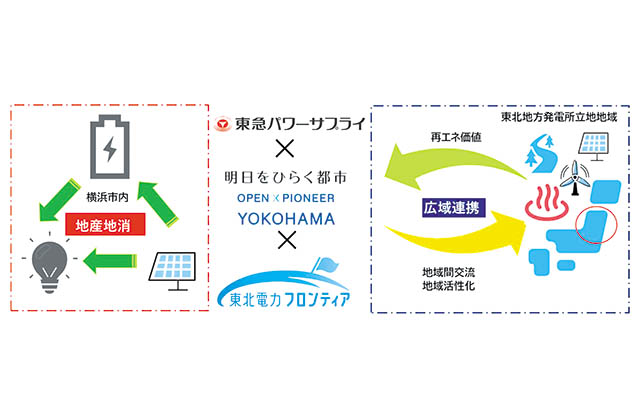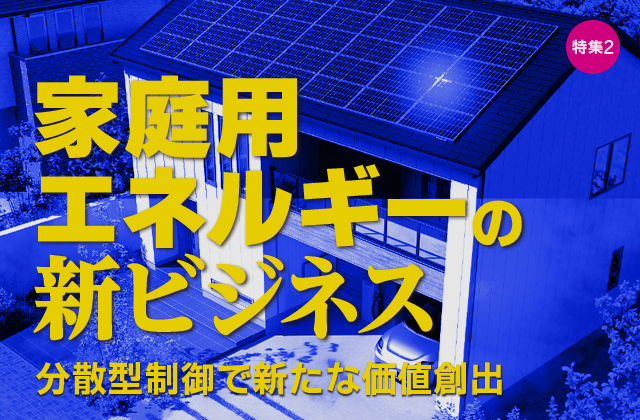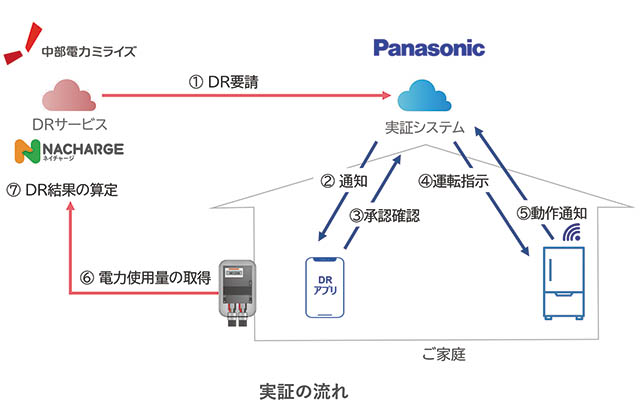自治体の人口減少対策や災害対応などを手助けするガス事業者。主戦場で果たす役割について3社のトップが語り合った。
【出席者】
緑川昭夫/大多喜ガス社長
澤田龍明/釜石ガス社長
小出 薫/越後天然ガス社長
―まずは、各社の概況から聞かせください。
緑川 持ち株会社の傘下にガス供給事業を担う当社、ガスを採掘する会社、採掘時に出るヨウ素を製造する会社があり、この3社で各事業を分担しています。
当社のお客さま数は約17万件で、供給区域は大きく外房の茂原、内房の市原、千葉、八千代の4市です。千葉県は天然ガスの産出地で、当社が供給する家庭用ガスの大部分は国産天然ガスです。そのため家庭用のお客さま向け料金メニューでは原料費調整制度を導入しておらず、固定価格です。一方、京葉工業地帯のお客さまには、東京ガスや東京電力エナジーパートナーからガスを卸してもらい導管で供給しています。
小出 当社は、新潟市秋葉区、江南区の一部、五泉市の約3万
4000件に都市ガスを供給しています。新潟県も、国内の約7割の天然ガスが採れるので、石油資源開発からの卸供給を受け、また海外からのLNG由来の都市ガスも活用しながら供給しており、件数では家庭用が圧倒的に多く、販売量は家庭用と工業用が同程度です。
澤田 岩手県釜石市で事業をしており、都市ガスのお客さまは7000件程度です。1957年に、日本製鉄の粗製コークス炉へのガスの供給を始め、88年に高炉が休止したタイミングでブタン原料の6Cガス供給を開始しました。私は、そのタイミングで入社しました。
2007年にはLPガス原料のPA―13Aガスを供給しています。11年の東日本大震災ではプラントが全壊しましたが、他社の協力もあり約1カ月半で復旧させました。導管もほぼ全滅でしたが、被災していない地域にはどうにか供給し、被災地には3、4年がかりで導管を入れ替えて供給再開しました。14年には岩手県初のLNGサテライト設備を竣工し、今は13Aガスの供給です。
事業環境変化に向き合う 市民サービスの充実へ
―人口減少や地域経済などによって、地方都市ガス会社の事業環境は大きく変化するかと思います。
澤田 釜石市は企業城下町ですが、63年の9万2000人をピークに、東日本大震災が起きた11年には約4万人、それから13年経ち、さらに1万人減りました。昨年11月には3万人を下回り、メーターの取り付け数も震災前は1万台でしたが、現在は8200台です。従業員も震災前の50人から34人まで減少しました。保安やインフラの維持管理を含めると、どうしても現状の人員が必要と思います。
小出 新潟県でも全体的に人口は減っています。ベッドタウンの新潟市秋葉区と江南区はあまり減っていませんが、郊外の五泉市は減少が激しいです。
緑川 東京のベッドタウンである八千代市は人口が増加していますが、外房のように、東京まで通勤が困難な地区は人口減少が激しいです。当社の本社がある茂原市周辺の供給エリアにも消滅可能性自治体が三つあり、人口が相当数減っています。
一方、京葉工業地帯には相当量のガスをご使用いただいている発電用途のお客さまがおり、販売量の割合では工業用が約7割に上ります。発電用途は、電力の価格自体、ボラティリティが非常に高く、電力価格や市場価格が高いとガスの販売量が減るという独特の動きが特徴です。
―地域に根差したエネルギー事業者として行政からの期待も高く、最近では社会インフラを効率化するスマートコミュニティーの構築事業に協力しています。行政とはどのような関係を築いていますか。
澤田 東日本大震災後、地元の自治体でスマートコミュニティーの確立の動きが生まれました。さまざまな施設を一定のエリアに集約し、住民サービスを効率化するものです。その際、地域の事業者が中核に参加することが条件で、参画しました。スマートコミュニティーでは、復興住宅での熱、電気、ガスの一括管理をはじめ、太陽光発電(PV)や太陽熱給湯を設置した住宅を3棟つくりました。この中で、エネルギーマネジメントを管理しています。復興への取り組みには、周囲からの期待の高さを感じています。
またこのほど、環境省の第5回脱炭素先行地域に釜石市での取り組みが選定されました。当社は、計画書の作成や地元企業によるSPC(特別目的会社)の設立で参画します。これまで計3回、申請しましたが、今回選定され、ようやくスタートラインに立てました。
 釜石ではスマート復興公営住宅が作られた
釜石ではスマート復興公営住宅が作られた