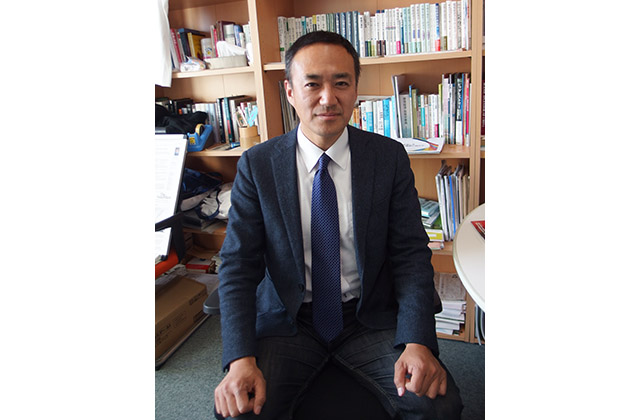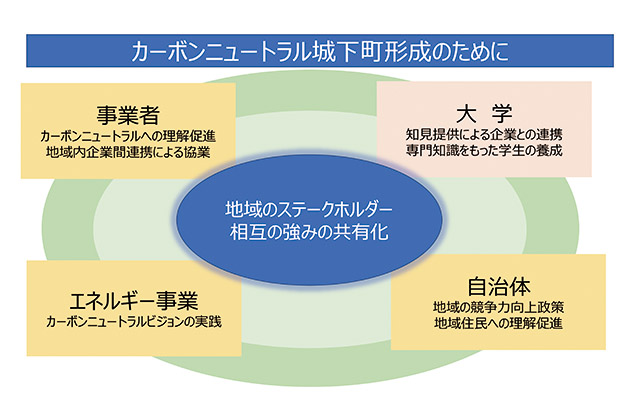<出席者>電力・ガス・石油・マスコミ/4名
ロシア軍のウクライナ侵攻はエネルギー安定供給の重要性を再認識させた。
エネルギー環境政策での中心議題だった気候変動問題は、すっかり影をひそめてしまった。
――ロシア軍のウクライナ侵攻で、悲惨な状況の映像が連日、テレビで流れている。一方、欧米と足並みをそろえて日本も経済制裁を行ったことで、国内のエネルギー市場に大きな影響が出そうだ。
電力 電力・石油・ガスの値段が上がることは避けられない。政府はさまざまな対策を考えるだろうけれど、国際市場で高騰することには打つ手がない。新聞の首相の動向欄を見ると、毎日のように資源エネルギー庁幹部が官邸を訪れている。7月の参院選に向けて、エネルギー価格を抑えることが大きな政治課題になっている。
――新聞もエネルギーを巡る問題を大きく取り上げている。
ガス 各紙取り上げているけれど、誰のコメントを載せるか、それと、自社の編集・論説委員がどこまで踏み込んだ記事を書けるかで、差が出始めている。やはり、ダントツは日経。「ウクライナ危機を聞く」のコーナーで、『石油の世紀』で有名な石油アナリストのダニエル・ヤーギンのインタビューを掲載していた。
――ヤーギンは石油アナリストでは大御所的な存在。「米シェール産業は重要な意味を持つ」など、コメントにも説得力があった。
ガス 自社の記事にしても、ヤーギンに話を聞いた米国ヒューストン駐在の花房良祐さんをはじめ、記者はよく取材している。編集・論説クラスでも松尾博文さん、西條都夫さんらが中身の濃い論説を書いている。改めてエネルギーについて日経の執筆者の層の厚さを認識した。一時、再生可能エネルギー推進に大きく偏重して、違和感を覚えていたけれど、ようやく元に戻ったなと思った。
――他の新聞はどうかな。
石油 よく分からないのが朝日。紙面では、被災した市民の写真を載せて、ウクライナの惨状について紙面を割いている。けれどウェブ版では、この戦争を分析して、海外の識者のコメントを載せたり、かなり突っ込んだ記事を載せたりしている。なぜ、これを本紙に載せないのか不思議だ。
マスコミ 読者が求めていることを考えているんだろう。朝日の読者層からすると、ウクライナ侵攻はまず人道上の問題になる
石油 ただ、本紙ではないけど、朝日新聞出版の『AERA』が、ロシアの肩を持つような記事を載せたことには驚いた。
旧ソ連圏に詳しい教授と国際紛争が専門の教授二人が対談をして、「気になるのは、私たちは西側視点のニュースだけで『悪いロシア』のイメージを作っていること」「『悪玉プーチン』だけに偏ると見えてこないことがある」と、右翼が聞いたら激怒しそうなことを語っていた。
マスコミ 何を考えているのかな、この新聞社は。
サハリンから購入継続⁉ 広ガスに消費者が反発も
――サハリン1、サハリン2からシェルやエクソンが撤退した。欧米から圧力がかかった場合、日本の対応も問われそうだ。
ガス サハリン1・2から日本が撤退することは、まずないと思う。ただ、今回の戦争で痛感したのは、ロシアと取引をしながら消費者を相手にしている企業が、非常に難しい立場に立たされること。例えばユニクロは、侵攻後、いったんロシアでの商売継続を決めながら、批判が殺到して方針を転換した。
エネルギー企業は、ロシア産の石油や天然ガスを購入している。中でも広島ガスは、買っているLNGの約半分がサハリン2のものだ。サハリンから日本への供給は継続されるだろうが、広ガスは消費者から反発を受けるかもしれない。経済産業省に、そういう指摘をする人がいる。
マスコミ 商社関係者が「サハリンから撤退しても、中国を利するだけ」と政治家や役人に吹き込んでいるらしい。ロシア産石油・ガスは日本に欠かせないけど、ウクライナ情勢の行方によっては、撤退もあり得るんじゃないか。
――エネルギー政策の基本はS(安全)+3E(安定供給、経済性、環境性)とされている。今までは環境性、地球温暖化問題が議論の中心だったけれど、この戦争で安定供給がかつてないほどクローズアップされることになった。
石油 「ウクライナの次は台湾」という人たちがいる。経済性も環境性も、安定供給がまず維持されてからの話だ。ウクライナの人たちには申し訳ないが、今回、それを日本人が理解し始めたことはよかったと思う。
ガス だけど、温暖化問題がなくなったわけではない。この戦争で最も影響を受けたのは、ロシアから天然ガスを買っていたEU諸国だ。中でもドイツは、今年中に原発を全廃すると言っている。温暖化対策をリードしてきた西欧の国が、2030年に向けてどうエネルギーミックスを考え直すのか注目している。
原発の再評価はいつに 参院選まで音無しか
――電力業界としては、この機会に原子力の役割が再認識されることを期待していると思う。
電力 産経論説委員の井伊重之さんがコラムで「原発の緊急稼働を検討せよ」と書いてくれた。全くその通りだと思っている。だけど、まだ業界としてそれを言い出せる状況にない。
ガス エネルギー基本計画策定のときに、原発の役割拡大で盛んに活動していた自民党の議員が今回はおとなしい。自民党にとって最大の課題は7月の参議院選。これに勝てば、次の衆議院選まで「黄金の3年」がくる。だから7月までは、音無しの構えを決め込んでいる。だけど選挙が終われば、再稼働や運転期間延長に向けて一気に動き出すだろう。
――「動かざること山のごとし、はやきこと風のごとし」。武田信玄の戦術みたいだな。