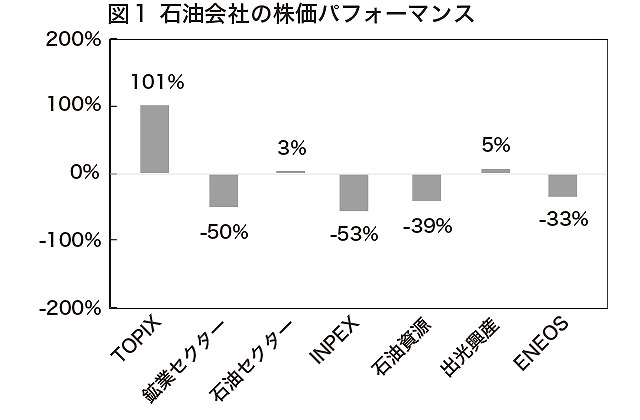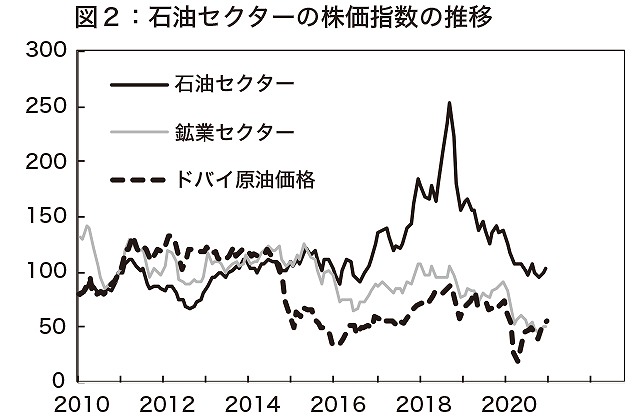あきもと・まさとし 1975年千葉県富里市生まれ。法政大学法学部卒。12年衆院選で初当選。内閣では国土交通大臣政務官を務めたほか、党の再生可能エネルギー普及拡大議員連盟事務局長などを務める。当選3回。
あきもと・まさとし 1975年千葉県富里市生まれ。法政大学法学部卒。12年衆院選で初当選。内閣では国土交通大臣政務官を務めたほか、党の再生可能エネルギー普及拡大議員連盟事務局長などを務める。当選3回。
直接民主制を学ぶ過程で、原子力への疑問と再エネのポテンシャルの高さに気が付いた。
自民党内屈指の再エネ推進派議員が、独自の電力システム改革案を披露した。
自民党の再生可能エネルギー普及拡大議員連盟の事務局長を務め、党内屈指の再エネ推進論者で知られる秋本氏。中学、高校から新聞や報道番組をよく目にしていたため、社会問題や政治に強い関心があった。「法律を変える立場になり、世の中を変えたいと思う人たちの気持ちを受け止めたい」。進路を考えた際、こうした思いから法学部を選んだ。
大学卒業後は、大学院で直接民主主義を専攻。研究テーマは産業廃棄物処理場や核施設などの、いわゆる迷惑施設建設の是非を問う住民投票について。「住民投票は原子力関係の話が多く、高知県東洋町で起きた高レベル放射性廃棄物の最終処分場の建設問題もその一つだった。当時から私は自民党員であったが、原子力政策についての勉強を進めたことで原子力発電の問題性に気が付いた」
独自に研究を進めた結果、「核燃料サイクルは破綻している」との結論に至った。
「青森県六ヶ所村の核燃料再処理工場も稼働しておらず、使用済み核燃料の置き場も定まっていない。一時保管場所として使われている原発サイト内の使用済み核燃料プールを拡張させてしのごうとする動きもあるが、いずれ限界を迎える。さらに高レベル放射性廃棄物の処分場所も決まっていないなど、核燃料サイクルは破綻しているにもかかわらず、原発推進のために地域振興を名目に税金を費やすのは健全ではない。震災前から再エネの方がはるかに将来性はあると思っていた」
そうした中、大学の講義に河野太郎氏が講師としてやってきた。その講義では冒頭に「核燃料サイクルを説明できる学生はいるか」と、質問が投げかけられたという。そこで秋本氏が挙手して質問に答えたところ、「君は何者だ」と河野氏の目に止まった。
「講義後に河野さんに呼ばれて『原発を推進する自民党でも核燃料サイクルをきちんと説明できる人はそういない。一緒に働かないか』とのオファーも受けた。もともと政治家という仕事に興味があったが、本格的に志そうと思った一つのきっかけだ」と当時を振り返る。
弱冠27歳で地元市議に当選し2期務めた。その後は党の衆院選の候補者となり、地元議員との懇親の場で脱原発と再エネのポテンシャルの高さを語ったところ、「そんな考え方なら共産党に行けばいい」と言われたこともあったそうだ。
2012年には衆議院議員選挙で千葉9区から出馬し初当選を飾り、舞台は国政へ。内閣では国土交通大臣政務官を経験。党では国会対策副委員長などを務めている。
再エネの大量導入が重要 送配電会社の「東西2社」案も
「日本を将来の担う主力電源は何か」と聞くと、「太陽光発電と風力発電だ」と語っている。「環境省が公表している資料でも、送電線に接続可能な地域の再エネ容量は国内の電力総需要の2倍以上ものポテンシャルを秘めている。評価が低いのはおかしな話だ」と述べ、「これからは間違いなく再エネの時代。進めなければ技術的にも諸外国に置いていかれる」と、導入拡大の重要性を訴えた。
政府も50年までにカーボンニュートラルの実現を目指す上で、再エネの大量導入が重要だと位置付けている。その中では系統に水素製造装置や蓄電池を導入することで、系統安定化や余剰電力を活用しようと計画しているが、このプランに対しても意見がある。
「再エネ主力電源化によって電力コストが上がるとの批判があるが、現段階で蓄電池や水素を接続すればコストが上がるのは当然の話。今すべきなのは系統に再エネを大量に導入すること。系統が不安定化するという懸念には、系統の高度化や利用ルールの整備で対応できる。蓄電池や水素の調査・研究は必要だが、商業利用はまだまだ先の議論のはずだ」
現在の送配電会社の在り方も、再エネの大量導入を阻害しているのではと疑問を持っている。「この狭い国土に10社も送配電会社があるのは非常に効率が悪い。例えば50 Hz帯、60 Hz帯の東西2社ぐらいに再編すれば、北海道のような再エネの高いポテンシャルを持つ地域の電気を、東京などの大需要地に送ろうとするインセンティブが働く。グリッド改革は再エネ導入拡大にもつながる」と説く。
また政府が計上した2兆円の環境投資基金についても、「10年先に開発できるかもしれない技術に投資するよりも、ラストワンマイルを埋められれば実用化できる技術にも投資できるような仕組みを作っていくべきだ」と指摘。「1年半かかるものを1年に短縮するための投資も重要で、現在の方針は非連続のイノベーションに重点を置き過ぎ。これも優先順位が違うのではないか」と主張した。
座右の銘は「先憂後楽」。「数十年後の日本国民から感謝してもらえるよう、責任ある判断をしたい」と語る。これからも確固たる信念を持ち、エネルギー政策と向き合う構えだ。