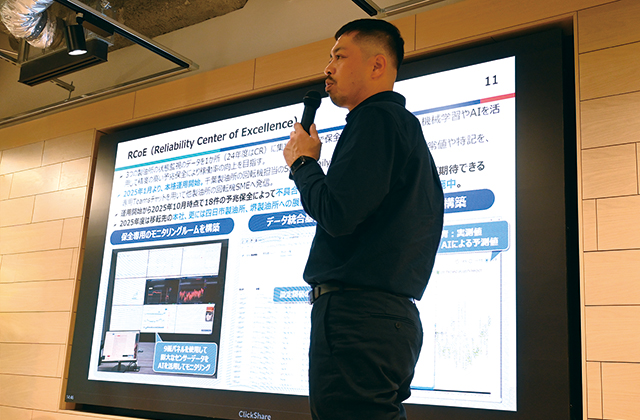飯倉 穣/エコノミスト
1、あれから15年~政府の措置は適切だったのか
東日本大震災・福島第一原発事故から15年である。復興は、物理的なインフラ整備を終了し、産業・生業も震災前水準に戻った。今後の課題は、福島浜通りの廃炉立地5町の経済社会再構築、福島原発の事故処理の行く末となった。
新年に入り東京電力の運営で、柏崎刈羽原子力発電所6号機の再稼働(2026年1月21日)に続き、原子力損害賠償・廃炉等支援機構・東京電力ホールデイングス株式会社の第五次総合特別事業計画の認定があった(1月26日)。
「東電再建計画 他社提携が柱 実現性は不透明」(朝日1月27日)。「東電再建 外部から資本 月内にも募集「非公開化 排除せず」」「東電再建重い6兆円投資 原発・再エネ、成長の柱に 収支改善計画は薄氷」(日経同)と報道もあった。
震災・事故ショックによる当時の政治指導者の狼狽・動揺が脳裏に浮かぶ。政治的思惑は、事故を自然災害とせず、人災とした。そして全日本の使用中原発停止と無理なエネルギー政策の転換で、事後のエネ供給と経済の不安定を招来した
東電は、2011年原賠機構設立・国の経営権取得で国有東電となった。東電経営は国主導、会社組織は総合特別事業計画(以下総特)の執行機関となった。今回の総特は、東電の福島責任貫徹、公的管理継続を再確認し、賠償・廃炉資金捻出で資金獲得のアライアンスを提示した。
現在震災後の政府措置がもたらしたエネルギー供給体制(電力システム改革等)の行き詰まり、再エネ主体のエネルギー供給確保政策の混乱、原子力エネルギー利用の迷走と試行錯誤が継続している。この視点も踏まえ浜通り復興の現状と国有東電の今後の運営(総特)を考える。
2、復興状況の再確認~廃炉関連5町の苦悩
東日本大震災(マグニチュード9.0)の被害は、死者19、782名、行方不明2、550名、住家被害122千棟(全壊)、鉄道・道路等のインフラ被害、避難者数47万人、災害救助法適用10都県241市町村、そして福島第一原発事故(避難指示区域1、150㎢)だった。
復興現状を見ると、避難者数減(現在2.7万人、内福島2.4万人)。復興道路整備(570km)・公営災害住宅建設(2.9万戸)、高台移転宅地造成(1.8万戸)は既に終了し(20~21年)、産業面でも3県(岩手・宮城・福島)の製造品出荷額は震災前を超えた(20年)。営農再開農地面積(25年震災前比96%)もほぼ回復し、更に避難指示区域面積(309㎢)も震災時比26%に縮小した(復興庁資料)。
福島県浜通り(相双地区12市町村)はどうか。人口は15.5万人(25年、震災前比78%)に落ちたが、生産額は、震災前9992億円(10年)から震災で4290億円(11年)に低下後、8440億円(21年)に回復している。これは相馬、南相馬、広野の火力発電再稼働等が大きい。
廃炉関連5町(楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町)の人口(住民基本台帳)は、25年4.7万人(10年6.4万人)だが、実際の居住者は、1万人程度にとどまる。生産額は、廃炉作業等があるものの、現在2000億円程度(10年4670億円)と半減している。福島感情を尊重した福島原発の廃炉決定(2014年福島第一5・6号機、2019年福島第二1~4号機)で、原発再稼働・S&Bによる経済復興を見込めないことが大きい。同時に東電、即ち日本の電力供給基盤を弱体化した。
代わって政府・福島県は、福島イノベーションコースト構想(17年策定)が描く6分野(廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙)の開発・起業支援や福島国際研究教育機構(F-REI)等の施設作りで産業集積を目論んでいる。現在は「浪江 ロボット・創薬研究拠点に 国主導「エフレイ」計画 住民の関心高まらず」(朝日25年11月11日)の段階にある。国・県という官の努力で、地元に戻る雇用がどの程度か定かでない。また「再エネ推進 福島のいま、理想 原発事故受け先駆けの地、現実 メガソーラー住民困惑も」(同12月19日)である。国の落下傘プロジェクトや再エネ推進で、国・県・地域の意向がかみ合っているか懸念もある。
15年経た今日、現実直視も必要である。この地区の今後の展開を図るには、福島原発立地町の長期的な経済復興に、「原子力発電が地場産業だった」ことを再確認することを勧めたい。メガソーラー等の状況も踏まえれば、国・地方は選択肢として原子力を再考すべきである。
3、震災の余波は~エネルギー供給体制は弱体化
震災後、政治・マスコミ的思惑が錯綜した。脱化石エネ、原子力開発忌避・撤退、再エネ活用期待の大風呂敷の政策主導が罷り通った。吟味不十分・勢いだけの再生可能エネルギーの固定価格買取制度が許容された。そして年3兆円を超える国民負担となった。
メガソーラーは、救国のエネルギーとされたが、狭い国土を忘却し、国土利用・土地利用計画構想がなかった。再エネ推進者・担当官庁の視野狭窄である。自然エネの特性(単位面積当たりの発電量)無視だった。現在の発電量(1兆kwh)の3割程度を太陽光発電で賄うには、6,600平方キロ(パネル3,300平方キロ×2倍程度)の土地面積が必要と試算できる。立地は、国土をにらんで確保する必要がある。新全総(1969年)の手法を思い出す。因みに同量確保に原子力発電所の必要面積は、30~60平方キロ程度だが、原子力立地も容易でない。
現在、経済・社会的に太陽エネの行き詰まりに直面している。立地制約の顕在化である。立地地域の雇用は増えず、土地乱開発と将来の廃棄物懸念で、地域の紛争が絶えない。さらに地球環境保全は地域環境保全を軽視した。適切な事業者選択の視点も欠如している。そして再エネ価格の妥当性と国民負担の限界が露わになった。15年経て自由競争の再エネ需給市場は、成立しなかった。また自然環境に左右される発電形態の対応で火力を軽視したことも反省点である。
この15年間のエネルギー政策は、海外情勢に脆弱なエネルギー需給構造を形成し、貿易収支や物価面で経済の安定・成長どころか、不安定を招く事態に至っている。また国内の電力業等の産業体制も脆弱になった。電源投資が進まず将来の供給面の不安だけでなく、電力価格の高止まりを招いている。いずれにしても国土利用・産業政策的に、原子力・再エネの再構築が必要である。福島県の認識はなお従前の通りだろうか。国・福島県は、改めて明確なビジョンを提示すべきであろう。経営方向が定まらない東京電力の姿が、エネルギー供給混迷の象徴といえる。