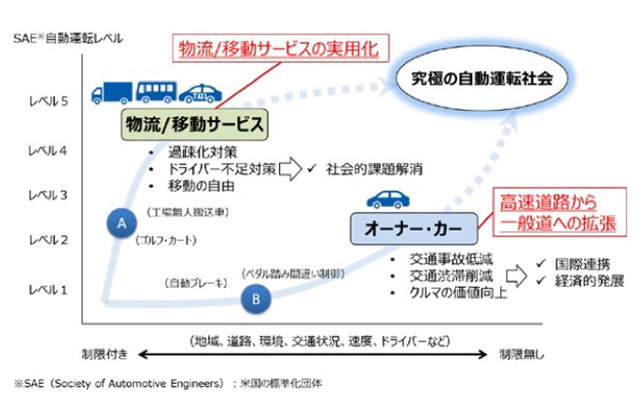【事業者探訪】山鹿都市ガス
温泉街として知られる熊本県山鹿市で、都市ガス小売り事業を営むのが山鹿都市ガスだ。
人口減少が深刻化する中、助け合いの精神を大事に地域に根差した事業を展開している。
熊本県北部に位置する山鹿市は、九州を代表する名湯「山鹿温泉」や1910年に建てられた芝居小屋「八千代座」などで有名な観光地。毎年8月に催される「山鹿灯籠まつり」には、多くの観光客が訪れる。
同市は明治時代に、県北部を流れる菊池川の水上交通の要、物産の集散地として発展した。
肥後・熊本(熊本市)と豊前・小倉(北九州市)をつなぐ「豊前街道」の中間地点に位置し、九州屈指の宿場町でもあった。
同市で都市ガス事業が始まったのは1970年。それまでLPガスが主流だったが、都市ガスの普及が急務となった。この動きを推進したのは、旧山鹿市の青年会議所の有志で、同所が出資し、山鹿ガス(現・山鹿都市ガス)を設立した。

同社は今年、設立から54年を迎えた。1市4町が合併する前の旧山鹿市を供給エリアとし、一般住宅、飲食店、医療施設、宿泊施設などの家庭・商業用に都市ガスを販売している。民間企業の工場がないため、工業用などの大口契約はない。また、同市にはLPガス事業者も多く、供給エリア内の同社の普及率は50%だ。
ガス供給で観光業下支え TSMCの効果に期待
市中心部で湧き出る温泉の温度は、30~40℃前後と比較的低いという特性がある。このため、旅館などの宿泊施設では源泉をボイラーなどで昇温する必要があり、この加温作業に用いられているのが、同社が供給するガスだ。地域の主力産業である観光業には欠かせないエネルギーインフラを、長年陰から支えてきた。
ガスの原料にはLNG(液化天然ガス)ではなく、プロパンガスと空気を混合して供給するPA13A方式を採用している。山鹿市古賀にある本社に隣接するガス製造基地には、毎時1万6800㎥のガス発生設備や335㎥の貯蔵能力を持つ中圧ガスホルダーなどを備える。
事業継続の上で一番の課題は、山鹿市の人口減少による供給先の減少だ。市町合併が行われた2005年1月時点の人口は約6万人だったが、現在は約4万8000人と、徐々に減少し続けている。
現在のメーター取り付け数は約3000件だが、実際に稼働しているのは2300件ほどにとどまる。コロナ禍の影響もあったとはいえ、23年度には例年の年間ガス販売量80万㎥を下回ってしまった。
事業の存続が危ぶまれる中、転機をもたらすことが期待されるのが、今年2月に開所した熊本県菊陽町の台湾積体電路製造(TSMC)の熊本第一工場だ。半導体工場の城下町となった菊陽町では、TSMCに関連する工業団地の建設が進み、同社社員や建設作業員の住宅地の建設も進む。それは、第一工場から北西約30Km圏内にある山鹿市でも同様だ。
岡本曉宗社長は「工業団地の進出に伴い、山鹿市でも住宅地の建設が始まる見通しだと聞いている。最近では、市内での工場新設を視野に入れる半導体関連の企業も出てきている」と、半導体工場立地の効果を話す。

第一工場から南西に進むと熊本市がある。同市は政令指定都市の中でも渋滞箇所数ワースト1位の「渋滞都市」。通勤の混雑を避ける点からも、山鹿市が住宅用地として注目されているという。
2月に第二工場の建設が決まって以降は、県外から訪れた建設作業員が宿泊施設を求めて山鹿市にやってくることも。市内では、作業員用の仮設住宅の建設があちらこちらで始まっている。半導体関連の工場建設に伴い、「家庭用の供給先増加につながれば」と期待を込める。