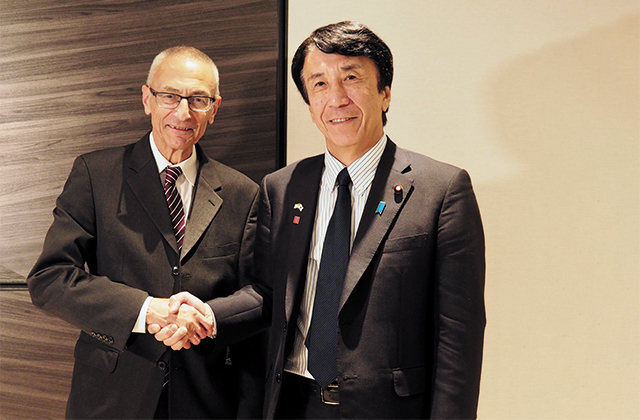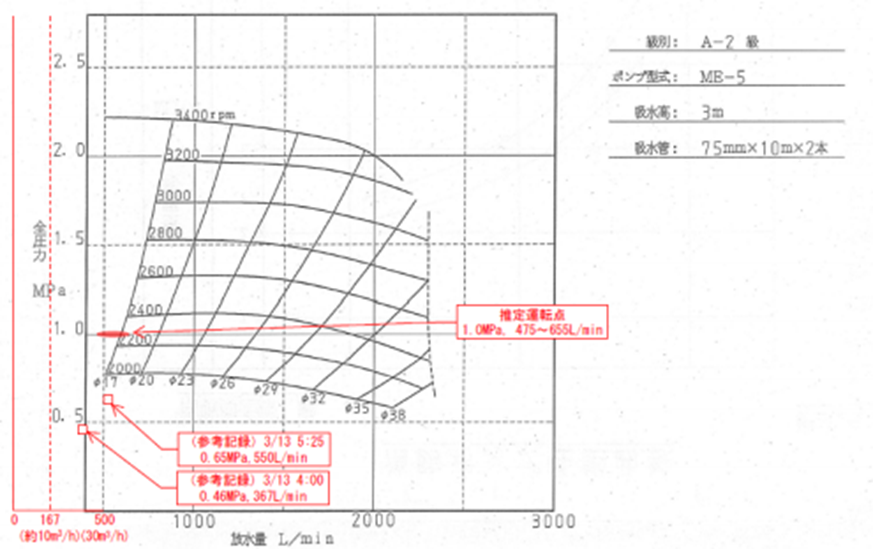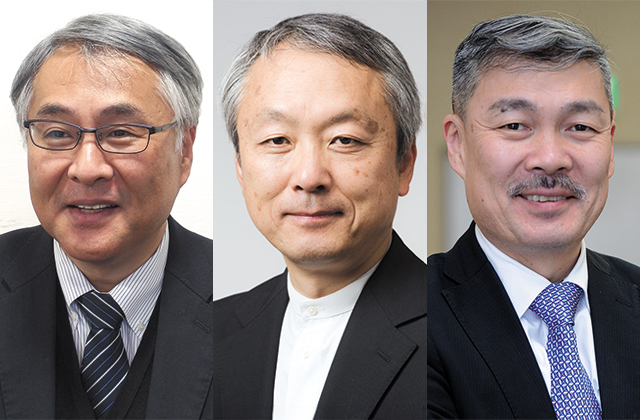柏崎刈羽原発の再稼働を巡り、地元・新潟県の動向に大きな注目が集まっている。
地元の焦り、県議会と花角英世知事の慎重姿勢―。早期再稼働の可能性を探る。
「今年は島根2号機、女川2号機、柏崎刈羽7号機が再稼働する見込み」
昨年来、電力業界ではこんなフレーズが飛び交っている。本誌でも再稼働問題を取り上げる際、枕詞のようにそう書いてきた。だが、柏崎刈羽が島根、女川に続けるかは不透明だ。
柏崎刈羽原発については昨年末、原子力規制委員会が東京電力に対して事実上の運転禁止命令を解除。地元の柏崎市と刈羽村は今年3月、早期再稼働を求める請願を採択した。4月15日には7号機の原子炉への燃料装填を開始し、夏前には再稼働に向けた準備が完了する見込だ。
残るハードルは新潟県の同意だが、最大の難関として立ちはだかる。今後は新潟県技術委員会による報告書の提出などを経て議論が加速するとみられるが、「県民の信を問う」とする花角英世知事の再稼働「容認」の判断は一体いつになるのか。

県の要望と国の回答 島根、女川の直後に
鍵を握るのは、避難計画の実効性確保を巡る国の関与だ。新潟県と柏崎市、刈羽村は昨年7月、国道8号柏崎バイパスの早期全線供用や北陸自動車道への進入路を増やすためのスマートインターの導入などを政府に要望した。その後、運転禁止命令の解除が現実味を帯びた12月、新潟県と柏崎刈羽原発から5~30㎞圏内(UPZ)の市町村が避難道路の整備などを政府に要望した。
一見、同じように見える要望だが、実態は異なる。県と立地自治体の要望は、約3年をかけて両者が綿密なすり合わせを行い作成した。国からの回答について柏崎市の櫻井雅浩市長は「満額に近い形で得られると確信している」と語る。
一方、県とUPZ圏内の自治体による要望は、別添資料に「新潟県との未調整部分を含む」と記されるなどスケジュール優先で作られた感は否めず、原子力防災とは無関係と思われる要望も含まれている。例えば、新潟県では新幹線が通らない新潟・上越間の高速鉄道計画が存在するが、震災直後の鉄道移動は考えにくい。今回、高速鉄道のような原子力防災との関係性が薄い事業整備を要望するのは筋違いだ。花角知事は4月3日の記者会見で「もう少し精緻なというか、具体的な要望にしていかなければいけない」と述べ、要望書をできるだけ早く再提出する方針を示した。花角知事の「精緻」という言葉は、要望内容の修正を念頭に置いたものとみられる。
花角知事の再稼働容認の最短タイミングとして挙げられるのが、「要望に対して国から十分な回答を得られた時」だ。「国と交渉を行い、避難道路整備の見通しが立った」として県内市町村の首長らに伺いを立て、9月定例会に地元経済界が請願を提出。自民党などの賛成多数での可決をもって、県民の信を得たと判断する―。これが最もスムーズな決着か。8月の島根2号機、9月の女川2号機の再稼働とタイミングも重なる。
しかし、最短ルートでの決着を阻みかねないのが、県議会で単独過半数を握る自民党である。
「(柏崎刈羽原発が)動く気配は全くない。花角知事の任期満了の2026年6月まで判断が先送りされる可能性すらある」
こう打ち明けるのは若手県議だ。党内には再稼働の条件として「避難道路の完成」を求めるベテラン議員すら存在する。こうした姿勢は「条件闘争」の側面があると分析する県政関係者もいるが、国からの回答を得て慎重派が首を縦に振るかは微妙なところだ。