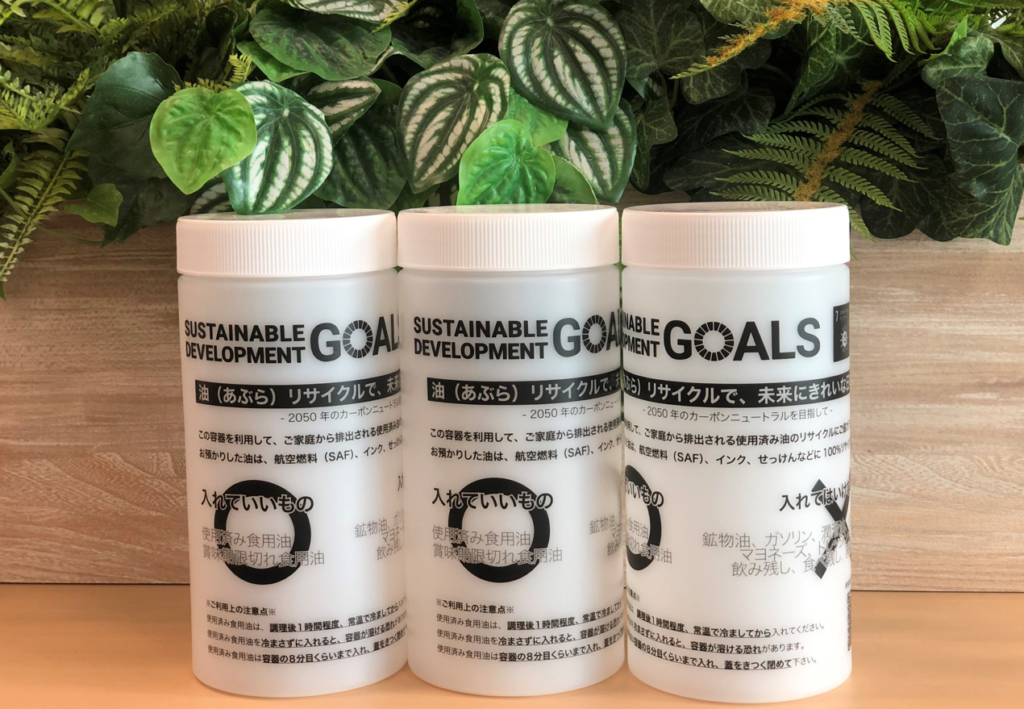石破政権で初となるGX(グリーントランスフォーメーション)実行会議が10月31日に開かれ、「GX2040ビジョン」の策定に向けて議論を深めた。石破茂首相は、地熱や中小水力の開発など、GX加速への当座の取り組みを具体的施策としてまとめ、経済対策に盛り込むよう求めた。また、GX2040ビジョン、エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画の3つの案を年内にまとめること、来年の通常国会に向け、カーボンプライシングの詳細設計を定める改正GX推進法案の検討を進めることを、改めて指示した。若干の「石破カラー」を出しつつも、基本路線は岸田政権下での議論を踏襲する方針だ。

石破首相は会議のあいさつで、「地域の森林資源の活用などにも効果的な脱炭素先行地域の拡大や、地熱、中小水力の開発は、地域経済にGXの恩恵をもたらす」などと強調した。
当日、武藤容治GX実行推進担当相が提出した資料でも、GX加速に向けた当座の取り組みのイメージで、地域経済の成長に資するものとして、①地域脱炭素の推進、②再エネ拡大、③省エネや国内投資促進――を挙げた。特に再エネではまず「地域が高いポテンシャルを持つ地熱や中小水力の開発加速」を、次いで「太陽電池や洋上風力などの研究開発・社会実装加速」を掲げた。
このほか、生活環境の向上につながる取り組みとしては、断熱窓や給湯機などの住宅、電動車、建築物関係を挙げた。
地熱好きの石破首相 今後の政策議論でどこまで強調?
石破首相は、再エネでは地熱や中小水力にこだわりがあるようだ。例えば10月4日の所信表明演説では、再エネ政策の文脈で「わが国が高い潜在力を持つ地熱」と強調している。
また、ある有識者は、今年初めのとある研究会で、地球温暖化問題や原子力の重要性などを講演した際、個人的に参加していた当時無役の石破氏から「地熱と中小水力で賄えないのか」といった質問を受けた。「これを聞いて、石破さんは個人的に地熱などが好きなのだと感じた。ただ、原子力をやめて再エネへ、という強い思いまでは感じなかった」と振り返る。
なお、エネ基を議論する基本政策分科会でも、10月23日の会合の事務局資料で再エネに関する世界の動向として、次世代地熱に関する各国やIEA(国際エネルギー機関)の動きをまず取り上げていた。このあたりがエネ基の取りまとめでどの程度反映されるのか、気になるポイントだ。
構成員「これまでと一貫した議論を」 事務局も路線継続強調
話をGX実行会議に戻すと、構成員からは「日本の産業競争力強化に資するGX実現に向けて、引き続き過去12回と一貫性のある議論を継続し、年内のビジョン策定に取り組んでほしい」といった意見が出た。
事務局は、「地域経済の成長に資する再エネや省エネは、総理の経済対策の指示の中でもフォーカスされている。ただ、その他のLNGの確保や原子力などが不要ということではない。本日も何人かの委員が言ったように、施策の継続性が重要ということは変わらない」と説明。原子力などについてもこれまでと同様に検討を進めていく方針を強調した。
GXビジョンやエネ基の案を年末までに示すのであれば、時間的猶予はあまりない。特にエネ基はこれまでヒアリングがメインで、本格的な中身の提示はこれからだ。後数回の会合で、どのような絵姿がいつ示されるのか、注目される。