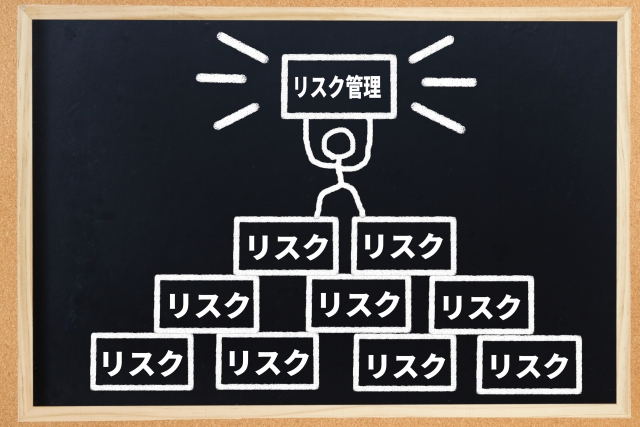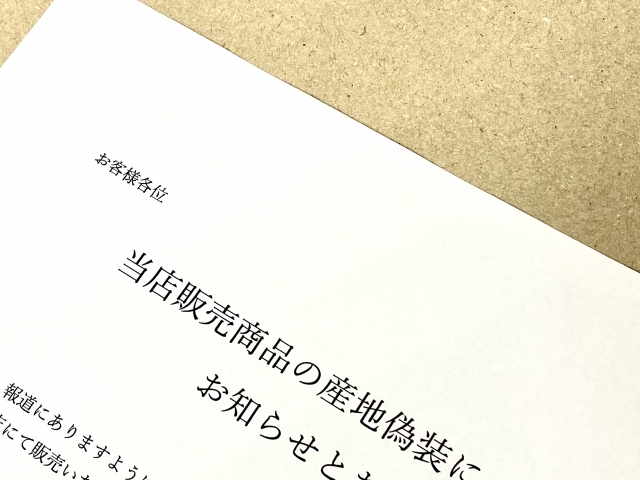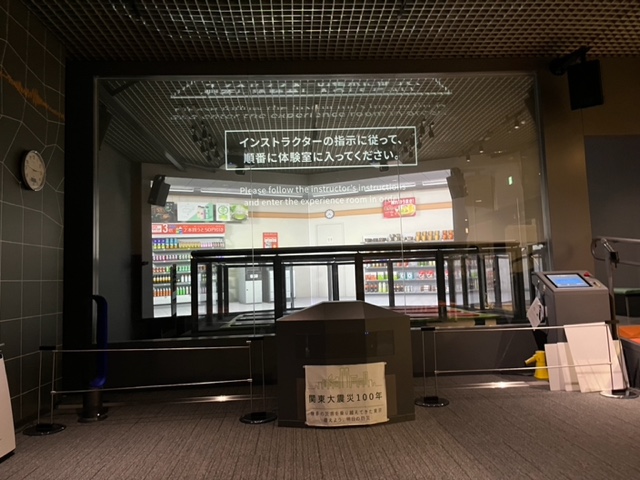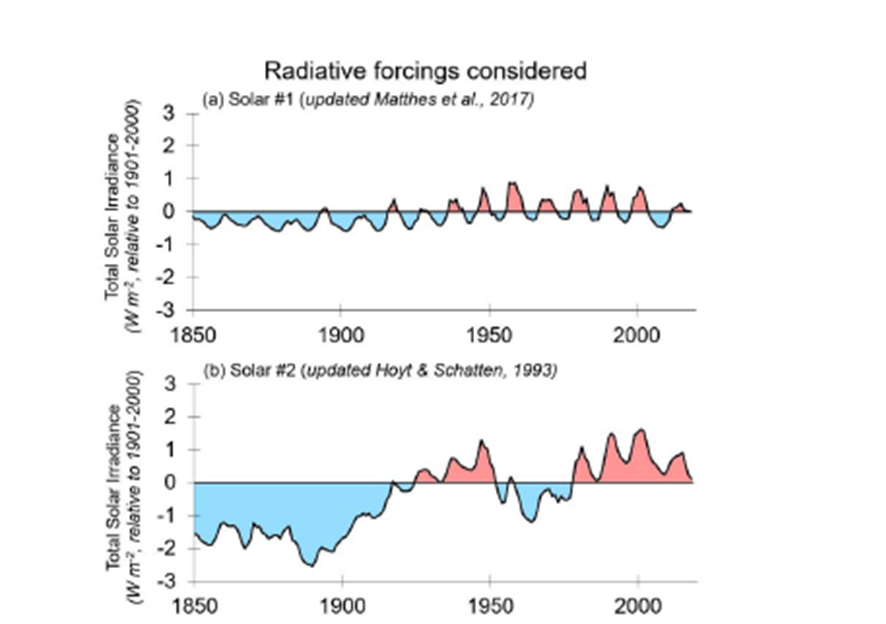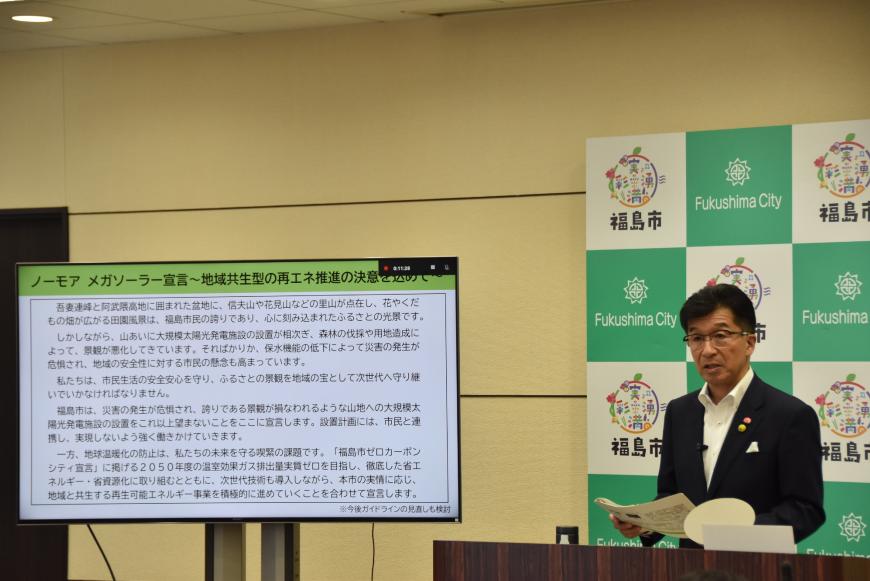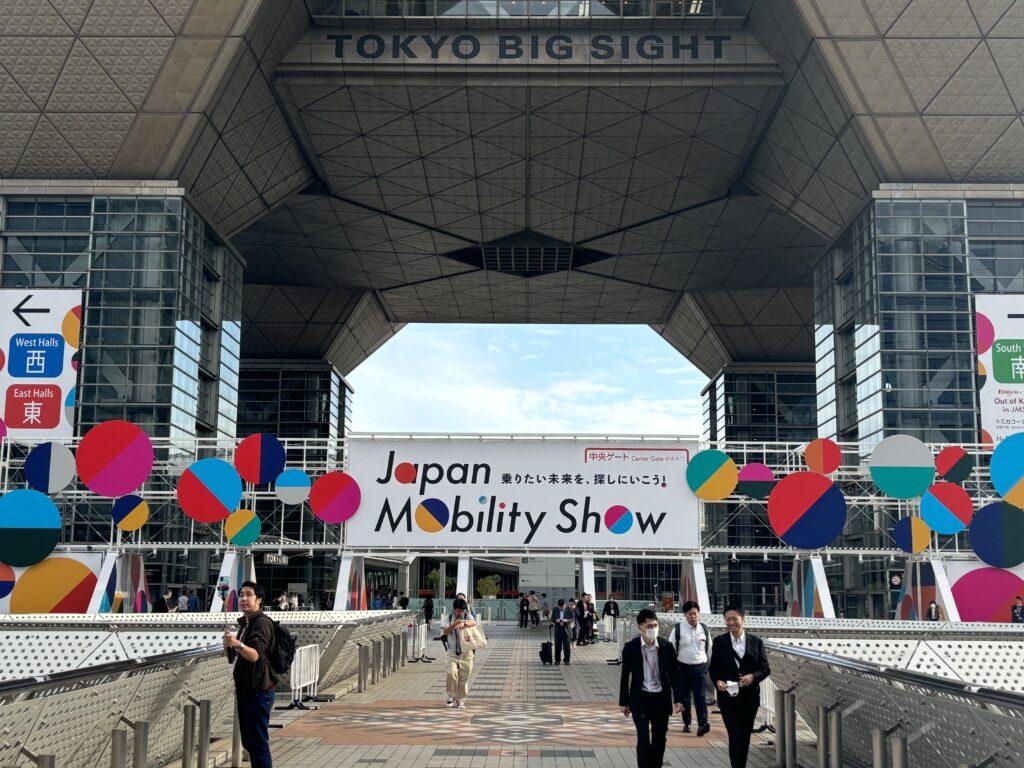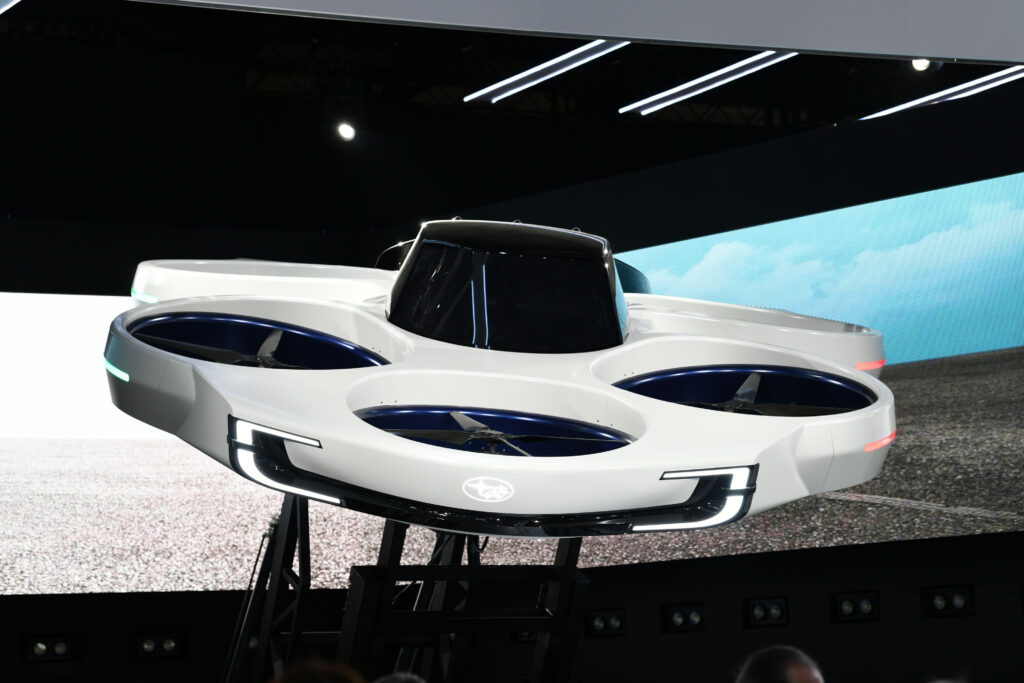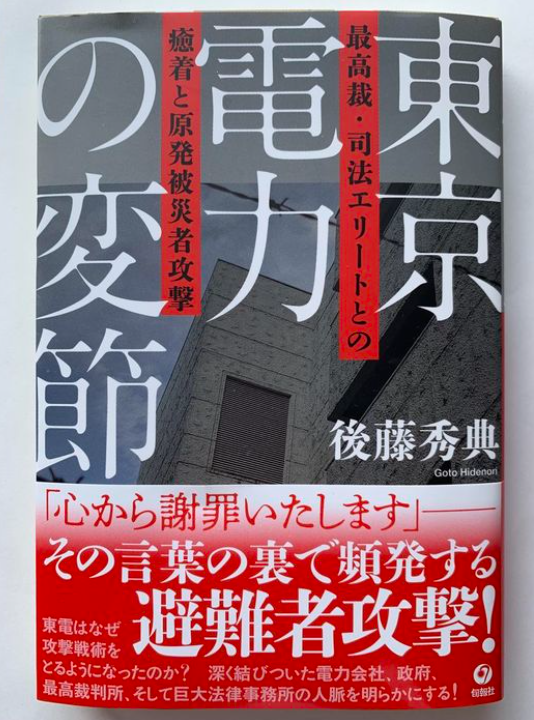公正取引委員会は今年3月30日、電力3社(中部電力・中電ミライズ、中国電力、九州電力・九電みらい)に対して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為(カルテル)について排除措置命令・課徴金納付命令を発した。(リーニエンシー=課徴金減免制度=を行った関西電力には排除措置命令も出されなかった)。カルテル行為に伴い、会社に発生する損害・費用としては、課徴金のみならず、第三者で構成する調査委員会の調査費用、官公庁の入札停止処分で失った利益などが考えられる。株主から、こうした損害を発生させたとされる現旧取締役に対して責任追及の提訴を請求する動きが、関西電力を含む4社に対して6月から出てきた。
~株主からの現旧取締役に対する責任追及の提訴請求への対応~
今年6月、電力4社はそれぞれの株主から、現旧取締役の責任追及の提訴請求を受領した。(中部6月21日受領、関西6月7日受領、中国6月8日 受領、九州6月8 日受領)。会社が60日以内に訴訟を提起しない場合、または提訴しないという回答を得た場合には、株主自身が会社を代表して訴訟を提起することになる。
結果としては、電力4社のうち中部、関西、九州の3社が訴えを提起しないことを決定する中、中国は8月3日、清水希茂前会長、瀧本夏彦前社長ら一部役員に責任追及の訴えを提起することを決定した。
提訴しないと決定した中部、九州は、「善管注意義務違反があったとは認められず、責任追及の訴えを提起しないこととした」と、いわば常套句で説明をした。
一方、関西は、「提訴した場合の勝訴の可能性、訴訟手続きにおける立証活動の範囲や負担などを総合的に判断し、責任追及の訴えを提起しない」と、いずれ出てくるであろう株主代表訴訟を意識したかと思われる理由付けをした。
〇関西電力7月28日のプレスリリース「訴えを提起しないことを決定」
「株主からの提訴請求への当社の対応」〈…… 独立性を確保した利害関係のない社外の弁護士に調査を委嘱し、その客観的かつ厳正な調査結果を受けて、対応を検討してまいりました。検討の結果、現旧取締役24名について、本件提訴請求に対して、対象者の責任の有無、提訴した場合の勝訴の可能性、訴訟手続きにおける立証活動の範囲や負担などを総合的に判断し、責任追及の訴えを提起しないことを本日の監査委員会、取締役会で決定しました……。〉
〇九州電力8月3日のプレスリリース「訴えを提起しないことを決定」
「株主からの提訴請求に関する当社の対応について」〈…… 当社は、独立性を確保した利害関係のない立場にある社外の弁護士に対して、本提訴請求書に記載の本件取締役の責任について調査を委嘱し、その調査結果の報告を受け、本件取締役の責任追及の訴えの提起の要否について検討してまいりました。検討の結果、本件取締役には、本件提訴請求書に記載の事項について善管注意義務違反は認められないことから、当社は、本日、いずれの本件取締役に対しても責任追及の訴えを提起しないことを決定いたしました。〉
〇中部電力8月9日のプレスリリース「訴えを提起しないことを決定」
「株主からの提訴請求への対応」〈…… 当社取締役とは利害関係のない外部法律事務所に調査を委託し、その結果を監査役会にて精査し、対応を検討してまいりました。検討の結果、本日、当社の全監査役は、当社の現取締役および元取締役20名に関し、本提訴請求書で指摘のあった事項について、善管注意義務違反があったとは認められず、責任追及の訴えを提起しないことといたしました。〉
~中国電力 株主からの現旧取締役に対する提訴請求への対応~
〇8月3日のプレスリリース「清水前会長、瀧本前社長らへの訴え提起を決定」
「現旧取締役に対する株主からの提訴請求への対応について」〈旧取締役3名(清水 希茂前会長、瀧本夏彦前社長、渡部伸夫元副社長)について責任追及の訴えを提起すること、その他の現旧取締役19名は不提訴とすることを決定。 〉*同日、清水前会長、瀧本前社長はそれぞれ相談役、特別顧問を辞任。*提訴理由については、下記10月4日提訴時のプレス資料参照
〇10月4日のプレスリリース「清水前会長、瀧本前社長等への訴えを提起」
「旧取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起について」〈—本年6月、当社の株主20名から当社監査委員宛の「責任追及等の訴え請求書」を受領したことから、提訴請求を受けた現旧取締役22名について、責任追及の訴えの提起の要否を検討した結果、当社監査等委員会は、旧取締役3名に対して責任追及の訴えを提起する ことを決定しました。当社は、本日、当該旧取締役に対する損害賠償請求訴訟を広島地方裁判所に提起しましたので、お知らせします。〉
*損害賠償請求額5992万6297円 =今後新たな損害が確定した場合には請求の拡張を行います*請求の原因 =公正取引委員会から受領した独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令が、現時点において法律上有効であることを前提とすれば、同委員会が設定した違反行為が行われたとされる当時(2018年11月~20年10月)において、清水希茂氏、渡部伸夫氏、瀧本夏彦氏には、取締役としての法令順守義務違反、監視監督義務違反および内部統制システム構築運用義務違反があったと判断しました。
具体的には、3氏は当時、法令に違反する行為に直接関与していたこと(法令順守義務違反)、3氏(取締役)相互もしくはその使用人の行為を是正・制止するための行為を取っていなかったこと(監視監督義務違反)、およびそれらの行為を防止するための具体的な内部統制システムの構築・運用が不十分であったこと(内部統制システム構築運用義務違反)が挙げられます。したがって、これらの義務違反により当社が被った損害について損害賠償請求を行うものです。
なお、当社は、公正取引委員会からの排除措置命令等に対し、取消訴訟を提起しており、将来においてその全部または一部について取り消される可能性があるため、取消訴訟の結果によって、本訴訟における訴訟上の主張を撤回または変更することがあり得ます。<引用終わり>
◎メディアの報道
10月5日、業界紙と地元紙は、中国電力の前会長・前社長らへの損害賠償請求提起を丁寧に報道した。
〇電気新聞10月5日付〈前社長ら3人に損害賠償請求提起〉〈中国電力、カルテル問題で〉〈 中国電力は4日、電力販売カルテル問題に関して清水 希茂 前会長と瀧本 夏彦 前社長、渡部 伸夫 元副社長の3氏に対し損害賠償請求訴訟を広島地方裁判所に提起したと発表した。〉〈…… カルテルを結んだとされる期間に取締役だった人物を提訴すべきとの株主の申し立てを受け、監査等委が元取締役について社内を調査。責任を追及すべきかどうかを検討し、8月3日に提起を決めていた。請求額は調査にかかった弁護士費用などの5992万6297円。連帯して支払いを求める。社内調査の結果、監査等委は3氏ともに「法令順守義務違反」「監視監督義務違反」「内部統制システム構築運用義務違反」があったと判断。—同社が被った損害の賠償請求を行うと説明している。〉〈 中国電力は9月28日に公正取引委員委員会の排除措置命令と課徴金納付命令に対し、取消訴訟を東京地裁に提起した。結果次第で、公取委から納付命令を受けた約707億円の課徴金額が変わる可能性もある。その場合は今回の損害賠償請求訴訟を撤回、もしくは変更することがある。〉〈中国電力の株主は6月、カルテルを行ったと公取委から指摘を受けた期間に取締役だった役員22人に対し、課徴金と電力入札の指名停止に伴う損害額として合計808億円の賠償を求めていた。〉
一方、地元紙の中国新聞は10月5日付朝刊で、取消訴訟、旧役員への賠償請求、そしていずれ株主代表訴訟と、3つの訴訟案件を抱えることになる状況を説明している。なお、この紙面において同紙は、元役員3名への賠償請求額が社内調査を依頼した弁護士費用に限定され、課徴金を含んでいない点について、草薙真一兵庫県立大副学長の「(取消訴訟で)3人の行為に伴う損害が確定してから追加請求する方法は妥当」というコメントを紹介している。
〇中国新聞10月5日付 〈中国電力、カルテル問題で三つの訴訟、公取委処分取り消し・役員への賠償請求の焦点は? 10/12には株主代表訴訟も〉 〈中国電力は、電力販売で関西電力とカルテルを結んだとされる問題に端を発し、今後三つの訴訟に対応する。 公正取引委員会の処分取り消しを求め、9月28日に東京地裁へ提訴した。 瀧本夏彦前社長たち元役員3人には今月4日、損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こした。 一部の株主は、他の役員経験者に損害賠償を求め、12日に広島地裁へ訴えを起こす。〉
*元役員3人への訴訟。 〈中電は清水希茂前会長と瀧本氏、渡部伸夫元副社長の3人に対し、計約5992万円の賠償を請求する。社内調査を依頼した弁護士費用で、課徴金は含んでいない。中電は6月、公取委がカルテルを結んでいたと認定した期間に取締役だった22人を会社として訴えるよう株主20人に求められていた。取締役会から独立する監査等委員会の判断を受け、3人の責任を追及する。監査等委員会と取締役会が社外の弁護士に委託して調べたところ、瀧本氏と渡部氏は自ら関電側と情報交換し、報告を受けた清水氏も容認したと確認した。取消訴訟の結果が出ない段階では、処分は有効と判断した。取消訴訟の結果によっては3人の責任原因に関する主張を変更、撤回する可能性があり、賠償請求額についても見直すとみられる。〉
*株主代表訴訟。 〈株主20人が広島地裁に訴えを起こすのは、中電が「違反行為に関与した事実はない」として提訴を見送る役員経験者19人(←10月12日の実際の訴訟提起では、会社が訴えた3氏も含めて22人)。課徴金に相当する約707億円の賠償を求める。カルテルに直接関与していない人を含め、当時の経営陣全体の責任を問うスタンスだ。〉
*識者の視点。 〈兵庫県立大の草薙 真一 副学長(エネルギー法)は……元役員3人に損害賠償を求める方針は「自らうみを出そうとする姿勢の表れ」と評価する。 課徴金相当分を当初の請求額に含めなかったことについては「(取消訴訟で)3人の行為に伴う会社の損害が確定してから追加請求する方法は妥当」とする。〉
~電力4社の株主代表訴訟~
株主からの現旧取締役の責任追及の訴え提起に対して、電力各社は、上記のように中国電力が一部役員を提訴することを除き、訴えを提起しないことを決定した。これを受けて、10月12日、各社の株主が当時の取締役らに損害賠償を求める株主代表訴訟を名古屋、大阪、広島、福岡の各地裁に起こした。
請求金額=関西12名約3508億円、中部14名約376億円、中国22名約707億円、九州電力8名約28億円
今回の訴訟提起では、被告となる役員数や請求額を絞り込むなどしており、中国や九州では、課徴金見合いの請求額となっている。その中で、関西に対しては課徴金が課されない中、約3508億円を賠償請求額とした。
〇電気新聞10月13日付〈4社株主、代表訴訟提起〉〈カルテル問題 役員数・請求額絞る〉 〈……各株主は12日、それぞれの地方裁判所に株主代表訴訟を提起した。今後の訴訟対応などを考慮し、6月に会社側へ役員提訴を請求した際に比べ、被告となる役員数や請求額を絞り込んだ。中国電力は既に3人を提訴しているが、同社株主らは別訴として3人を対象に含めた。各社株主はカルテル問題を巡り6月に会社側へ役員提訴を請求。課徴金のほか、社内調査費用や官公庁の入札停止処分で失った利益などの支払いを求めるよう主張した。〉〈 一方、中部、関西、九州の3社は8月までに会社側として提訴しない方針を決定。中国電は10月に清水 希茂 前会長ら3氏を提訴している。中部、関西、九州の3社株主は代表訴訟提起に当たり、役員の責任範囲や損失額などを精査したと説明。被告とする役員数を絞り、中部電は21人から14人、関電は24人から12人、九州電は25人から8人としている。……〉〈 中国電力の株主らは会社側が提訴した元役員3氏についても、課徴金額を請求していないことなどを理由に「二重起訴」には当たらないと主張。6月の提訴請求時と同じ22人を今回の対象としている。〉
ところで、関西電力への賠償請求について約3508億円となったことについて、各紙は次のように報じた。
〇朝日新聞10月13日付〈 ……カルテルを主導したと認定された関電。株主ら26人は八木誠元会長ら12人に対し、約3500億円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。課徴金は免れたものの、カルテルで電気料金を高止まりさせ、「今後賠償を求められるなど、潜在的な債務を負わせた」としている。〉
〇毎日新聞10月13日付〈 ……大阪地裁への提訴後、記者会見した河合弘之弁護士は「自由競争 を制限し、消費者から利益を吸い上げようとした。道義的に許されない」と批判。カルテルを主導した関電が課徴金を免れたのも不当だと訴えた。〉
両紙とも「カルテルを主導した関西電力」という表現が出てくるが、この点について触れておく。3月30日の処分発表時の公取委の記者会見では下記のような質疑が出てくる。
Q:今回のカルテルの中心になっていたのは、関西電力ということですね。
A:そこはですね。我々が審査した結果、関西電力が本件に違反行為を主導したという事実は認められなかったと評価しています。本件違反行為は、2017年頃から、中部電力管内、中国電力管内、九州電力管内の顧客を獲得するための営業活動を関西電力が行なっていて、それに対抗した中部電力、中国電力、九州電力と価格競争が進んだことを契機としていると考えています。各違反行為社は各社間で行われた顧客獲得競争によって電気料金の水準が低下した。関電のみならず各社が電気料金の水準の低落を防止して、自社の利益を確保する必要性を認識した。各社は顧客獲得の競争相手である関西電力との間で、それぞれ複数回の面談等を重ねて、本件合意形成したものであるということなので、事実関係として、関西電力が中心になったとか主導したというものでは必ずしもないのかなと思っています。
要するに、公取委では関西電力のみならず各社が電気料金低落防止、自社利益確保の必要性を認識、違反行為の合意はあくまで当事者双方の合意に基づくものであり、「関西電力が中心になったとか主導したというものでは必ずしもない」と言っている。
これに対して、メディアが「関西電力主導」と言うのは、関西電力が各社とそれぞれ、いわば扇の要として、しかも当時の副社長まで出て、調整に当たったことをイメージの中心において言っている。
~中国経済連合会会長人事~
ところで、中国電力が前会長、前社長らの訴え提起を決定したのだが、一連の流れの中で、地元のメディアが厳しい反応を示したのが、清水希茂会長(当時)が中国電力の会長を辞任表明している中で、中国経済連合会会長をいったん留任したことであった。3月30日、公取委によるカルテルの排除措置命令、課徴金納付命令を受けて、中国電力は清水希茂会長が6月(28日)の株主総会をもって会長を辞任、相談役に就任することを発表した。
一方、同氏が会長を務める中国経済連合会の総会が6月7日に開催され、清水氏の続投が決定した。この点について、地元メディア、全国紙地元版は、ネガティブな論調で記事掲載した。(見出しのみ紹介)
*読売新聞6月8日付〈清水氏 異例の会長続投 中電会長は引責辞任〉
*日経新聞6月8日付〈中経連、会長の続投決定 カルテル追及なし〉
*中国新聞6月8日付〈中経連 清水会長を再任 理事会反対なく続投要請〉
ところが、上記のように8月3日、中国電力は 株主からの現旧取締役の責任追及の提訴請求に関して、旧取締役3名(清水前会長、瀧本前社長、渡部元副社長)について責任追及の訴えを提起することを決定し、あわせて同日、清水前会長は相談役を辞任した。結果、中国経済連合会は、8月31日の臨時総会・理事会で清水氏の会長退任、芦谷茂・現中国電力会長の会長就任を決定した。
ジャーナリスト 阿々渡細門