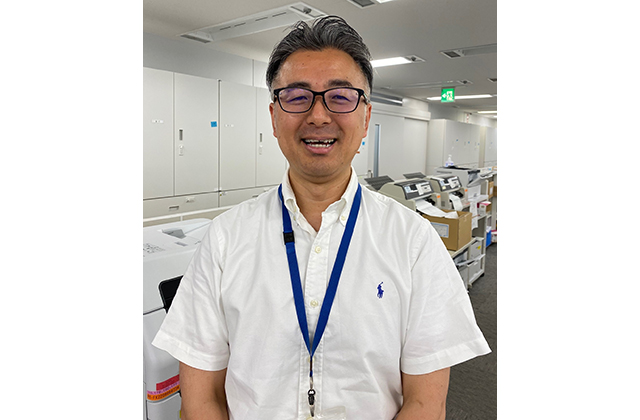矢島正之/電力中央研究所名誉研究アドバイザー
電力市場における競争の激化、分散型電源の大量導入およびデジタル技術の急速な普及などで、内外の電気事業のビジネスモデルは大きく変化している。そのような変化は、電気事業の価値連鎖のすべての段階でみられるが、とくに、顧客に近い販売分野は、顧客と電気事業の接点であり、同分野のビジネスモデルの変化は、顧客に対しての電気事業の顔の変貌を意味している。販売事業の成功には、プロダクトのデジタル化が欠かせない。ドイツでは、電気事業の販売部門でデジタル技術に支えられた様々なプロダクトが開発されているが、業界団体BDEWの調査によれば、デジタルプロダクトの販売を成功させるために販売事業に求められるものは、つぎのようなものである。
(1)プロセス、インターフェイスおよびプロダクトのデジタル化
(2) 顧客(とくに、フレキシビリティの利用可能性)に関する詳細な知識
(3) 顧客のニーズを最適化し、操作が簡単で理解しやすいプロダクト開発のための能力
(4) プロダクトのコスト最適化(最大の利益を実現するためのコストの適正化)
(5) 市場の発展とその企業収益や顧客行動への影響に関する早期認識
(6) 収益、コストおよびチャンスやリスクの展開に関する理解
(7) 良好なデータ品質を確保するための優れたデータ処理
(8) IT企業や保険会社のような新しいパートナーとの戦略的な協調
以上の成功要因から明らかなことは、販売事業に従事する企業は、新たなコンピタンスの獲得に迫られているということである。顧客のニーズに最適化し、操作が簡単で理解しやすいプロダクトを開発・販売する能力を有する企業は、大きな成功を収めることができる。そのようなプロダクトは、多くの場合、顧客のニーズに応じて多様なサービスをバンドルしたものであり、例えば、コモディティとしてのエネルギー供給と併せて、フレキシビリティや分散型電源を制御するサービス、さらには、セキュリティサービスや快適な暮らしをもたらすサービスなどを提供するプロダクトである。
また、販売事業は、供給コストの変化が複雑化してくることを理解しなくてはならない。例えば、系統の容量制約と間欠性の再生可能エネルギー発電の相互関係から供給コストの複雑な変化が生じる。将来的には、販売事業は、包括的なソリューションの価格付けにおいて、比較的単純なコスト見積もりによる価格設定を行うことは不可能である。事前に確実に見積もることができない価格に影響する要素が多く出現するからである。また、価格計算式に影響を与える要素をすべて適切に表現することは不可能と思われる。このため、販売事業者は、コストの変化を通じて販売のリスクとチャンスが増大することを認識しておく必要がある。
販売事業は、顧客と電気事業の接点であり、将来、破壊的なイノベーションが創出されるのは、主として顧客に最も近い販売部門と考えられている。このため、販売事業は、早期に事業全体のデジタル化を進め、プロダクト開発や顧客グループ等に関する中長期のポジションニングを行い、コモディティ販売(純粋なエネルギー販売)を超えた新たな価値創造戦略を開発することが求められている。
【プロフィール】国際基督教大修士卒。電力中央研究所を経て、学習院大学経済学部特別客員教授、慶應義塾大学大学院特別招聘教授、東北電力経営アドバイザーなどを歴任。専門は公益事業論、電気事業経営論。著書に、「電力改革」「エネルギーセキュリティ」「電力政策再考」など。