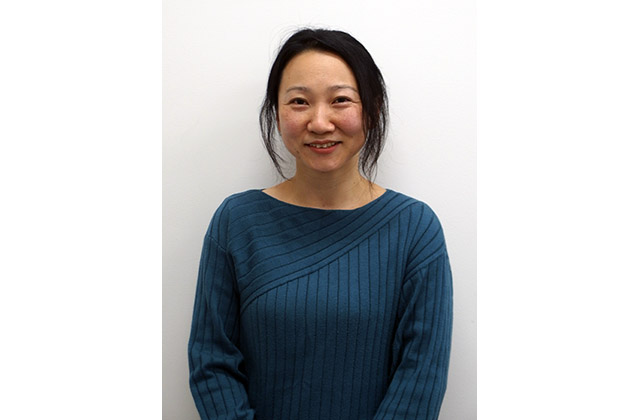資源価格高騰・円安進行を受け、エネルギー関連事業者が軒並み好業績を上げる中で、大手電力各社は総崩れの状態だ。

10月下旬に発表された2022年度上半期の決算(当期純損益)を見ると、大手電力10社のうち東京が1433億円の最終赤字を記録したのを筆頭に、東北1363億円、関西763億円、中国560億円、九州476億円、中部426億円、北陸381億円、沖縄168億円、北海道16億円と、9社が最終赤字に転落。四国だけが89億円の最終黒字となった。
通期予想を見ても、東京と九州が未定としている以外は、東北1800億円、関西1450億円、中国1390億円、中部1300億円、北陸900億円、北海道710億円、沖縄416億円、四国250億円と、大幅な最終赤字となっている。
最大の要因は、規制料金部門の収支悪化だ。石炭、LNG、石油の燃料調達価格が上昇する中で、燃料費調整条項に基づく燃調価格が全電力で上限(基準価格の1・5倍)に到達。超過分については、事業者側が負担する状況となっている。どの程度の負担額かといえば、事業者によって差があるものの、標準家庭(月使用量260kW時)の12月分料金で1400~3600円程度だ。仮に現状で燃調上限を撤廃すると、それだけの値上がりが発生することになる。
「燃料価格は過去にない水準に上昇し経営を圧迫している。このまま赤字が継続すれば、私どもの使命である電力の安定供給に支障をきたしかねず、複数の会社では規制部門の料金値上げが避けられない状況だ」。電気事業連合会の池辺和弘会長は11月18日の会見で、こう警鐘を鳴らした。
都市ガスは軒並み増益に 調整上限の影響受けず
その一方で、原料費調整条項の調整上限の大影響を実質的に免れた都市ガス会社の上半期決算は好調ぶりが目立った。主要6社の当期純損益を見ると、東京716億円、東邦68億円、西部71億円、北海道23億円、広島11億円の5社が最終黒字に。大阪だけが、米フリーポートLNGの火災事故の影響で割高なスポット調達を余儀なくされていることから、297億円の最終赤字となった。
通期予想では、東京1180億円(対前年比23・3%増)、大阪290億円(同77・8%減)、東邦160億円(同3・5%増)、西部100億円(同20倍)、北海道53億円(同1・2%増)、広島29億円(同20・8%増)と、全社が最終黒字だ。東邦を除き規制料金部門がないという事情もあり、大手電力との違いは鮮明だ。
ちなみに石油・LPガス主要各社の通期の純損益予想は、ENEOS3300億円、出光興産3250億円、コスモエネルギーホールディングス1150億円、岩谷産業300億円、伊藤忠エネクス130億円、ニチガス110億円と、こちらも全社が黒字だ。
いずれにせよ、大手電力の惨状が際立っているのは事実。安定供給体制を維持する上でも経営の健全化は急務だ。元凶である規制料金の在り方が問われている。