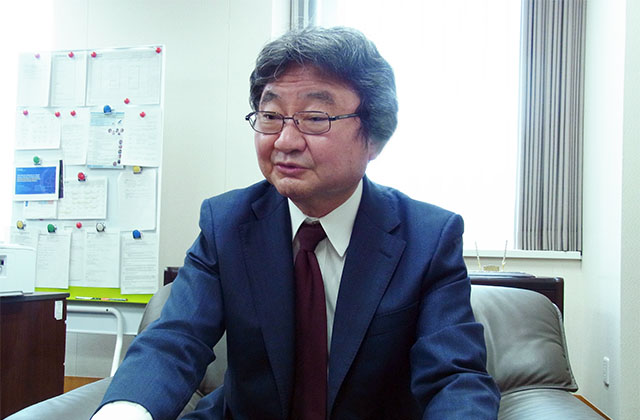LPガスが最も安定!? エネルギー事業に異変
カーボンニュートラル時代への対応が重要な経営課題になっているはずのエネルギー事業者に異変が起きている。
某地方で都市ガス事業とLPガス事業を運営するA社。2016年の電力小売り全面自由化以降、地域の再エネを活用する目的で新電力事業の展開に力を入れてきた。
「脱炭素化が世界的な課題となる中で、CO2を排出する化石エネルギーの一本足打法ではいずれ行き詰まるに違いない。数十年先の経営を考えれば、ガス会社といえどもカーボンフリーの電力事業を手掛けておくべきだと考えた」(A社幹部Ⅹ氏)
ところが、21年初頭に起きた卸電力市場価格の高騰を受け、電力事業は大幅な赤字に転落。春になり市場価格も落ち着き、収支が改善し始めたところに、今度はウクライナ危機による世界的なエネルギー価格の暴騰が発生した。歴史的な円安進行も相まって、燃料・電力調達価格の急上昇は新電力各社を直撃。事業の休止や撤退を余儀なくされるところが相次ぐ中、A社も事業存続の岐路に立たされている。Ⅹ氏が言う。
 電力事業に力を入れたが……
電力事業に力を入れたが……
「電力に気を取られているうちに、都市ガスの収支も悪化してきた。むしろ足元で安定しているのはLPガスだ。脱炭素化では劣勢に立たされているLPガスが収益に貢献して、最右翼の電力が窮地に陥るとは。将来を考えると、これでいいのかという気がして仕方がない」
国民生活・経済活動を支える低廉で安定した供給の実現こそエネルギー事業の土台。そこが揺らいでは、脱炭素も何もあったものではない。直面する難局をどう乗り切っていくか。事業者の経営手腕が問われている。
杉森氏に鴇田氏…… 不祥事辞任が相次ぐ
ENEOSの杉森務前会長、そしてTOKAIホールディングスの鴇田勝彦前社長と、エネルギー業界トップの不祥事による辞任が相次いだ。
杉森氏は女性への度を越した不適切行為、鴇田氏は交際費の不適切な使い込みと理由は違うが、共通するのは昭和の慣習から抜け出せない企業体質が現れた点だ。
杉森氏を知る人からすれば、今回の報道はさもありなん。普段はフランクな人柄で新聞記者や部下から慕われる親分肌だが、お酒が入ると態度が一変。東京・銀座の高級クラブでこうした態度を見せることもあったという。
杉森氏は旧日本石油の営業畑の出身。これまでは同じ営業出身で親分格でもあったW元会長の存在が重石になっていたが、W氏が亡くなった後は「タガが外れた」(石油業界関係者)。周囲も杉森氏の行き過ぎた行為を止めることはなかったという。
「旧日石の支店長クラスともなれば特約店を回る際などに過度な接待を受けることは当たり前で、派手にお金を使ってきた。しかし石油業界は今でも昭和の慣習が抜けていないと思われてしまい、甚だしいイメージダウンだ」と石油業界関係者は嘆く。
一方で鴇田氏の場合はというと、会食などで不適切な経費の使い込みが発覚したとして、9月15日の同社取締役会で社長を解職された。経産省OBの鴇田氏が同社社長に就いて17年。「元社長のF氏によるワンマン経営から脱却し、グループ再編や持ち株会社化などで果たした功績は大きいが、あまりにも長く社長をやり過ぎた。社内には不満がうっ積しており、今回の電撃解職は〝5人組の反乱〟と見る向きもある」(事情通)
有能だが遊び好きで豪放磊落なトップが許容されたのも、今は昔。企業経営ではコンプライアンス重視の傾向が一段と強まっていこう。ただ、そこに一抹の寂しさを感じてしまうのは、なぜだろうか。
天下り先決まらず 役人「冬の時代」到来
国家公務員総合職の希望者が減っている。かつては全国のエリートが中央官庁の幹部への道を目指した。だが日本経済が長く低迷する中、官僚たちを取り巻く環境の変化が、優秀な学生たちに霞が関で働くことをためらわせているようだ。
旧科学技術庁出身で文部科学省の幹部を務めたT氏。自他ともに認める「やり手」官僚だったが、今年3月に退官した。以前ならば、文科省の関連団体などに相応しいポストが用意されていたが、「まだ天下り先が決まっていない」(文科省関係者)。
 役人に冬の時代が到来しつつある (文科省)
役人に冬の時代が到来しつつある (文科省)
もっとも財務省や経産省のOBには、今も手厚い再就職の斡旋がある。しかし旧科技庁の関連組織は規模を縮小する傾向にあり、「天下り先の確保が難しくなっている」(同)。エリートたちが冬の時代を迎えつつある。
福井で地層処分の動き 業界は「ありがた迷惑」
原子力施設の集中する福井県・嶺南地区で、高レベル放射性廃棄物の地層処分を実現させようという動きが起きている。原子力関連団体が地元政治家を集め、勉強会などを開催。しかし電力業界関係者からは、「ありがた迷惑」「難しい状況で余計なことをしないでほしい」などと活動を警戒する声も聞かれる。
団体はO町、M町を中心に、ここ数年、著名人と地元の政治家と合同でセミナーを開催している。原子力関連の学会、ゼネコンなどが支援し、研究者や電力会社のOBが集まっているが、電力業界と直接の関係はない。団体側が「地層処分の可能性を探るのが真の目的」と周囲に話していることが関係者に伝わり、一部の関係者の不信を強めている。
長く原発と共存してきた嶺南地区では原子力に対する拒絶感は少なく、個人レベルでは地層処分に肯定的な人がいる。それにつられ、団体は北海道寿都町のように地層処分受け入れの窓口を作ろうとしているようだ。しかし、「嶺南地区の原発は再稼働や使用済み燃料の中間貯蔵の問題を抱える。いま地層処分について行うべき行動ではない」(電力業界関係者)。
福井では県と地元の政治関係者が一貫して「放射性廃棄物を県外に出す」政策を掲げている。一方、行き場が決まらない使用済み燃料の中間貯蔵は重い問題だ。
福井県で原子力発電を行うK社やN社は現在、再稼働とリプレース問題などで手一杯だ。エネルギー業界関係者も政治家も、高レベル廃棄物の最終処分の話などする余裕はなく、地層処分の議論は逆に原子力批判派に攻撃の材料を与えかねない。
「ありがた迷惑な面もある。活動をやめていただければいいのだが」。電力業界関係者はこう頭を抱える。
BGかプールか 電力市場改革で混乱
バランシンググループ(BG)制度の維持か、パワープール制への移行か―。資源エネルギー庁の有識者会合で議論されている卸電力・需給調整市場改革の方向性を巡り、電力業界が混乱の様相だ。
要因は10月4日の会合でエネ庁が提案した、効率的な電源の運転と最適な供給力(kW時)と調整力(⊿kW)の調達を実現するための「同時市場」を巡る議論にある。
これは、前日市場の入札方法としてThree-Part Offer(ユニット起動費、最低低出力コスト、限界費用カーブでの入札)を導入。この情報を踏まえて一般送配電事業者(TSO)がkW時と⊿kWを含む電源起動(停止)計画を作成し、小売り事業者は自社の調達需要とTSOの予測需要との差分も含めて確保する仕組み。
エネ庁の提案では相対契約で事前に売り先が決まる「セルフスケジューリング電源」も認めるとしている。だが同日の会合で学識者委員のM教授は、「なぜ、セルフスケジューリング電源などわざわざ設けるのか理屈が示されていない」と述べ、事実上のプール制への移行を主張したのだ。
業界関係者X氏は、同時市場は「BGが計画値同時同量を達成するために必要な量をしっかりと確保するための仕組み」との認識。エネ庁も、あくまで現行のBG制度は維持するというスタンスを変えていない。
別の業界関係者O氏は、「送配電事業者の間でコンセンサスが取れているわけではない」と、この議論を巡るもう一つの問題を指摘する。BGかプールかはともかく、同時市場に移行するとなれば大改革になることは間違いない。機能不全に陥ってしまった現行の電力システムの二の舞にならないよう、より冷静な議論が求められる。