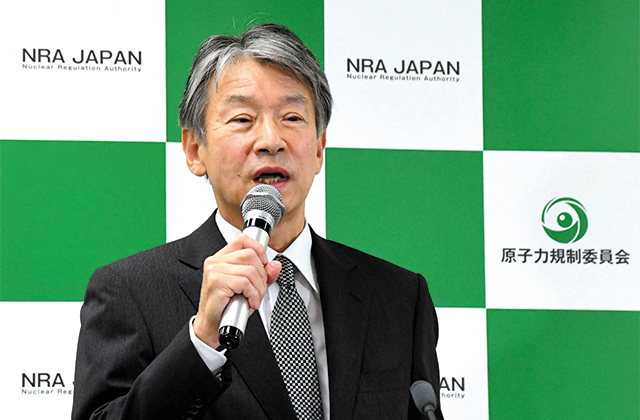<出席者>電力・ガス・石油・マスコミ/4名
首相はGX実行会議で原発再稼働に意欲を見せ、次世代革新炉の検討も要請した。
業界内には期待する声がある一方、実現性を疑問視する向きもある。
―岸田文雄首相が8月24日のGX実行会議で、「原発回帰」と受け止められる発言をした。再稼働を国が前面に立って進めるとし、次世代革新炉の新増設・リプレースの検討を要請している。電力業界は「ようやく政府が動いてくれる」と思ったはずだ。
電力 まぁ、ありがたいと思っている。だが、どこまで本気で政権が取り組むかだ。首相が言う冬までの9基の稼働はほぼ確実だった。ただ、来年夏以降に運転開始を目指す7基は分からない。
特に柏崎刈羽6、7号機と東海第二は、地元同意のハードルが高い。首相が現地を訪れて、地元の人たちに再稼働の必要性を訴えるしかないと思っている。
―次世代炉についても首相発言で関心が高まった。
電力 新増設・リプレースもSMR(小型モジュール炉)や高温ガス炉に期待する声が強まりそうだ。経済産業省も原子力小委員会を開いて革新型炉の開発を打ち出している。だが、役所と業界の本音はABWR(改良型沸騰水型炉)、APWR(改良型加圧水型炉)を改良した大型次世代軽水炉の開発を加速させて、国内に建設することだ。
マスコミ SMRが海外で建設されるようになれば、製造に参加している日本メーカーも潤う。それは歓迎だろう。しかし、原子力産業の将来を考えると、屋台骨の三菱重工、東芝、日立とそれらの傘下企業が生き残ることを考えなければいけない。
そのためには実績があるABWRと、美浜1・2号のリプレース、敦賀3・4号増設に計画があるAPWRを軸にした原子炉の建設を優先すべきだ。経産省の判断は間違っていない。政策的な支援も当然、考えているはずだ。
―朝日、毎日などは新増設・リプレースなどに反発しているが、国際大学教授の橘川武郎さんもプレジデントオンライン(9月11日)で「どれも雲をつかむような話ばかり」と批判していた。
石油 大分反響があったようだ。橘川さんは、革新炉について「誰が何をどこで造るか決まっていない」と指摘している。確かにその通りだ。言いたいことをいう性格だから、思っていることを書いたのだろう。ただ、電力さんの言う通りならば、業界、メーカーが国内に造るのはABWRとAPWRの改良型になる。
マスコミ 影響力のある人の主張だけにインパクトがあった。「『次世代革新炉の開発・建設』を本気で行うのであれば、『既設原発の運転延長』を行う必要はなく、両者を同時に掲げるのは論理矛盾」と指摘している。これには首を傾げた。本気でカーボンニュートラルを目指すならば開発・建設と延長を同時に進めないと、とても間に合わないと思うよ。
毎日の目立った記事 首相発言の舞台裏を暴露
―首相発言についての記事はほかにもあった。
ガス 一連の記事で際立ったのは、毎日の「原発こそ新しい資本主義、首相の原発回帰宣言、舞台裏と打算」(9月6日)だ。首相発言を聞いて、これは経産省のいつもの文章と書きぶりが違う気がした。
そう思っていたら、首相が自ら「『政治決断が求められる項目を明確に(私に)示してもらいたい』と指示。原発を所管する経産省幹部さえ『寝耳に水』のサプライズだった」と書いてあった。それで合点がいった。
マスコミ 複数の記者が政府関係者に突っ込んだ取材をしている。「気候変動対策とは資本主義の在り方自体を見直すこと。政権中枢には早くからこうした問題意識が共有されている」との経産省幹部の話しは、是非は別にして参考になった。
―政府と歩調を合わせたのか、日経新聞が編集方針を見直したようだ。社説「エネ・環境戦略を問う」(8月18日)で、「原発新増設へ明確な方針打ち出せ」と主張している。
ガス 日経新聞のトップは連日のように財界幹部と顔を合わせている。その場で、「(再エネ偏重の)最近の紙面はなんだ」と言われることが多いらしい。それで、トップダウンで原発について方針の見直しを指示したようだ。
石油 編集・論説委員クラスも「最近、『脱炭素新聞』とやゆされる」とこぼしていた。ただ編集の現場のマインドは、そう簡単には変わらないと思うよ。
―日経は社説の後、連載「原子力政策転換の行方」(9月6日)を始めている。
マスコミ よく取材して原子力政策を巡る課題をまとめていると思う。ただ、「基本的なスタンスは前と変わってないな」と思うところもある。
日経の連載に違和感 基本的立場変わらず
―例えば。
マスコミ 「政府・与党内には規制を緩めれば、再稼働を早められる原発はあるとの見方もある」と書いている。特重(特定重大事故等対処施設)の完成が原子力規制委員会が定めた5年間の猶予期間に間に合わず、そのために止まっている原発を動かすことだ。
テロや自然災害などに対応する特重は、万一の場合に備えるもので原発の安全運転に不可欠ではない。工事の現場での不可抗力に近い理由で工期が遅れる場合に、稼働させることは、決して「規制を緩める」ことではない。
電力 原子力に理解のある与党議員や電力業界は、規制委に審査の効率化を求めるが、「規制を緩めてほしい」とは絶対に言わない。そんなことを言えば、世間から袋叩きになることは分かっている。ただ、マスコミに書かれたら仕方がない。
―結局、電力業界は泣く子とマスコミにはかなわないんだよ。