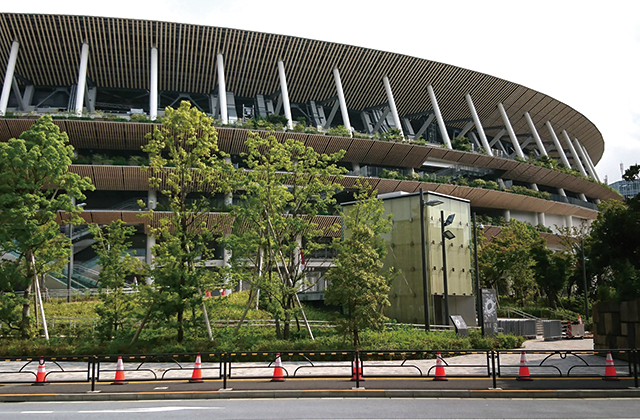テーマ:経産省・環境省の概算要求
エネルギー特別会計を巡る2023年度予算の概算要求がまとまった。エネルギー安全保障に寄与するとともに、脱炭素効果の高い電源の活用を促す中身となっている。
〈出席者〉A政治家 Bエネルギーアナリスト Cエネルギー業界関係者
―エネルギー危機下の概算要求をどう見ているか。
A 予算額は膨らませてあるが、政策に目新しさはない。ロシアによるウクライナ侵攻を経て、エネルギー価格は高騰し、円安が進行。国際的なLNG調達環境は大きく変わったが、概算要求からはいかに対応していくかという変革への意識が見えてこない。
B 本当に必要なものに資金が振り分けられているのか疑問だ。喫緊の課題はLNGや石炭の安定供給だが、例えば「系統用蓄電池や水電解装置等の導入支援による電力網の強化」に新しく100億円が充てられている。不必要とは言わないが、化石燃料をいかに確保していくか、という視点が欠落している。
LNGの貯蔵量は、ガス会社が約1カ月分、電力会社はわずか2~3週間分しかない。少なくとも、それを倍増させる必要があるだろう。そのための設備費を負担する仕組みを考えなければならない。
A リスクにさらされた時のために、戦略的に国内の備蓄基地を構築したり、各社のパイプラインを接続したりしないと意味がない。国が何をやるのかが、何も見えない。
C 大手ガス会社などのLNG基地は、各社の需要想定の中で目一杯に使っている。ただ、一部には稼働率が悪いところもあると聞く。効率はよくないが、そこで貯蔵する方法も考えられなくはない。
A 概算要求ではJOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)への出資金を増額させた。数年に一度、法改正を行って業務を拡充しているが、権益確保につながっているのか。無秩序な投資を行った前身の石油公団に逆戻りしていないか、検証する必要がある。
C かつて経産省はあらゆる手段を使って石油の確保に努めたが、LNGにはさほど関与してこなかった。しかし、今はLNG確保のため、カタールやオマーンに赴いている。サハリン2の運営会社を再編する大統領令が出された時、当時の萩生田光一経産相と保坂伸資源エネルギー庁長官はかなり慌てていたという話も聞く。経産省はとにかくロシアを刺激しないことを最優先にしているようだ。
A 三井物産と三菱商事が新たな運営会社から参画を認められ、JERA、東京ガス、広島ガス、東邦ガスもこれまでと同じ内容で購入契約を結んだ。目先ではうまく対応できているように見えるが、中長期的な視点で見た場合、外交的な負債になりかねない。
来年5月、皮肉にもLNGの半分をサハリン2から調達する広島ガスの本拠地、広島でG7サミットが開催される。各国首脳がロシア制裁について議論する最中に、ロシアから「空調が効いた涼しい部屋で会議ができるのは、ロシアのガスのおかげだ」と言われたらどうするのかな。
B LNGのスポット価格が世界的に高騰する中で中東や東南アジア、オーストラリアなどのLNGは今後、これまでと同じ条件で契約更改できなくなる。となれば、依存度を減らしていくしか方策はなく、原発の活用が重要になってくる。運用中の原発33基を全て稼働させると、LNG2000万t分に相当する量を削減できるが、これは日本の全LNG輸入量の約4分の1に相当する量だ。

―岸田文雄首相は8月24日、GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議の第2回会合で、原発再稼働や新増設に言及した。原子力政策に進展はあるのか。
岸田発言は単なる現状追認 今こそ原子力政策の再構築を
C 本来、原子力は国家の中長期エネルギー戦略の要の一つと位置付けるタイミングだ。しかし、経産省は再稼働と新増設が必要な理由として、「足元の危機」を利用しているようにも見える。GX実行会議で経産省が示した資料は、「エネルギー政策の遅滞」として、系統整備や原発再稼働などの遅れを指摘した。そして、需給ひっ迫など足元の危機を克服するために、原発再稼働や次世代革新炉の開発・建設などが必要だと唱えている。
B 需給ひっ迫を再稼働の理由にしていては、状況が打開されたとき「原発は必要ナシ」と言われてしまう。早急な再稼働と、中長期的な計画の策定は分けて行うべきだろう。
A 原子力政策は「急がば回れ」だ。いま破綻している原子力政策を、根本から再構築する必要がある。最終処分地や核燃料サイクル、国と事業者の役割分担、規制のあり方、技術開発の方向性、そのスケジュール……。政府はその大枠を提示すべきだ。今のままでは、有権者から「最終処分地はどうするのか」と聞かれたとき、政治家はハッキリと答えられない。最近の世論調査では、再稼働に半数以上が賛成している。国民の理解を得られる土壌ができ上がった今こそ、原子力政策を立て直す好機だ。
B すぐに取り掛かってほしい。稼働を停止して10年が経ち、現場での実務経験がない人が増えている。残された時間は長くない。規制委改革も待ったなしだ。三条委員会で政治が直接に指揮・命令できないが、業務監視は求められている。3・11以後、なぜ日本だけが原発を停止しながら審査を行っているのか、なぜ10年もかかっているのか、委員の選任は適切だったのか―。
A 規制委といえども、原子炉等規制法(炉規法)に基づいての規制しかできない。審査自体には政策的な関与はできなくても、そもそもの審査方法の枠組みや規制体系の見直しは、炉規法を改正できる立法府の役割だ。例えば、不服がある場合は第三者に申し出られる仕組みの導入など、改善できる点は多い。
新規制基準は、紋切り型のように「世界で最も厳しい」といわれるが、その厳しさは「質」ではなく「量」だ。「世界一厳しい規制をやっている」という政治家の言い訳のために、電力会社が苦しめられている側面もある。
B 裁判で例えれば、規制委は裁判官と検事、弁護人までを兼ねているようなものだ。被告のように扱われる電力会社は、炉が止められ、拘置所に入れられた挙句、無実を証明するまで出られない。
C 2年前、自民党政調の原子力規制に関する特別委員会で、規制庁は40年運転制限ルールは立法政策の問題と改めて確認した。また今年の同委員会では、安全審査が行政手続法上の標準処理期間である2年を遥かに超えて遅滞していることを指摘した。GX実行会議でも「運転期間延長」いう言葉が入った。今後、事態がどう進むかだ。