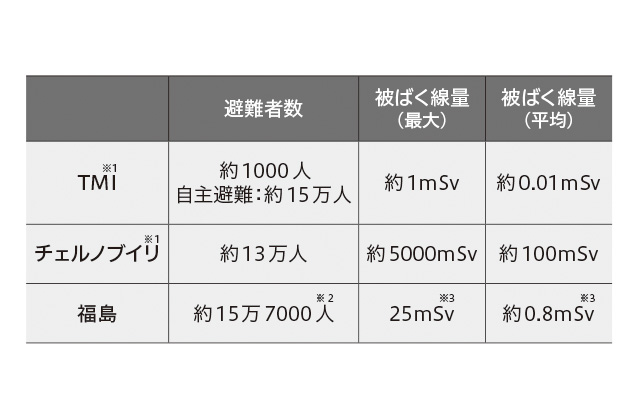<出席者>電力・石油・マスコミ・ジャーナリスト業界関係者/4名
自民党総裁選で河野太郎氏が、党員、国会議員から多くの支持を集めている。
核燃サイクルを否定する河野氏の動向を、業界関係者は息をひそめて見つめていた。
――自民党総裁選に出馬した河野太郎氏は「核燃料サイクルを手じまいする」と発言した。河野氏を支持した党員・党所属議員は多く、業界関係者はショックを隠さなかった。
電力 核燃料サイクルを止めることは河野氏の持論だから、出馬した時、業界関係者は表面上、冷静さを保っていた。しかし、支持を集めて新総裁の「有力候補」となっていくと、「ほかの候補なら誰でもいいが、河野氏だけはだめだ」と言い出すようになった。
――原発については再稼働を容認したが。
電力 確かに、カーボンニュートラル実現のために、原発に一定の理解を示して再稼働を容認した。しかし、使用済み燃料の再処理を中止する持論は変えていない。
もし青森県六ケ所村の再処理事業を止めると、三村申吾知事は、「では、県内の使用済み燃料は各原発に持ち帰って下さい」と言い出す。県はあくまで、再処理をしてプルトニウムでMOX燃料をつくり、出てくる高レベル放射性廃棄物は青森県外で地層処分することを条件にして、使用済み燃料を「一時保管」として引き受けているからだ。
仮に三村知事が使用済み燃料をそれぞれの原発に送り返したら、どうなるか。どの原発も保管するスペースは限られているし、地元は猛反発する。全てが徐々に停止していくだろう。読めないのは、河野氏がそこまで見通して再処理の中止を言い出したかどうかだ。
――河野氏の真意を読むのは難しいようだ。
マスコミ 自民党議員の中には、「そこまで考えている」と断言する人がいた。一方、「河野さんは原子力を進める上で、青森県や地元が果たす役割をよく理解していないのではないか」と見る関係者もいる。
こういう話を聞いたことがある。かって河野氏は、「再処理を中止する場合、まず大切なことは、青森県や関係する地自治体に謝罪にいくことだ」と言った。すると、それを聞いた三村知事が「正直な男だ」とほめたという。もっとも、聞いたのは大分昔のことだ。今、再処理事業を止めたら、もう三村知事に謝罪で済む話ではなくなっている。
サイクル中止宣言 有識者から賛同も
ジャーナリスト 河野さんが核燃サイクル中止を言い出したことで、マスコミや有識者、さらに業界の中にもある再処理事業に否定的な声が大きくなっている。アゴラ研究所の池田信夫さんが、ウェブで「新首相『核のゴミ』問題を解決する簡単な方法」という記事(9月17日)を載せている。
核燃サイクルは大赤字の事業だから、原子力事業を守るためにも使用済み燃料の再処理を止めて、直接処分に方針を変更すべきだという内容だ。池田さんはもともと再処理事業に難色を示していたと記憶しているが、総裁選の真っただ中の時期に記事が出たので、驚いた。
マスコミ 池田さんは、原子力事業に占める地元自治体の重要性をよく理解していないと思う。確かに、電力会社の中にも、できれば再処理事業から撤退したいと思っている人たちがいる。どの原発も新規制基準に対応するため、安全対策に膨大な費用をかけている。それでも、稼働できるか不透明な原発もある。
加えて、小売り市場の競争激化で、体力は疲弊していくばかりだ。それでいながら、国は核燃サイクルを維持する費用を捻出する仕組みをつくろうとしない。そう考えると、撤退を考えるのは当たり前のことだ。
ジャーナリスト だが、問題は地元がどう反応するかだ。もし河野さんが本当に青森県やほかの原発立地道県を説得できるというなら、電力業界は再処理断念・直接処分に方針を変えるのではないか。
「改革者」でアピール 調整能力に難点も
――河野氏についてはエネルギー政策以外にも、政治家としての資質の点でほかの候補よりも批判が多かったようだ。
ガス 「改革者」のイメージが強くて、実行力、突破力で党内外の人気を集めている。だけど首相になれば、複雑な利害を調整する能力が必要になる。その点を評価する人たちは、まずいない。
ある政治家からこんな話を聞いた。河野さんが防衛大臣の時、北朝鮮のミサイルに備えて、打ち落とすため陸上配備型のイージス・システムを自衛隊の秋田県の新屋演習場と山口県のむつみ演習場に建設する計画が持ち上がった。ミサイルの発射基地が地元に造られることを歓迎する人はいない。それで両方で、政治家や防衛省関係者が地元への説明や説得に当たっていた。
ところが、新屋演習場の施設から発射すると、ブースターが陸地に落下する可能性が分かった。それで河野さんは何の相談もなく、導入を断念すると言い出した。これに激怒したのが、山口県で懸命に地元の説得に当たっていた政治家だ。その後、菅政権が出来た時、河野官房長官という話が浮上した。だけどこの政治家は、「それだけは絶対にない」と断言していた。
――マスコミはどうか。原子力に否定的な朝日、毎日、東京は「河野支持」の論調では。
石油 いや、中立的なスタンスで記事を書いている。ただ、右寄りの人が多いネットの世界では、圧倒的に人気があるのは高市早苗さんだ。「虎ノ門ニュース」という右派の論客が出るユーチューブ番組がある。そこでアンケートを取ると、98%が高市支持だった。
――この座談会が掲載された雑誌を発行する時には、もう総裁選の結果が出ている。今は「河野総裁」が誕生しないことを祈るばかりだ。