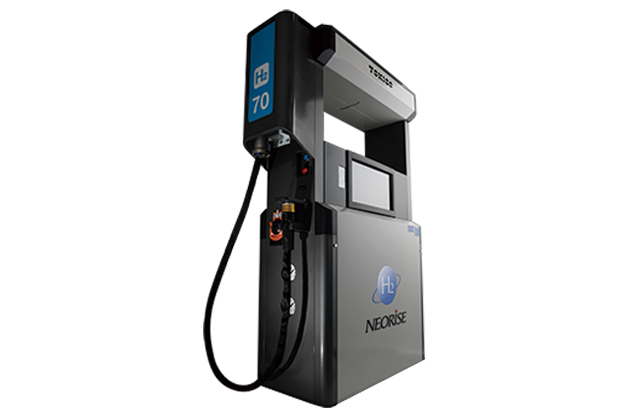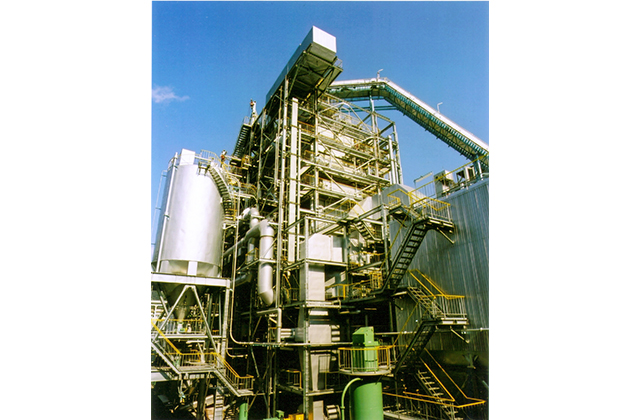飯倉 穣/エコノミスト
1,2050年カーボンニュートラルを目指したエネルギー基本計画素案が提示された。その実現に必要なファイナンスを考える上で、興味深い金融記事があった。
「東芝、買収合戦の様相 CVC、ベインと連合 KKRも検討」日経2021年4月15日
「東京4度目緊急事態 政府決定 違反の店「厳しく対応」、休業要請「金融機関も働きかけを」」朝日夕同7月9日
「気候変動対策 動き出す日銀 環境融資 金利ゼロで資金貸付 金融機関を長期支援 緩和維持 みえぬ出口」朝日同17日
金融機関(投資ファンド)の行動、金融圧力利用の政府発想を見つめ、金融仲介機能に着目した日銀の取組を考える。
2,2030年温暖化ガス46%削減目標の「エネルギー基本計画(素案)」の審議があった(7月21日)。大胆な省エネを前提に、1次エネ供給構成で再エネ20%、原子力10%、化石エネ70%を目指す。電源は、再エネ36~38%、原子力20~22%、化石41%(うちガス20%、石炭19%)を掲げる。中身と可能性のチェックは今後だが、その実現に向けてエネルギー開発・転換、省エネ等で膨大な投資資金需要が見込まれる。
第一次オイルショック後と同様、そのファイナンスに関心が集まる。市場の失敗等も予見されるので、短期は政策、長期は市場任せとしても、民間金融の行動が鍵である。
3,金融は、資金保有者から不足者への資金の流れである。その担い手は、金融仲介業であり、金融機関、証券会社が典型である。加えてファンド等の運用機関もある。
近年成長鈍化に伴う投資機会の縮小や緩和的金融政策を背景に「お金でお金を儲ける強欲資本主義(資金の効率的運用)」の動きが顕著である。通貨は、交換・計算・保存機能手段と見れば無機質だが、富や稼ぎの象徴となると「欲望」その物で厄介な面がある。
日本版ビッグバン(金融自由化)以降、金融業は、Predatory(略奪者)の性格を強め、高利貸しの本性を露わにしてきた。金融の見る企業統治・事業統治、資産構成・資本構成の最適化、企業再編、プライベートエクイテイ、産業金融等々は、収益確保の投資機会である。働く者にとって、企業・事業の最適化となるか未知である。
その例は、2000年代以降のファンドの活劇(ステイールとサッポロビール、TCIと電発等)に見られ、最近の東芝である。東芝関連「エフィッシモ・キャピタル・マネジメント」等の動きは注目に値する。目指すところは、投資利潤の最大化である。企業を支配し事業分割・売却や合理化で企業価値を向上させ、投資額に対し数年で年率20%超の回収を目指す。金融収益の低迷に悩む銀行等金融機関の行動も大同小異である。
金融機関に地球温暖化防止のための事業者金融を推奨し、それを中央銀行が支援する。首を傾げてしまう。
4,コロナ対策で、金融機関の積極的関与を求めた某大臣の発言に対する反発はすさまじかった。そこに金融機関の姿がある。「晴れの日に傘を貸して雨の日に取り上げる」は、金融の常道である。金融の論理と事業者の思いは異なる。利用者で、金融機関にシンパシー(親近感)を感じる人はいないだろう。故に金融機関は、裏方に徹する。またそのような立場である。近時金融力のアピールを見かけるが、極めて危うい。公的規制で、化石燃料投資を排除することは十分納得的であるが、金融の力で行うことに疑問が残る。
5,そのことも考慮してか時流に乗ってか、日銀が「気候変動対応を支援するための資金供給の骨子」(7月16日)を決定した。金融機関の気候変動名目の投融資を対象に金利ゼロ%、期間1年(借換可能)、30年度まで貸付を実施する。
日銀は、10年以降経済活性化を求める政治の要請に呼応して、政策金融類似の金融措置を実施してきた。成長基盤強化を支援するための資金供給(10年9月開始)、貸出増加を支援するための資金供給(13年開始)、アベノミクスの大胆な金融緩和政策(13年開始)である。成長基盤強化支援や貸出増加支援の資金供給が民間金融機関の貸し出し増を招来したか不明である。
また金融政策の効果は、実質経済成長率(12~19年度年平均0.8%)や財政改善面(公債残高12年度末705兆円、19年度末887兆円)で現れていない。ただ日銀のバランスシートの際限なき拡大を招来している(13年3月164兆円⇒20年3月604兆円) 。日銀の動きは、むしろ経済不安定を助長している。
6,今回の気候変動対応貸付は、バックファイナンスであり、金融機関支援と理解できても、気候変動対応への量的・質的効果は要領を得ない。現状の金融政策の行き詰まりで、金融機関の窮状を見かねた救済策に見える。政治的な弁明効果はあろうが、金融的な効果は未知数である。趣旨と効果も不明なまま見切り発車である。果たして適切なことであろうか。
金融政策を担う日銀に求めたいことは、物価安定が基本で、経済変動や経済ショックに伴う経済・金融環境の激変に対応した金融政策である。日銀は、まず量的緩和と称するマイナス金利の是正、国債の事実上の引き受けやETF購入などの資産市場への介入を縮小し、日本経済の実情に合った正常な金融政策への回帰を目指すべきである。実物経済への介入方法は、伝統的な金融調節に徹するべきであろう。
中央銀行は、脱炭素融資を支援する前に、まず経済均衡を取り戻す経済運営・金融政策に務めることが肝要ではなかろうか。
【プロフィール】経済地域研究所代表。東北大卒。日本開発銀行を経て、日本開発銀行設備投資研究所長、新都市熱供給兼新宿熱供給代表取締役社長、教育環境研究所代表取締役社長などを歴任。