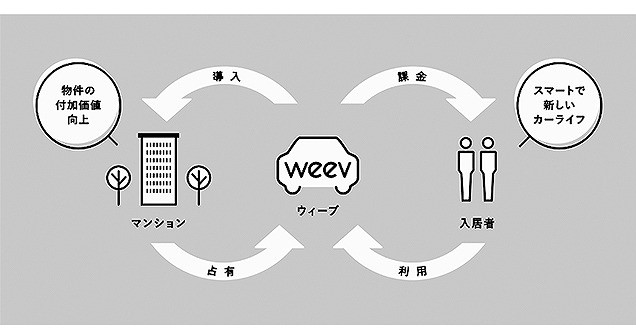【ロスアトム】
欧州から東アジアに至る北極海航路について、ロスアトム社主催のセミナーが6月に都内で開催された。
さまざまな可能性を持つこの、日ロの関係者がその将来性や利用の見通しなどを話し合った。
北極海航路――。欧州からロシアの北極海沿岸を通って東アジアに至る輸送ルートで、スエズ運河を通過する南回りルートに対して、航行時間が16~36%短縮される。ロシア側は大型原子力砕氷船団を発展させ、年間を通じて利用できるようインフラの整備に取り組んでいる。
ロシア連邦政府は、国営原子力企業「ロスアトム」を航路開発を担当する機関として任命している。6月24日にオンライン、オフラインの2形式で開かれたセミナーは、ロスアトムが策定した「2035年までの北極海航路インフラ開発計画」について同社幹部らが内容を説明。航路の発展性、効率性、安全性、また日本企業による利用の見通しなどについて、日ロ双方の関係者が協議を行った。
セミナーには、ロスアトム・モスクワ本社から同社副社長・北極海航路局長のヴャチェスラフ・ルクシャ氏、同北極開発特別代表のウラジミール・パノフ氏をはじめ、航路開発に関わる幹部らが参加。日本側からは国土交通省の幹部などの関係者約200人が参加している。

ロシア連邦政府は19年、35年までの北極海航路インフラ開発計画を認可した。計画は三つのステージ(①24年まで、②30年まで、③35年まで)に分かれている。各計画には、北極圏への大規模投資のためのインフラ開発と、積替輸送のための環境の整備が盛り込まれている。
インフラ整備に注力 原子力砕氷船を拡充
計画の実現に向けて、ロスアトムはさまざまなインフラ整備に注力している。まず、原子力砕氷船の拡充。砕氷船は氷で覆われる海域を航行する船の前方を進んで氷を砕き、航行の支援を行う。現在、最新の22220型である「The Arctic」をはじめ、5隻の原子力砕氷船を運用。ロシア側は22220型を4隻建造中であり、さらに砕氷力を増した10510型の「Lider」の建設を進めている。

ロスアトムは、原子力砕氷船を多用途救助船として利用することも重視している。特別な医療設備を備えており、急病人を収容し手当を行う。またヘリコプター発着場を備え、海難事故現場に向かい船舶の救助に当たる。
航路の安全な利用にも力を注ぐ。可能な限りの方法で病人の搬送や海難事故などへの対応に当たる。航海中の船舶で急病人などが出た場合、インマルサット(Inmarsat:通信衛星による移動体通信)、あるいは沿岸の無線局を通じて、海事救援調整センターが連絡を受け、その指令で近くの船舶かヘリコプターが病人を救助し、近くの救助船に搬送する。
海難事故が起きた場合も同様だ。国際コスパス・サーサット・プログラム(International Cospas-Sarsat Programme:衛星を利用して捜索救援活動を率先する政府間組織)などを使用し、速やかに救難を行う体制を整えている。
増加する貨物輸送 LNG輸送で倍増
北極海航路を利用する貨物輸送量は、ここ数年で大きく増えている。14年は年間約400万tだったが、ノバテク社のロシア北部ヤマル基地からのLNG輸送などにより、18年に約2000万tと前年から倍増。20年は約3300万tに増加した。輸送の増加に伴い、船舶の載貨重量も増えている。
現在、LNG輸送は欧州向けが圧倒的に多い。中国・日本・台湾・韓国向けは主に夏から秋に限られ、20年は最大で月約90万tにとどまっている。ロスアトムは、貨物輸送量は24年までに8000万tに増加するとみている。日本を含むアジア向けLNGなどの輸送が増えることへの期待も大きい。
ルクシャ氏はセミナーで日本企業の関係者に対して、「北極圏にはLNG、原油、石炭など鉱物資源が豊富にあり、(北極海航路という)新しい海上輸送の動脈は、われわれにさまざまな可能性を与えてくれるだろう」と話し掛けた。
また、「追加的な機会が生じており、われわれは一緒にそれらを利用できる。強力な砕氷船団を就航させることで、年間を通して北極海航路を安全に航海する機会を提供することができる」と述べた。
一方、国交省総合政策局海洋政策課の久保麻紀子課長は、「北極圏の資源に対する関心は高い。北極海航路を利用するには、安全性と経済的メリットが大切。いまは冬季は通れないが、定期的なコンテナ船の運航ができるかが重要な点になる。課題を一つ一つ解決していくことが、一番の近道になる」と話している。
安全な運航が可能で、経済的にも利点があれば、北極海航路で日本とロシアはウィンウィンの関係になる。今後どう進展していくか、注目する日本側関係者は多い。