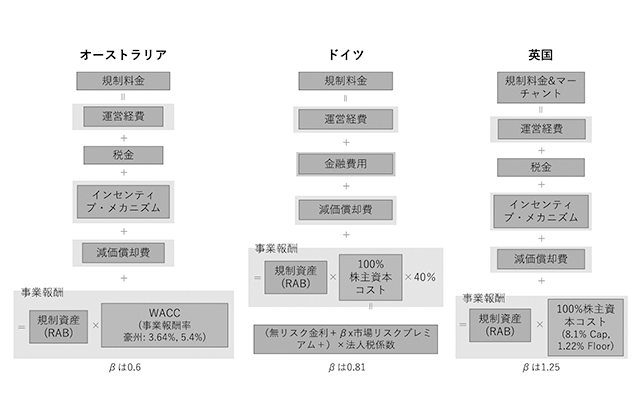【論説室の窓】竹川正記/毎日新聞 論説委員
各国のエネルギー・環境政策を揺るがしそうな第二次トランプ政権。
日本は潮目を踏まえた賢明な脱炭素対策で発言力を高めるべきだ。
①米国の石油・天然ガスプロジェクトを停滞させている政府の制限を全て撤廃、②バイデン政権下で実施された自動車の排ガス規制の強化など車産業の発展を妨げる規制を撤廃、③(米民主党の)過激な左派が掲げるグリーン・ニューディール政策に反対―。
トランプ次期米大統領の公約集「アジェンダ47」は、民主党のバイデン政権による脱炭素政策をことごとく覆す内容だ。米議会も与党・共和党が上下両院多数を占める「トリプルレッド」を追い風に、「化石燃料回帰」にまい進する構えだ。
第二次政権は、新設の国家エネルギー会議議長に石油産出地であるノースダコタ州知事を、エネルギー長官には油田開発サービス会社トップを、それぞれ起用するなど、石油・天然ガス重視の姿勢を鮮明にしている。「ドリル、ベイビー、ドリル!(掘って掘って掘りまくれ!)」と連呼するトランプ氏は、バイデン政権時代の米国産液化天然ガス(LNG)の輸出許可停止措置も打ち切る考えだ。
見逃せないのは、この政策大転換が「気候変動はでまかせだ」とするトランプ氏の心情を反映するだけでなく、通商政策や外交・安全保障政策とも密接に絡んでいることだ。

バイデン政権から大転換 ディール外交とも連動
「タリフマン(関税男)」を自称するトランプ氏は、国内産業の保護を理由に中国だけでなく、同盟国の日欧にも追加関税を課す方針を打ち出す。ただ、輸入品全てを米企業が代替供給できるわけではなく、トランプ氏が毛嫌いする貿易赤字の解消にどこまでつながるかは不透明だ。追加関税分が最終価格に転嫁されれば、米消費者の負担が増し、インフレ圧力を再燃させるリスクもある。
そこで登場するのが、お得意の「ディール」だ。日欧などに追加関税を減免する代わりに、米国製品を大量に買うように迫ることが予想される。取引額の大きい石油・天然ガスの輸出拡大はディールの柱となるだろう。米エネルギー業界を潤し、貿易赤字の削減効果も大きい。シェール革命で世界最大の産油・産ガス国となった米国の「エネルギー・ドミナンス」を強化し、外交・安全保障上の影響力を高めることにも役立つ。
日欧にとって必ずしも悪い話ではない。日本は、地政学的緊張が高まる中東への化石燃料の依存度を下げたいのが本音だ。欧州は、ウクライナ侵攻を続けるロシアへのガス依存脱却を急いでいる。いずれも大口の代替調達先は、米国をおいて他にない。「予測不可能」なトランプ流に注意すべきだが、米国産石油・ガス輸入拡大で追加関税を交わせるなら「渡りに船」(経済産業省筋)とも言える。
一方、気候変動問題に対する国際的な機運は後退しそうだ。
トランプ氏は2025年1月20日の大統領就任早々、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」からの離脱を表明する方針だ。「米国第一主義」を掲げ、何事も損得勘定が先立つ同氏にとって「産業革命以来の排出責任」を理由に50年までのカーボン・ニュートラルを押し付けられた上、途上国の脱炭素化への資金拠出まで求められる国際公約は許せない存在なのだろう。
パリ協定の枠組み自体は残るが、世界第2位の温暖化ガス排出国の退場で、地球の気温上昇を産業革命前から1・5度以内に抑えるパリ協定の目標達成は一層危うくなる。気候変動対策に熱心なバイデン政権と協調し大幅な排出削減の必要性を訴えてきた欧州は、環境外交で主導権を失うことを懸念する。
パリ協定を漂流させないよう国際協調の立て直しが迫られる局面だが、日本には発言力を高めるチャンスとも言える。再生可能エネルギーや原発の活用が停滞する日本は石炭など火力依存度が高く、G7(主要7カ国)首脳会議などで米欧の挟み撃ちに遭い、批判の矢面に立たされてきた。仮に米国でグリーン志向が強い民主党政権が続けば、米欧主導で過度に厳しい排出削減ルールを課せられ、電力の安定供給や産業競争力を脅かされる恐れがあった。
だが、今後は米国の離脱がゲームチェンジャーとなり、地球温暖化防止国際会議(COP)で、欧州の発言力は低下する。一方で最大の排出国の中国を含むグローバル・サウスの影響力が高まると見られる。脱炭素一辺倒の欧州流の上から目線の排出削減圧力は弱まり、途上国の成長にも配慮した現実的な脱炭素対策が求められそうだ。そうなれば、日本が国際的なルールづくりに積極的に関与できる好機となる。
ASEANとの連携強化 幅広い協力で利益追求を
カギとなるのは世界の成長センターで、日本と同様に火力依存度が高い東南アジア諸国との連携強化だ。岸田文雄前政権は昨年、東南アジア諸国連合(ASEAN)9カ国などと、各国の事情に応じた多様な道筋で脱炭素を目指す「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」を立ち上げた。
日本が省エネ・脱炭素技術や、人材育成、ファイナンスなどを支援するのが柱だが、これにとどまっては意味がない。官民あげて日・ASEAN双方の利益となる脱炭素のバリューチェーンを構築することが求められる。
東南アジアが持つ森林吸収源やバイオマスなどの自然資本の利活用、二酸化炭素(CO2)を貯留する地下資源の開発、アンモニアなど脱炭素燃料の製造、エネルギー転換期に必須のLNGの安定調達、電気自動車(EV)に不可欠な鉱物資源の確保など、あらゆる分野で協力を深めるべきだ。環境分野で世界の覇権を目指す中国もASEANに接近しており、日本の外交戦略が問われる。
トランプ2・0とは裏腹に、米国を含めた世界の産業界や市場が脱炭素に向かう大きな流れは変わらない。日本がASEANなどを味方に付け、気候変動対策で実効性ある処方箋を示せれば、国益と地球益の双方にかなうはずだ。