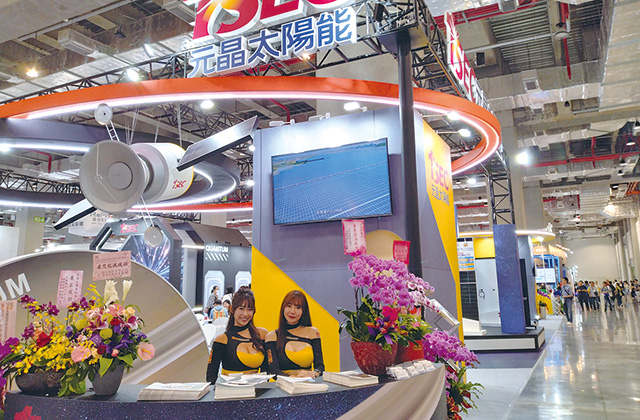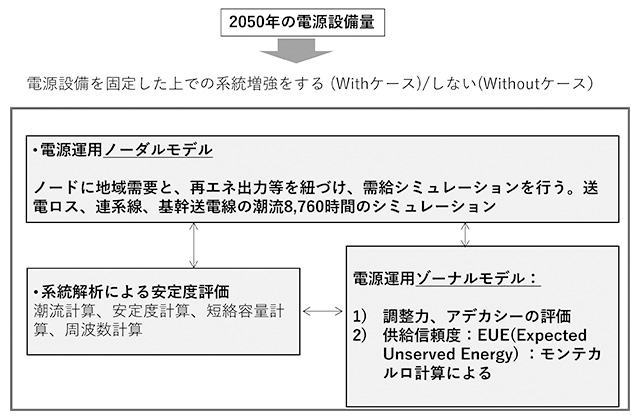【論説室の窓】井伊重之/産経新聞 客員論説委員
原子力の最大活用に前向きな姿勢を強調する新内閣の経産相。
緊迫化する国際情勢も踏まえ、安定電源を確保すべきだ。
石破茂内閣で経済産業相に就いた武藤容治氏は、今回が初入閣だが、これまでに経産副大臣や自民党の経済産業部会長、総合エネルギー戦略調査会事務局長を経験しており、エネルギー政策に通じている。家業である建材商社の経営を率いた経験もあって中小企業政策にも明るい。
初入閣した大臣の場合、就任記者会見の直前、役所の事務方が作成した想定問答を使いながら、主要政策に関するレクチャーを受ける。ただ、武藤氏の場合は「原発政策を含めてレクする必要がないほど、経産省の政策を深く理解されていた」(同省幹部)という。
その武藤氏は、就任会見で現在策定中の次期エネルギー基本計画について「原子力の最大利用は、安全という前提の中で進めていくのは当然だ」と指摘。その上で「再生可能エネルギーを最大限使いながら、原子力も安全に最大限再稼働し、さらに次世代革新炉も検討する」と述べた。これまでのエネ基で「可能な限り原発依存度を低減する」としていた原発の位置付けを転換する考えを強調した。

東京電力の柏崎刈羽原発についても「地元に寄り添い、結論を出していくのが石破政権での仕事になる」と語った。同原発を巡っては、岸田前首相は自身が退陣する直前の9月、原子力関係閣僚会議を開き、地元自治体が求める避難路整備などを関係省庁に指示。これを踏まえて武藤氏は、新潟県を含めた地元自治体から再稼働に向けた同意を取り付けることが、石破政権の課題であるとの認識を示した。
石破首相は岸田政権の経済政策を踏襲する方針を掲げており、原子力政策も同じだ。岸田氏はGX(グリーントランスフォーメーション)実行会議を主導し、脱炭素電源として再エネと並んで原発を最大限活用する方針を打ち出してきた。とくにデジタル化の進展に合わせてデータセンターや半導体工場の増設が相次ぐ中で、拡大が見込まれる電力需要に対応する必要があるとの立場を示してきた。石破政権が原発活用の方針を継続するのは当然だろう。
首相官邸の体制が不安材料 GX会議の実行力も未知数
しかし、不安材料は残る。それは石破政権を支える首相官邸の体制だ。岸田前政権では嶋田隆元経産次官が筆頭の政務秘書官として、原発政策に関する政府の実質的な司令塔として機能してきた。岸田氏が主催するGX実行会議を支えてきたのも嶋田氏だった。出身母体の経産省と連携しながら、GX実行会議で原発を最大限活用する方針を示すなど、実務を取り仕切ってきた。新たに発足した石破政権の下で今後、そのGX実行会議がどのように位置付けられるかは不明である。
石破氏は、筆頭の政務秘書官に元防衛審議官の槌道明宏氏を抜てきした。槌道氏は石破氏が防衛相時代に秘書官を務めた経験があり、旧知の間柄だ。もう一人の政務秘書官には、石破事務所で20年以上も秘書を務める女性の吉村麻央氏を起用した。さらに6人の事務秘書官には外務、財務、経産などの各省から一人ずつ派遣されたが、この事務秘書官にも防衛省出身者を一人充てた。防衛省出身の秘書官が二人体制で官邸に配置されるのは極めて異例だ。
第2次安倍晋三政権では経産省出身の今井尚哉氏が長年、政務秘書を務めて安倍氏を支えてきた。安倍政権や岸田政権に比べ、石破政権では経産省の存在感が大きく低下したのは間違いない。そうした中で国民の間に不安感が残る原発を巡り、明確な活用路線をどこまで継続できるかを注目する必要がある。
石破政権に何より求めたいのは、エネルギー安全保障の確立である。ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢のさらなる緊迫化などで、国際的にエネルギー安全保障の重要性は高まるばかりだ。資源輸入国の日本にとってエネルギーの安定調達が実現できなければ、電気・ガス料金の抑制や温室効果ガスの排出削減も達成できない。防衛政策に理解がある石破氏には、エネルギー安全保障でも明確なビジョンを打ち出してほしい。
資源開発の投資促進に課題 電力自由化の見直し不可欠
これまでの日本のエネルギー政策は、温室効果ガスの排出削減や電力自由化にばかり重点が置かれ、エネルギー安全保障に対する視座が欠けていた。岸田政権は脱炭素電源としての原発の優位性に注目したが、石破政権はその視点をさらに高め、エネルギー安全保障をエネルギー政策の基本に据える必要がある。
その点で新内閣の発足直後に広島県で開催された「LNG(液化天然ガス)産消会議」は、大きな成果を挙げた。会議に参加したイタリアとの間で、LNGの安定確保について覚え書きを交わしたからだ。同国の炭化水素公社(ENI)は、カタールと新規のLNG契約を結ぶなど関係は親密だ。我が国ではJERAが2021年にカタールとの長期契約を更新せず、同国との関係が冷え込んでいるが、ENIを通じて新たなLNG調達の道が開かれた。
日本の場合、海外からの資源調達は豪州に大きく依存している。日本に輸入される発電用石炭の7割、LNGも4割を豪州から輸入している。日本もJOGMEC(エネルギー・金属鉱物資源機構)を通じて海外鉱山の開発投資ができる仕組みを導入したが、実際に日本向け輸入を担う民間の電力・ガス会社との関係を緊密にすることで実効性を担保する必要がある。
エネルギー安全保障の精度を高めるには、電力自由化の見直しも不可欠だ。国内の電源不足に対応するための予備的電源の最初の入札は不調に終わった。政府は電力自由化の枠組みの中で電源の安定確保を目指す構えだが、自由化と安定電源の確保は半ば相反する。自由化の進展で大手電力は、運転コストがかかる老朽発電所を相次いで廃止しており、電源の新規投資には消極的だ。新たなエネ基では原発の新設解禁も検討されているが、安定電源の確保は自由化とは異なる枠組みで用意すべきだ。