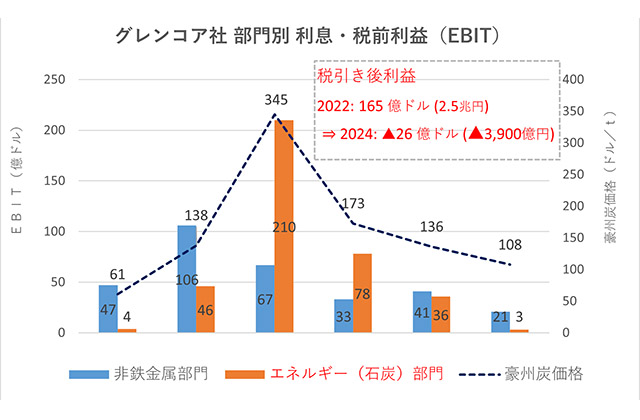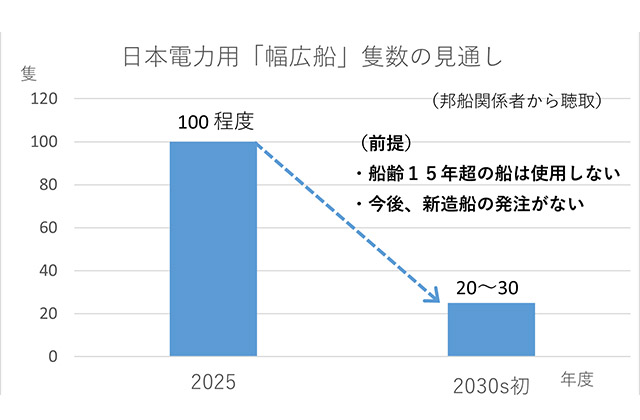【リレーコラム】平 慎次/ボストンコンサルティンググループマネージング・ディレクター&パートナー
プライベートを含めて大阪・関西万博を数回訪れることができた。各国の建築物や大屋根リング、また、25年後の将来世界の体験などを純粋に楽しんだ。自然との調和を重視しつつ、AI・ロボットなどの技術進化と共生する生活は、今取り組んでいるGXとDXの進みが結実する世界を示唆していた。
激動の25年を歩んだ電力業界一方で過去に目を向けると、個人的には約25年の間、電力・エネルギー業界に携わってきた。新卒で東京電力に入社した当時、非常用電源の建替工事で漏電を起こしてしまい、深夜に超高圧変電所がブラックアウトして何も役に立たなかった情けない思い出がある。
この間、業界では多くの変化が起きた。原子力データ改ざんなどの不祥事、新潟県中越沖地震などの災害、東日本大震災と福島原子力発電事故、小売り全面自由化・送配電法的分離、再生可能エネルギーの大量導入、脱炭素化・サステナビリティの潮流、そしてAI・データセンターによる電力需要増など、なんと大きなイベントが起きる業界かと思う。これに加えて、国際情勢・地政学の影響、燃料ボラティリティリスク、安全保障などにも配慮が必要になっている。
インフラ・公益事業で安定と思われがちだが、電力・エネルギー会社の経営マネジメントは難度が高いと感じる。現場での設備の保守・メンテナンスや災害時の緊急対応もこなしながら、不透明な事業環境下で暗中模索しつつも経営をかじ取りしなければならない。2000年前後には、世界のインフラ・公益事業会社の時価総額ランキングで東京電力がトップ10に入っていたと記憶するが、今年にはトップ30にも日本企業の名前が見当たらない。時価総額で全てを語るつもりはないが、経営力に差が出たのは否めない。
未来を見ると、今後の電力需要増に対応するため、電源開発の拡大をはじめとする令和のインフラ大構築時代に入る。一方で、ヒト・モノ・カネが足りない社会構造上のボトルネックにも直面している。高齢化や労働人口減少による技能者不足、地政学・インフレが相まったサプライチェーンの混乱、企業の財務体力の弱体化もあり、高度経済成長期のインフラ構築よりも立ちはだかる壁は高い。本当にできるのかと疑念もわくだろう。
これらのチャレンジングな状況をポジティブに捉えると、エネルギー会社にとっては活躍と成長のチャンスとも言える。万博で描かれたような将来を実現するために、そして万博の成功に続くように、日本企業の経営力向上に少しでも貢献すべく志高く取り組みたい。

※次回は、GX推進機構の重竹尚基さんです。