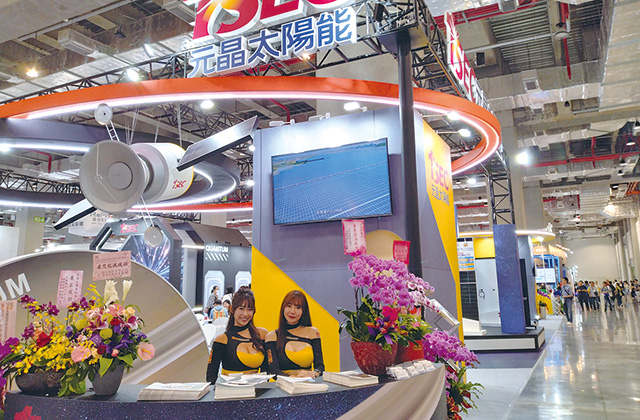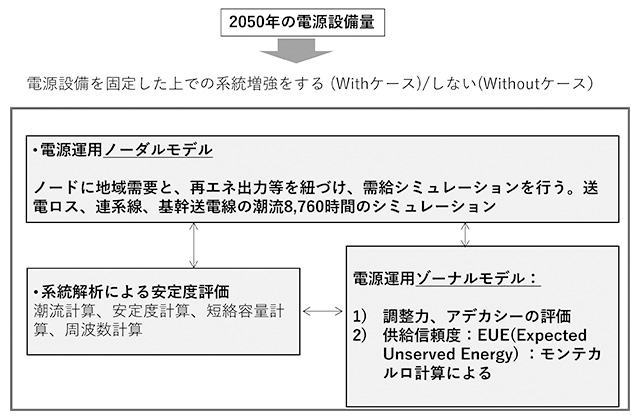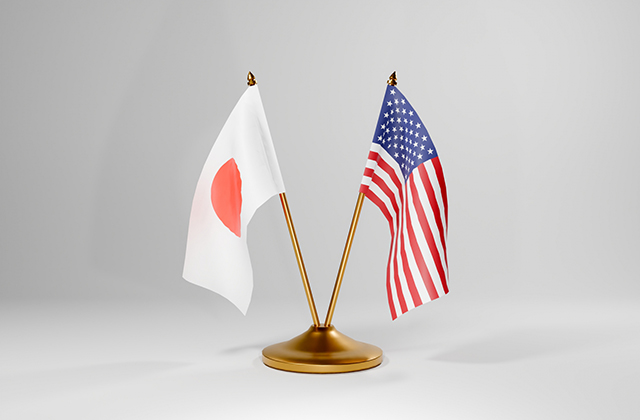【今そこにある危機】峯村健司/キヤノングローバル戦略研究所主任研究員
米大統領選はドナルド・トランプ前大統領vsカマラ・ハリス副大統領という構図となった。ハリス氏にこれといった思想や信念は感じられない。なぜ彼女が副大統領にまで上り詰めたかといえば、バイデン政権のDEI(多様性・公平性・包括性)政策の影響が大きい。むしろ能力よりもDEIを優先していた感さえある。
ハリスを阻む「正統性」問題 トランプに対する誤解
バイデン・ハリスはワンチームだと思われがちだが、ハリス氏の政策はバイデンよりもリベラルだ。加えて、政策が極端な方向に傾きかねないリスクを抱えている。
日本ではあまり見聞きしないが、強調したいのはハリス氏の大統領候補としての「正統性」を巡る問題だ。バイデン氏が7月21日に撤退を表明してから、民主党では候補者を決める予備選が実施されなかった。バイデン氏は現職大統領といえども、予備選という民主的な手続きを経て民主党の候補者となった。だがハリス氏の擁立は、バラク・オバマ元大統領やナンシー・ペロシ元下院議長 、ヒラリー・クリントン元国務長官ら、党内の重鎮の影響で非民主的に決定した。今後の論戦で共和党側がこのプロセスを追及する可能性がある。
日米関係への影響は……
候補者としての正統性の欠如は、「ハリス政権」の弱点になりかねない。自らを大統領候補に押し上げた党内左派に頭が上がらず、より政策が左傾化する可能性がある。一方で、彼女の唯一の強みはバイデン政権の副大統領だったという点だ。だからバイデン路線の大きな変更も許されない。ハリス氏が抱えるジレンマは、国内の経済政策や外交・安全保障政策にとって悪影響となりかねない。
外交・安全保障は「結果責任」だ。この点、バイデン政権の中東外交は大失敗だった。トランプ政権が築いたサウジアラビアとの良好な関係を破壊し、中国が付け入る隙を与えてしまった。だからといって、イラン封じ込めもできていない。大きな戦略が見えない外交を展開していた。
外交は常に最悪の事態を想定する必要があるが、最悪の事態を避けるために妥協を重ねてはならない。例えば、対ロシア外交上の最悪の事態は核戦争への突入だが、それを避けるためにウクライナの領土を割譲することは許されない。しかし、民主党のオバマ政権ではクリミア半島の併合を許し、バイデン政権ではウクライナ侵略を防げなかった。
いま民主党内では、オバマ政権で大統領補佐官を務めたスーザン・ライス氏の影響力が増しているという。彼女の補佐官 時代、私は朝日新聞の米国総局員として取材を重ねたが、彼女は典型的な親中派で、日本や台湾にあまり関心がない。米国の抑止力を弱めた張本人と言っていい。彼女が政権中枢に入り込めば東アジアの安全保障上、プラスに働かないだろう。
結果責任でいえば、トランプ政権一期目の外交は大成功だった。世界で国家間同士の大きな戦争は起きなかった。
ウクライナ対応を巡っては「トランプはロシアに甘い」という言説を耳にするが、それは正しくない。トランプ氏の外交・安全保障政策の根底にあるのは「力による平和」だ。トランプ氏が嫌っているのは、だらだらとウクライナ戦争が続くことで、突如支援を打ち切りロシア有利で停戦を行う可能性は低い。むしろより早く戦争を終結させるために多くの武器を短期集中的に供与し、ウクライナが優位性を得たタイミグで停戦する狙いだろう。今夏以降、ウクライナがロシア領土に越境攻撃を実施しているが、トランプ氏はこの動きに反対してない。
とはいえ、トランプ外交が一期目のようにうまくいくかは不透明だ。というのも、一期目はトランプ氏にまだ政治経験がなく、ハーバート・マクマスター大統領補佐官(国家安全保障担当)やマット・ポッティンジャー大統領副補佐官(同)という共和党主流派のプロフェッショナルが、外交のグランドデザインを描いていた。一期目以降はトランプ氏に政治経験や人脈が築かれ、二期目では彼らの影響力が低下する可能性がある。よりトランプ色が出て「日米同盟軽視」となった場合、蜜月関係を築いた安倍晋三元首相のようなリーダーは日本にいない。
両極端なエネルギー政策 議会選挙も要注目
大統領選と同日に行われる連邦議会選にも要注目だ。仮にハリス政権が誕生したとしても、議会で共和党が過半数を得ると政権運営で行き詰まる可能性が高い。一方、トランプ政権は財政負担となっている電気自動車(EV)購入の税額控除の撤回などインフレ抑制法(IRA)の部分修正を狙っているが、実現には議会での法改正が必要だ。議会を民主党が握れば、それは不可能となる。
バイデン政権下では日本の自動車メーカーなどを中心に、米国のEV工場や車載電池工場への投資が加速した。ハリス氏のエネルギー政策はバイデン路線を一段と加速させたもので、ほかにも石油・ガス企業への補助金の撤廃、緑の気候基金(GCF)に対する30億ドルの拠出、連邦政府の車両のEV化などを打ち出している。
もしトランプ政権になれば、発電所と自動車の排ガス規制が撤廃となるだろう。蓄電池導入に対する補助金もばっさりカットする可能性が高い。もちろん、パリ協定から離脱し、GCFへの資金拠出も止まるはずだ。日本企業は戦略の見直しが求められる。
残念ながら、日本企業は総じて地政学など海外要因に対するリテラシーが低い。対米関係でいえば、しっかりとしたロビイング活動を行う企業が少なく、同盟国という安心感もあり政治的に鈍感だ。しかし、大統領選だけでなく連邦議会選挙にも目配りしながら、機動的な対応を求められる時代になった。米国の内政を含めた地政学リスクを認識するため、インテリジェンス能力を高める必要がある。
みねむら・けんじ 朝日新聞社で中国総局員、米国総局員、編集委員などを務める。LINEの個人情報管理問題で新聞協会賞、中国軍の空母建造計画スクープでボーン・上田国際記者記念賞を受賞。専門は米中関係。