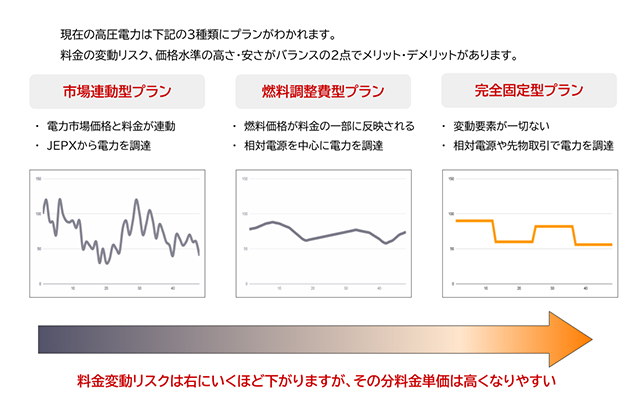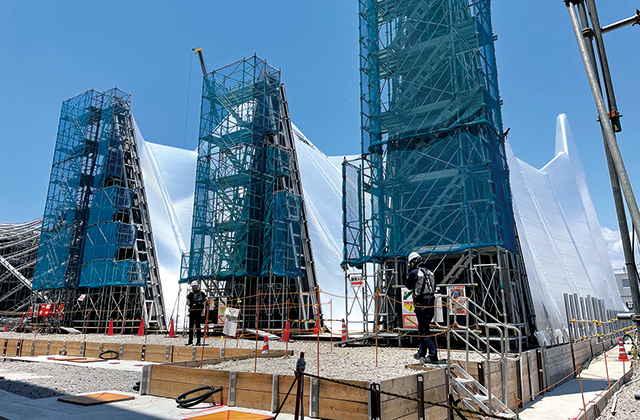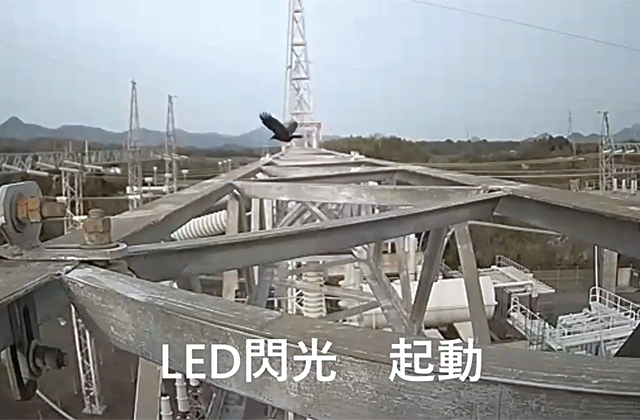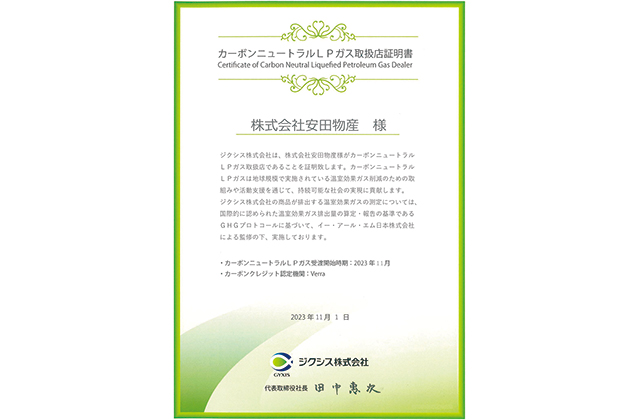【脱炭素時代の経済評論 Vol.04】関口博之 /経済ジャーナリスト
パリ五輪の聖火リレーがフランス国内で繰り広げられている。7月26日には開会式で聖火台に点灯される。この聖火トーチに使われている燃料は「バイオプロパン」だ。環境重視の大会運営を掲げる組織委員会からの注文だという。日本では馴染みのないこの「バイオプロパン」とは?
これは石油など化石燃料によらないプロパンガスのことで、欧米では商業生産されている。植物油や食用油、食物の残りかす、動物性脂肪など再生可能な資源から作られる。組成や性質は従来のLPガスと変わらないため、同様に使えるという。

なぜ日本では目にしないのか。LPガスの輸入生産を行う元売事業者で作る日本LPガス協会によれば、特に欧州ではバイオディーゼル燃料が広く利用されていて、これは主に植物油から作られるが、その際の副産物としてプロパンが生成され、それが「バイオプロパン」として流通しているという。本来の目的物ではないが、副次的に活用されているわけだ。フィンランドのネステ、オランダのSHVエナジー、米国のUGIなどエネルギー大手も手掛けていることで生産・流通も増えている。
残念ながら日本国内ではほとんど製造されていない。植物油を取る大豆などを栽培する広大な土地がない日本には不向きだ。
LPガスの脱炭素化を目指す「日本グリーンLPガス推進協議会」によれば、バイオ原料を元に同様なガスを作る試みとしては、牛のふんを原料にする古河電工や稲わらを発酵させるクボタなどの研究があるがまだ実験段階だ。一方では北九州市立大学や、産業技術総合研究所を中心としたグループでは、CO2と水素を合成し中間体のDME(ジメチルエーテル)を作り、そこから化学的にプロパンなどを生成する研究も始まっている。ただ北九州市立大でもようやく大型実験装置が立ち上がるところだという。
日本LPガス協会では2030年ごろまでに1日当たり100㎏生産の実証プラントを建設し、40年代に同10~100tの商用プラント稼働というロードマップを描くが、まだ現実味は乏しい。都市ガスの原料であるLNGの代替として開発が行われているe―メタンと比べても「まだ周回遅れの状態」(業界関係者)だという。
バイオプロパンが海外ですでに商用化されているのだとすれば、それを輸入するという選択肢もある。再生可能な資源を元に製造されたものであれば、中間体のDMEの形での輸入も手段だという。
現在のLPガスは、都市ガス導管のないエリアをほぼカバーしている。災害時には家庭のガスボンベが軒下備蓄にもなり、いわば最後のとりでともされる。こうした役割を考えてもLPガス(プロパンガス)の脱炭素化は避けて通れない課題だ。国も責任を持って道筋を描くべきだ。
ちなみに冒頭で触れたパリ五輪の聖火トーチ、この燃焼部を製造したのは新富士バーナーという愛知県豊川市のメーカーだ。この取材を縁にバイオプロパンなるものを知った。日本のものづくりと欧州の脱炭素燃料が五輪の祭典に彩りを添えると考えると、何とも心躍る気がする。
・【脱炭素時代の経済評論 Vol.01】ブルーカーボンとバイオ炭 熱海市の生きた教材から学ぶ
・【脱炭素時代の経済評論 Vol.02】国内初の水素商用供給 「晴海フラッグ」で開始
・【脱炭素時代の経済評論 Vol.03】エネルギー環境分野の技術革新 早期に成果を刈り取り再投資へ