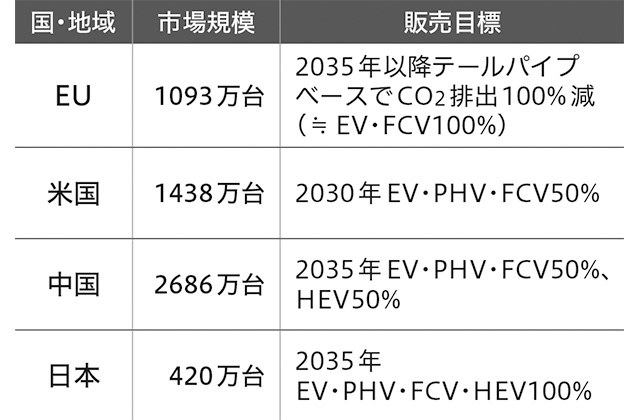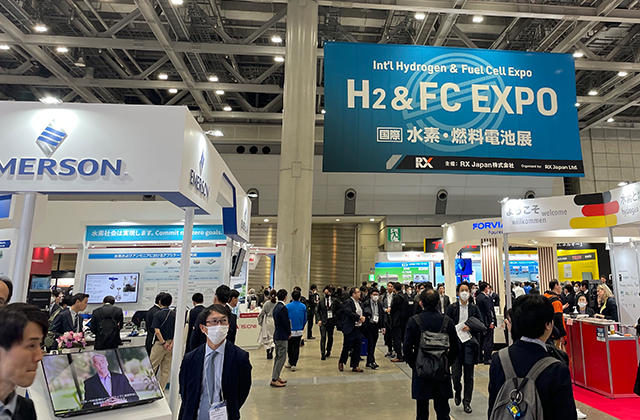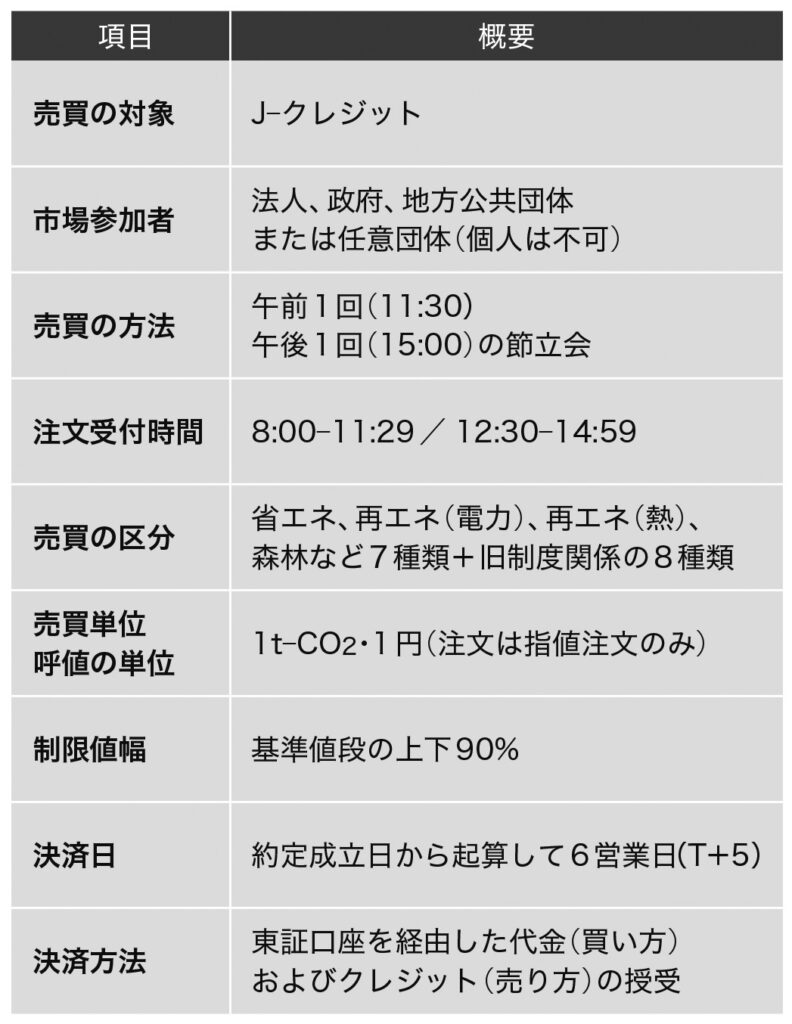NEWS 01:JERAが資本増強を検討 5兆円投資へ上場も選択肢
「第三者割当増資、既存株主による増資、それからIPO(新規株式公開)など、どのタイミングでどの選択をするのが一番いいのか。検討のさなかだ」JERAの奥田久栄社長は、5月16日に行った「2035年ビジョンの実現に向けた成長戦略」の発表会見で、こんな見解を示した。
 会見する可児行夫会長(左)と奥田社長
会見する可児行夫会長(左)と奥田社長
この戦略では、LNG、再生可能エネルギー、水素アンモニアの3分野を「戦略的事業領域」に位置付けるとともに、35年までに累計5兆円(各分野ごとに1~2兆円)を投じ、25年度見通しで2000億円の連結最終利益を3500億円へと引き上げる計画だ。
具体的には、LNG取扱量で現行の年間3500万tを10年後も維持しながら、再エネの開発容量を現在の500万kWから、洋上風力発電事業の世界展開などで4倍の2000万kWに拡大。水素アンモニアについては、生産から輸送、貯蔵、利用までのバリューチェーンを構築する先駆者として、年間700万t程度(アンモニア換算)の取扱量を目指していく。
総額5兆円の投資を実現するためにも、財務体質の強化は不可欠。奥田氏は会見で「自己資本を増強する方向で検討を進めていく」と述べた上で、前述のような複数の方策に言及した。果たして増資や上場に踏み切るのか。火力発電事業の最大手の動向に業界の関心が集まる。
NEWS 02:既存石炭火力削減で足踏み G7で強化方針示せず
4月28~30日にイタリア・トリノで開かれたG7(主要7カ国)気候・エネルギー・環境相会合では、昨年の温暖化防止国際会議・COP28でのグローバルストックテイク(世界全体の進ちょく評価)などの成果を踏まえ、どのような内容が示されるのかが注目された。ただ、既存の石炭火力のフェーズアウトについては、合意文書でこれまでの方針以上に踏み込むことができなかった。
欧米はここ数年、G7で排出削減対策が講じられていない石炭火力フェーズアウトの具体的な年限を打ち出すことを模索しており、COP28でもフェーズダウン加速の必要性が示された。では今回の合意文書での書きぶりはというと、「各国のネットゼロの道筋に沿って2030年代前半、または気温上昇を1・5℃に抑えることを射程に入れ続けることと整合的なタイムライン」でフェーズアウトするなどと記載した。30年代前半との時限を示しつつも、1・5℃目標を目指す、という判断基準も並列。具体的に規制が強化されておらず、日本からすればウェルカムな内容といえる。
欧米がロシア・ウクライナ戦争以降、脱炭素とエネルギー安全保障の両立というジレンマを抱え続ける実情が、改めて浮き彫りになったと言える。
他方、「この観点で次期NDC(国別削減目標)に情報を提供し、実施する政策の一環として具体的かつ適時の取り組みを行う」との一文も。新たなNDCは来年2月までの提出が求められ、ターゲットは35年が推奨されており、今後政府は議論に着手する。40年に向けたGX(グリーントランスフォーメーション)の新たな国家戦略、そして第7次エネルギー基本計画の議論と並行し、NDCではどのような内容が示されるのか。
NEWS 03:液石法省令改正で指針案 利益供与行為は原則NGに
LPガスの取引適正化に向け、液化石油ガス法の改正省令が4月2日に公布された。その柱は、①過大な営業行為の制限、②三部料金制の徹底、③LPガス料金などの情報提供―の三つ。このうち、①と③が7月2日に、②については来年4月2日に施行される。
資源エネルギー庁は、違反に対し罰則も辞さない構えだが、基準があいまいなままでは抜け駆け行為により制度改正がなし崩しになりかねない。それを回避しようと、5月20日の総合資源エネルギー調査会(経済産業相の諮問機関)液化石油ガス流通ワーキンググループ(座長=内山隆・青山学院大学教授)では、取引適正化ガイドラインの改正案を含めた実効性確保策が示された。
例えば、改正省令では過大な営業行為の制限について「正常な商慣習を超えた利益を供与してはならない」としているが、何を持って「過大な利益」とするかの線引きは難しい。これについてガイドラインでは、利益供与に「設備の無償貸与や安値提供、フリーメンテナンスなどの物品・サービスの提供」、「LPガスボンベ置き場の賃借料を名目とする金銭的な利益の提供」を含むとし、健全な競争を阻害し一般消費者に不利益をもたらす可能性を踏まえれば過大かどうかにかかわらず、「一切行わない方向で取り組むことが望ましい」と明記する方針だ。
同日の会合では、5月10日までにエネ庁の通報フォームに670件もの情報提供があり、改正省令公布後も駆け込み的営業行為が続いている実態が明かされた。業界関係者の一人は、「省令改正は改革の第一歩に過ぎない」との見方。不動産業界など利害関係が複雑に絡み合うだけに、業界、そして監督官庁の本気度が問われている。
NEWS 04:自民にe―メタン議連発足 導入促進制度構築など提言
自民党の有志議員が4月18日に発足させた「GXにおける天然ガスの高度利用とe―メタン促進に関する議員連盟」(e―メタン議連、会長=梶山弘志幹事長代行)。5月17日の会合で、政府が策定する経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)を見据え、移行期における天然ガスの利用の推進とe―メタン実装に向けた環境整備を求める提言をまとめた。
 議連の初会合であいさつする梶山会長
議連の初会合であいさつする梶山会長
提言は、まず移行期の天然ガス利用について、①化石燃料の中で最もCO2排出量の少ない天然ガスの戦略的な利用、②LNGの安定調達や継続的な活用に向けた取り組み、③カーボンニュートラル(CN)化に向けた天然ガスへの燃料転換―の推進を掲げた。
e―メタン実装への環境整備では、①技術開発によるコスト低減・生産技術の確立、②LNGとの価格差に留意した導入促進制度の構築、③e―メタン利用時のCO2排出に関わるカウントルールの整理―を明記。中でも、値差支援などを図る導入促進制度については、民間事業者の投資の予見性を確保することが必要とした上で、今夏までに固めるよう求めている。
都市ガス産業では、熱利用分野のCNへの円滑な移行を目指し、まずは足元で天然ガスの高度利用を進めながら、将来的には既存のインフラ設備や消費機器を利用できるe―メタンに原料をシフトしていく構えだ。