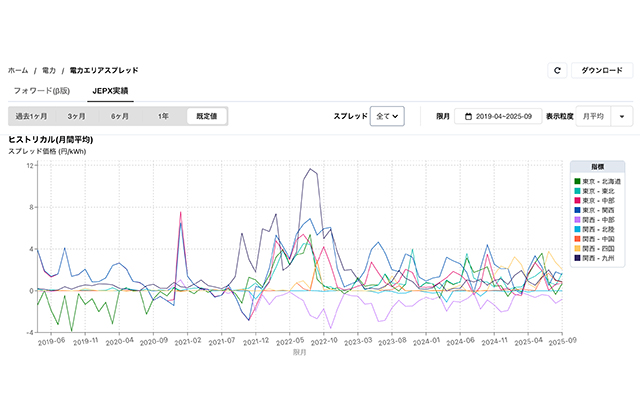【エネルギービジネスのリーダー達】田口昂哉/ヘリカルフュージョン代表取締役CEO
安定的かつ連続運転に適したヘリカル方式の核融合発電で、2030年代の実用発電を目指す。
金融畑出身のノウハウを生かし、世界初の商用化に挑戦している。

「現在の技術力で実用化に至る唯一の道はヘリカル方式だ」
核融合スタートアップのヘリカルフュージョン創業者で、代表取締役CEO(最高経営責任者)の田口昂哉氏はこう意気込む。2021年10月に設立された同社は次世代エネルギーとして期待される核融合発電のヘリカル方式で30年代の実用発電を目標に掲げており、日本から世界初の商用化を狙っている。
研究者との出会い転機に ヘリカルの優位性に着目
ヘリカル方式の核融合発電は、らせん状の磁場でプラズマを閉じ込める仕組み。安定かつ連続運転に適しているのが強みだ。このほかトカマクやレーザーなど多様な方式があり、商用化に向けた動きが各国で加速している。これまで世界的に主流と目されてきたトカマク方式は磁場と電流を併用しプラズマを閉じ込める仕組みで、一部パラメータで好成績をあげてきたが、急激なプラズマ崩壊(ディスラプション)のリスクを抱えている。田口氏は「定常運転、正味発電、保守性という商用炉に不可欠な三要件を満たしつつ、経済性を確保できる」と、ヘリカル方式に目を付けた理由を明かす。
同氏は京都大学大学院文学研究科を卒業後、みずほ銀行や国際協力銀行、PwCアドバイザリー、金融系スタートアップにCOO(最高執行責任者)として参画するなど核融合とは接点のない領域でキャリアを積んでいた。では、なぜ核融合分野に足を踏み入れたのか。それは、研究者の宮澤順一氏と後藤拓也氏から起業相談を受けたことがきっかけだ。二人は核融合科学研究所などで長年ヘリカル方式を含む核融合炉の研究に取り組み、20年ごろにはヘリカル型核融合炉の基礎研究が完了したと判断。アカデミアを離れ、商用化に向け起業する道を探っていた。しかし、起業のノウハウを持ち合わせておらず、共通の知人を通じて田口氏に声がかかった。太陽と同じ原理でエネルギーを生み出す核融合の革新性に魅力を感じた田口氏は、「歴史の転換点に立ち会ったと実感した。当然、核融合の業務経験はなかったし、自分以上に適任はいるかとも考えたが、ここで誰も動かず頓挫するのは惜しい」と考え、共同創業を決断した。
創業当初から手掛ける技術はヘリカル方式と決まっていた。宮澤氏と後藤氏は長年の研究成果から商用炉に最も適していると判断していたが、その考えを田口氏に押し付けることはなく、科学的根拠に基づいて各方式の特性を説明したという。田口氏にとって核融合の知識を習得するには大きな労力を要したが、理解が深まるにつれ、自らもヘリカル方式の優位性を確信した。
創業後は、金融業界やスタートアップで培った経験が武器となった。資金調達のノウハウや培った人脈が、初期の立ち上げを後押しした。田口氏は「会社経営の土地勘があった分、最初の動き出しに役立った。ファイナンスからコンサルまで、これまでの経験がすべて生きた」と振り返る。こうした強みを背景に、創業から約4年でSBIインベストメントなどから融資を含め約23億円を新規調達。累計調達額は、文部科学省の補助金を含め52億円に達した。
7月には従来の基幹計画を更新し、核融合の実用発電を30年代に実現するための新計画「Helix Program」を策定した。商用発電炉「Helix KANATA」を30年代に稼働させることを目標に掲げ、着工までの間に統合実証装置「Helix HARUKA」で各種試験を進める方針だ。
同社はすでに核融合研で確立されたプラズマ物理と炉設計のノウハウを受け継いでおり、実用発電に向けた課題は残り二つ。一つは核融合で生じるエネルギーを熱として取り出す「ブランケット」の開発。もう一つは、従来の低温超伝導コイルより強力な磁場を発生できる「高温超伝導コイル」の開発だ。これにより、コンパクトで高性能な発電炉を実現する。いずれも大規模な投資となるため、投資家の存在や、パートナー企業との連携は不可欠だ。「従来の基幹計画は第三者には伝わりづらい内容だったが、戦略名を掲げ、開発状況を明確にすることで理解されやすい形にした」と、新計画には協業体制の拡大を狙う意図も込められていることを語る。
発電炉は全て自社設計 新たな産業創出狙う
同社の強みは次世代技術を扱うという先進性だけではない。発電炉の設計を全て自社で行っている点にもある。「部品や要素技術にとどまらず、最終的に発電炉そのものを日本でしか作れない状態にしなければならない」と田口氏は強調する。産業の果実を得るにはサプライチェーンの上流を抑えることが不可欠という考えからだ。新たな産業の創出で日本を活気づけたいという強い思いが挑戦を支えている。