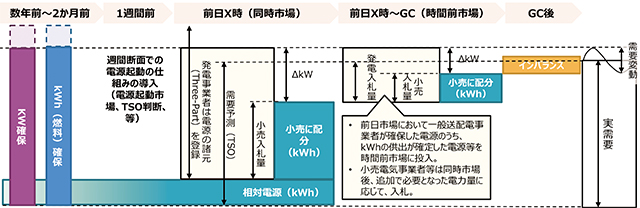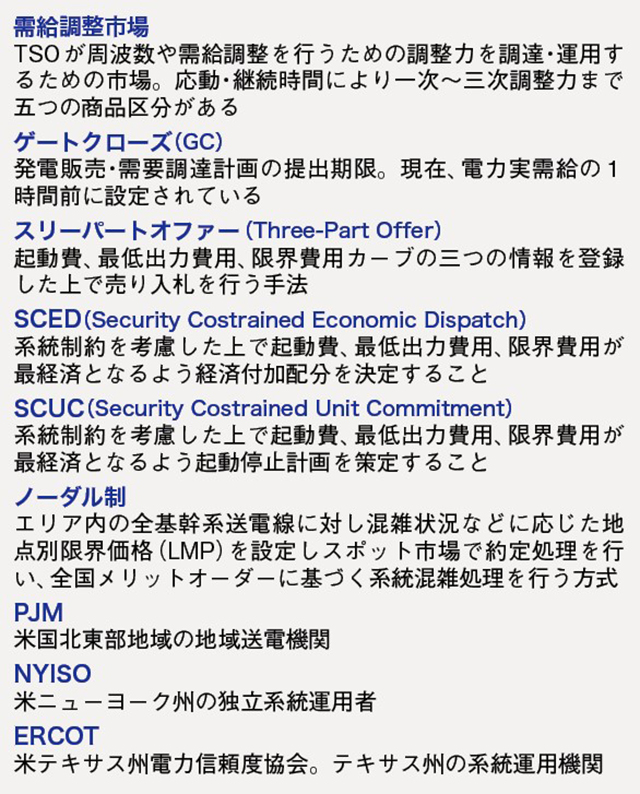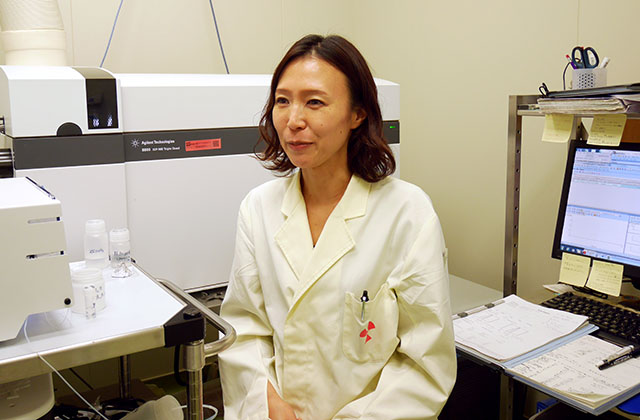【静岡ガス】
静岡ガスは昨年9月、低圧ユーザーのニーズに応える新電気料金プランを打ち出した。今冬から「節約応援プラン」を本格的に展開し、同社ブランド「SHIZGASでんき」の販売に注力する。
節約応援プランは、ユーザーの電力の使用実態に合わせて基本料金を変動させる。一般的な電気料金は、基本料金、電気の使用量に応じた従量料金、燃料費調整額、FITの額で構成されており、基本料金は契約する電力のアンペアに応じて決まっている。

このアンペアは年間のピーク電力使用量からはじき出される。少人数の世帯だと20~30A、世帯人数が多かったり電力使用量が多いユーザーは40~60Aで契約することが一般的だ。静岡ガスのプランは、この契約アンペアを下げて、料金を減らそうとするユーザーが増えたことに対応した。
「家族人数の多かった世帯で、若者の県外移住などによって世帯人数が減少傾向にあった。これまでは契約アンペアをそのままにしているケースが多数あった。一方、昨今の資源価格の高騰や電気値上げなどで、従来以上に電気料金にシビアなお客さまが増えている。そうした中で、アンペアを見直すニーズが出てきた」(営業本部戦略推進部営業企画担当の吉田公春さん)
需要家の使用実態を把握 対面営業の強み生かす
契約アンペアを下げて料金を抑えるプランはいたってシンプルだが、ユーザーの電気使用実態を把握して、アンペアの最適解を見つけ出すのは手間の掛かる作業だ。それでも同プランを手掛ける意義は何か。「これまでガス事業を含め対面を中心に営業を進めてきた当社ならではの強みを生かしたいと考えている。お客さまと接する中で、実際の電力使用実態を把握し、契約アンペアをどれくらい下げれば最適な料金プランになるのか、お客さまと相談しながら決めていく。結果的に契約アンペアの見直しを後押し、節約をサポートすることで『SHIZGASでんき』を選んでもらいたい」(同)
ユーザーと接してさまざまなことが分かった。例えば、省エネ家電が浸透する中、それに伴い、電力消費量も減少傾向にあること。普段からどのような機器を使っているかを把握しておくことも、ユーザーの電力使用実態を調べる上では重要なことだという。
また大手電力各社が整備してきたスマートメーターによって「30分値」を取得できるようになったこともサービスを進化させている。電力消費実態を把握する上で重要なデータとなっており、そのデータは同社が独自で開発したアプリとも連携させている。ユーザー自身もスマホの端末から使用量を把握でき、ユーザー自らも節電や節約の意識を高めるようなシステムを構築した。
単純に単価を下げるような販売では、事業環境によっては事業者自らも首を絞めることになる。それでは高い公益性が求められる事業者として持続可能な事業を営むことは不可能だ。静ガスはユーザーと事業者が互いにウィンウィンになる手法の導入を目指していく。