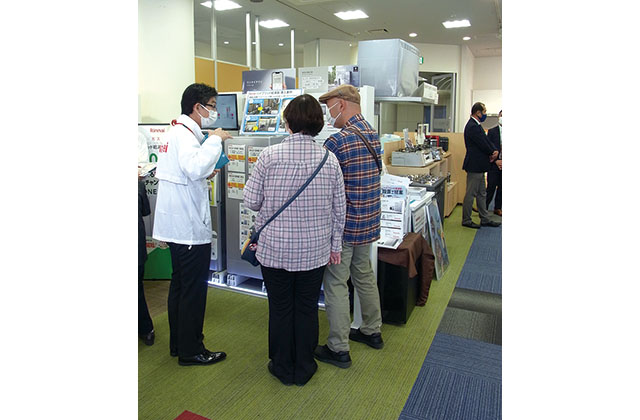【エネルギー企業と食】伊丹産業×米
伊丹産業は1948年、食糧公団の米穀輸送・保管倉庫業、主要食糧の集荷・製粉業を手掛けたことに始まる。49年からは薪炭や練炭、58年からは現在主力のLPガスといったエネルギーを手掛けるようになった。これらは、米輸送で培った輸送のノウハウが生かせるため目をつけたという。
その後、しばらくはエネルギー事業に注力するが、93年に合意したウルグアイ・ラウンドによるミニマム・アクセス(最低限輸入義務)によって潮目が変わった。94年に新食糧法が可決し、それまでの生産者から国が買い上げて売るという基本方針を改め、農家や流通業者だけでなく、一定の条件を満たせば誰でも米の取り扱いができるようになった。
このタイミングで、独自ブランド「伊丹米」の販売を開始。再び米穀事業に注力することになる。これは創業者・北嶋政次氏の悲願でもあったとのことだ。発売直後の伊丹米は、統一ブランドで独自に6銘柄を販売した。「産地をアピールしたパッケージが消費者の心をつかんだ。流通面でも関西スーパーマーケットと提携することで販路が広まり一気に拡大していった」。米穀事業部西日本支店の藤木敏弘支店長はこう振り返る。現在では全社売上高の15%を支える重要事業になっている。

その一方で、日本国内は人口減少の一途をたどっており、米の消費量も減少している。この状態に歯止めをかけ、需要を掘り起こすことも大切だ。一時期、米を食べると太るなどといった話が広まることがあった。しかし、コロナ禍を経て身体のことを考える機会が増え、インフルエンサーなどが訴えてくれたことで米の存在を見直す考えが広まりつつあるという。
伊丹産業は米普及の啓蒙活動にも注力している。その一つが10月に行われたパ・リーグクライマックスシリーズファイナルステージ第1戦のゲームスポンサーだ。「伊丹産業Day」と銘打ち、入場ゲートや外野の看板に表示された。入場者には先着1万5000人に新潟県魚沼産、石川県・兵庫県産のコシヒカリ300gを無料配布した。「球団からもお客さまからも大変好評だった。イベント活動には積極的に取り組んでいく」と藤木氏は意気込む。
今後は米産地との取り組みを増やす。SDGsや環境配慮への関心が高まる中、米生産にも対応が求められているためだ。温暖化によって気象条件も変わりつつある。生産者は毎年減っている。こうした課題にも、創業者の米へのこだわりを継承し取り組んでいく。