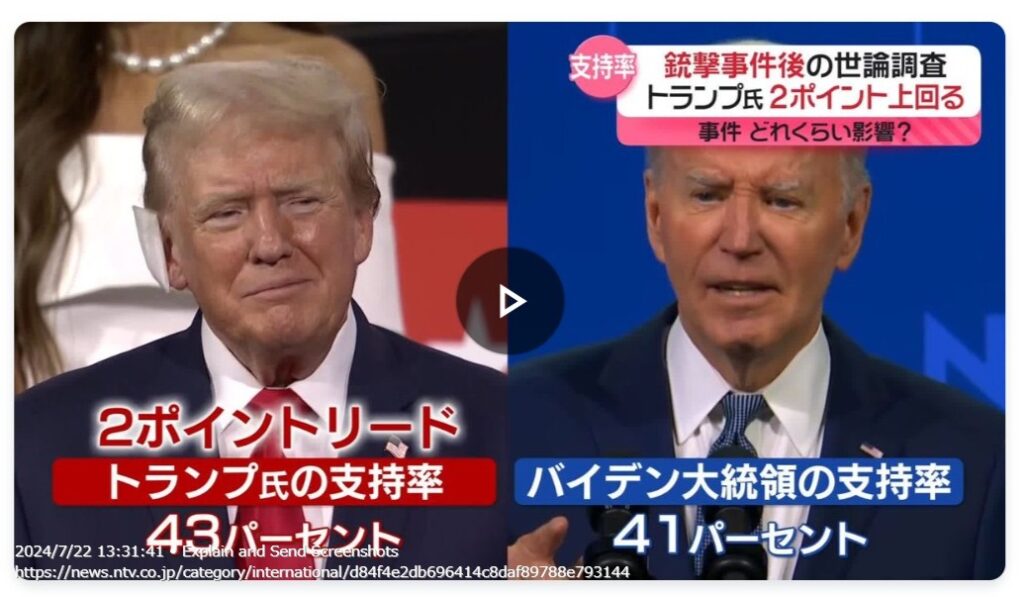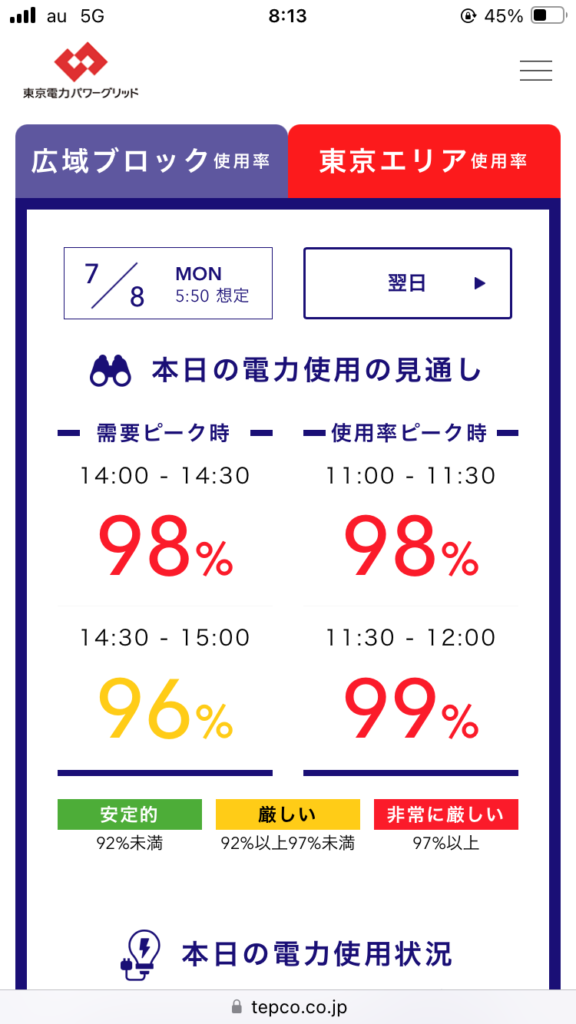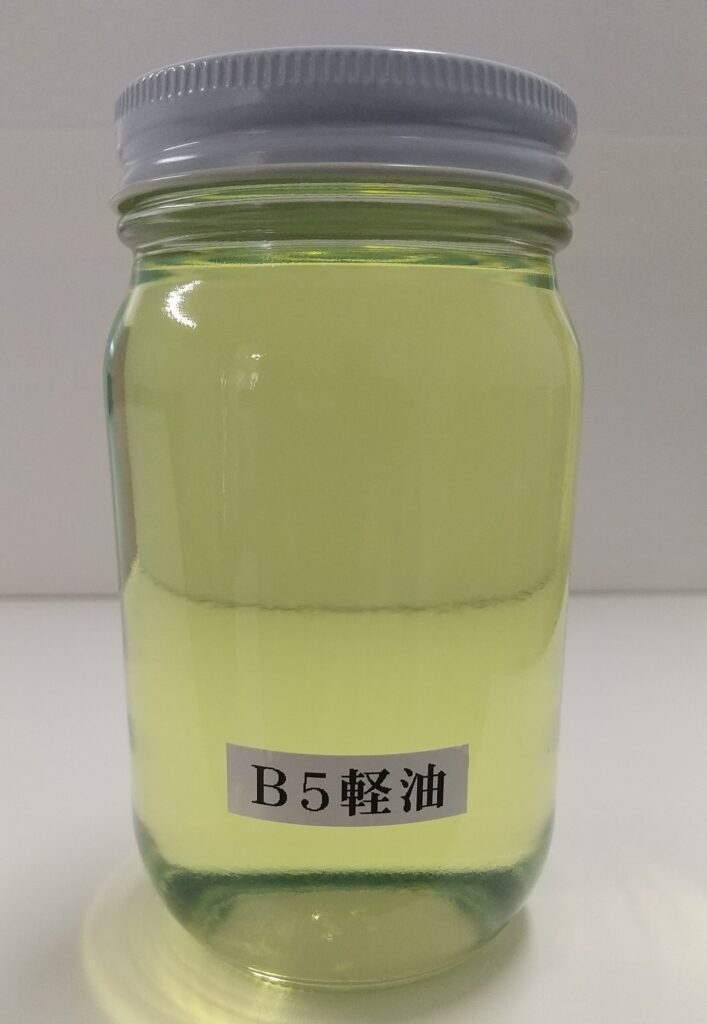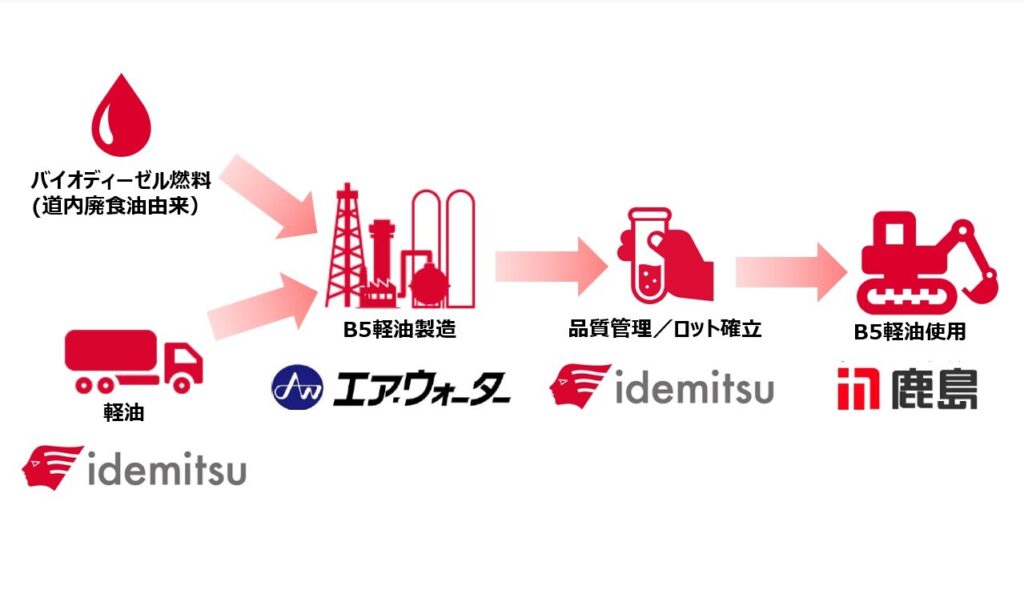原子力規制委員会の審査チームは7月26日の会合で、日本原子力発電の敦賀2号機(福井県)の直下の断層が活断層であることを「否定しきれない」との判断を示した。この曖昧な表現で、原発に対する新規制基準に適合していないとされた。31日の規制委定例会に報告される。この判断が規制委の審議で追認されると、日本の原発で、事後的に運転が停止される、初めての不合格例となってしまう。日本原電は詳細な地質調査を通じて活断層ではないことの立証に努めており、追加調査の継続や審査の再申請を強く希望している。規制委は議論の継続を認めるべきだ。
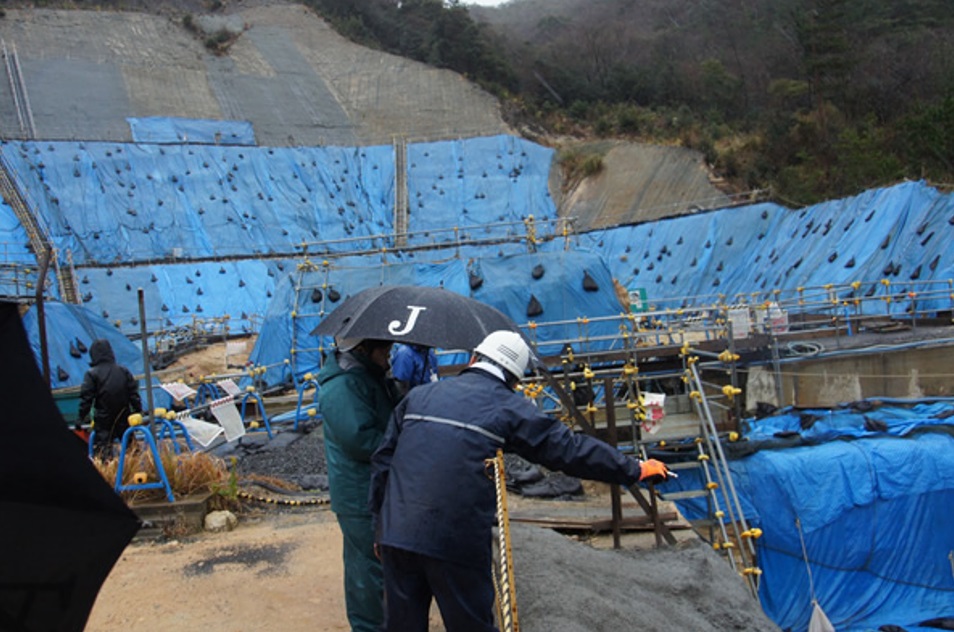
「悪魔の証明」の強要
これまで、エネルギーフォーラムなどの報道で指摘されたように、この審査は長期化、しかも議論の組み立てが異様だった。敷地内の断層を「活動性を否定することは困難である」として、そこから派生する断層が「連続する可能性が否定できない」との判定を下した。この論法は一種の「悪魔の証明」で日本原電側は、完璧な立証が難しい。
一行政機関が、民間企業の財産である、原子力発電所の活動を止めてしまう。これは財産権、経済活動の自由の侵害である。
こればかりではない。東日本大震災後に再稼働できた原発は12基に過ぎない。14基の原子力発電所が止まり、建設中の原発、大間と東通の原発の建設も進まない。行政手続法での審査期間は2年間であるのに、規制委は2012年の新規制基準の施工から12年も審査をしているプラントだらけだ。これはおかしい。
ここで日本原電は、政府を訴えること、そして政治判断を求めることをしてほしい。
行政訴訟しか、救済の方法が他にない
規制委員会による判断で、「廃炉」となる道筋は法律上決まっていない。規制委員会は、独立性を保つと言っても、好き勝手ができるわけがない。私は法律の素人だが、規制委員会・規制庁の行動には、さまざまな問題があると考えている。
その審査による日本原電、電力業界、経済損失、一般消費者への損失は計り知れない。仮に116万k Wの敦賀2号機が80%の稼働率で換算すれば、発電単価を10円=1k Whとして、年間860億円の価値を生み出せる。代替のLNG火力の燃料費削減効果は、100万k Wの原発1基で年間1000億円程度になる。
1800億円以上のコスト負担を、敦賀2号機をめぐる審査で、原子力規制委員会は国民に課している。他の長期停止した原発もそうだ。そして規制委の行動はかなり法的な不備がある。裁判では、そのおかしさとその是正を、かなり主張できるだろう。
私はアメリカの行政問題をいくつか調べたことがある。米原子力委員会(NRC)は、下部機関の原子力規制庁と各電力会社の規制が問題になっている場合に、裁定を下す機関だ。そのために原子力問題では、それほど行政訴訟は起きていない。しかし、税、通信、航空などでは、事業者と行政機関が頻繁に裁判を行っている。これは訴訟を当たり前とするアメリカの国情も反映している。しかし行政の行為を止めるのは、当然ながら司法なのだ。
日本では、企業が国を訴えることは稀だ。しかし他に手段がなければ、日本原電が敦賀2号機の問題で裁判をすることは一つの手であろう。
政治の介入をなぜしないのか
またこのおかしな判定で、政治の救済を日本原電は行うべきだし、政治もそれに応じるべきだ。岸田文雄首相が「首相案件」として介入しても良いほど、重要な問題だ。
政治家は原子力規制の問題から逃げている。批判が怖いのだろう。原子力規制制度は民主党政権の時につくられ、多くの問題があるのに、なかなか自民党政権、そして経産省は見直さない。この活断層騒動も、断層の規定を作り変えるだけで終わる話だ。今の12〜13万年前の活断層を、1万年程度にしたとしても、地震の予測はできないために、リスクは大きく変わらないという専門家もいた。
このようなおかしな規制政策を続けさせてはいけない。電力業界、日本原子力発電は、原子力の未来のために、過剰でおかしな規制を是正させてほしい。その背景には一連の原子力規制によって、安く、豊富な電気を使えなくなって、損を被った消費者がいる。政治家は、この現実を前に、原子力規制に対して、介入をして是正を図るべきだ。
そして、この敦賀2号機の異様な議論を前に、原子力規制のあり方そのものも議論し、改革をするべきであろう。