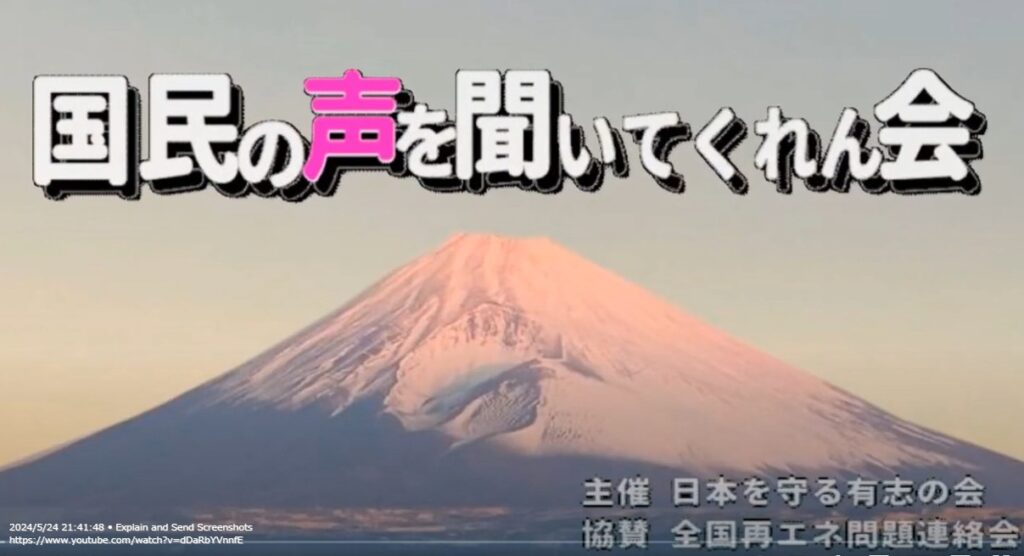ネットゼロ、サーキュラーエコノミー(循環経済)、ネイチャーポジティブの統合的な実現
1月から始まった通常国会は6月23日に会期末を迎える予定だ。エネルギー・環境関係では、水素社会推進法、CCS事業法、再生可能エネルギー海域利用法改正、地球温暖化対策推進法改正、生物多様性増進活動促進法、再資源化事業高度化法(いずれも略称)など、各分野での課題対応を図った法案が提出された。ここでは、水素、CCS、洋上風力関連の法案に比べて、メディアで取り上げられるボリュームがやや少ないように思われる、地球温暖化対策推進法改正、生物多様性増進活動促進法、再資源化事業高度化法の意義などについて、メディアの取り上げ状況も含めて触れておきたい。昨年のG7広島サミット、G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合では、ネットゼロ、サーキュラーエコノミー(循環経済)、ネイチャーポジティブ(←生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せること)の統合的な実現の重要性が再認識された。政府においても、「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2023」や「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」などでこの3つの課題に向けた取組みが取り上げられた。

参考=23年6月16日 経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)(抜粋)
◆新しい資本主義の加速~投資の拡大と経済社会改革の実行~
・グリーントランスフォーメーション(GX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)などの加速
30年度の温室効果ガス46%削減(13年度比)、50年カーボンニュートラルの実現に向け、わが国が持つ技術的な強みを最大限活用しながらGX投資を大胆に加速させ、エネルギー安定供給と脱炭素分野で新たな需要・市場を創出し、日本経済の産業競争力強化・経済成長につなげる。……(省エネルギー推進、再生可能エネルギー拡大、原子力活用、水素戦略、自動車・輸送分野での対応などに触れたのち)……地域・くらしの脱炭素化に向けて、中小企業などの脱炭素経営や人材育成への支援を図りつつ、25年度までに少なくとも100カ所の脱炭素先行地域を選定するなどGXの社会実装を後押しする。また、……国民・消費者の行動変容・ライフスタイル変革を促し、脱炭素製品などの需要を喚起する。環境制約・資源制約の克服や経済安全保障の強化、経済成長、産業競争力の強化に向け、産官学連携のパートナーシップを活用しつつ、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に取り組む。また、動静脈連携による資源循環を加速し、中長期的にレジリエントな資源循環市場の創出を支援する制度を導入する。……
◆わが国を取り巻く環境変化への対応
1.国際環境変化への対応
・対外経済連携の促進、企業の海外ビジネス投資促進
……アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)構想などの実現に向け、標準作りなどに加え、日本の技術や制度を活用し、世界の脱炭素化に貢献する。日本の技術を活用し、40年までの追加的プラスチック汚染ゼロとの野心の達成に向けて多数国による条約の策定交渉などを主導する。また、30年までに生物多様性の損失を止めて反転させる目標に向け、本年度中の国会提出を視野に入れた自主的取組を認定する法制度の検討や、グリーンインフラ、G7ネイチャーポジティブ経済アライアンスなどの取組を推進する。…… ←「ネイチャーポジティブ経済」については、後述「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」の項参照
4月19日の経済財政諮問会議においても、伊藤信太郎環境相が「環境を軸としたグローバル対応と地域活力の創生」と題して、ネットゼロ、サーキュラーエコノミー(循環経済)、ネイチャーポジティブの統合的な実現について語っている。
◎4月19日の経済財政諮問会議における伊藤信太郎環境相の説明〈環境を軸としたグローバル対応と地域活力の創生〉(内閣府議事要旨より)〈GXの推進に当たっては、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブを含め一体的に進めることが重要。現在検討中の第6次環境基本計画案においては、自然資本の基盤の上に経済社会活動が成立しているという認識に立ち、自然資本の維持・回復・充実を図り、複数課題の同時解決を目指す「統合的アプローチ」を環境政策のグランドデザインとして位置づける方針である。これに基づき、地域共生型の再エネ導入による地域の脱炭素化と経済活性化の同時実現や、GXに資するサーキュラーエコノミーの取組を進めていく。グローバル対応に関しては、先行する気候変動対策に加え、資源循環やネイチャーポジティブへの対応が重要になっている。資源循環分野においては、事業者間連携などによる資源循環の促進と国内外の資源循環体制の強化を通じ、わが国企業の産業競争力強化、経済安全保障に貢献する。ネイチャーポジティブ分野では、自然資本に立脚した豊かな経済社会の礎とすべく、ネイチャーポジティブ経済への移行による新たな企業価値の創造などを推進する。その際、日本の自然資本の状況を適切に表せる評価ツールの開発と、それを世界の標準としていくための産官学連携拠点の形成、国際標準化活動を通じ、サステナブルファイナンスの呼び込みを目指す。〉
環境・公害関係の専門紙・環境新聞は、上記会議での伊藤環境相の説明について報道するとともに、今国会の提出法案について関連付けて説明している。
◎環境新聞4月24日付〈4月19日の経済財政諮問会議に関する報道の中で〉〈……伊藤環境相は臨時議員として「環境を軸としたグローバル対応と地域活力の創生」を説明した。伊藤氏は「わが国が主導したG7コミュニケにもある通り、気候変動、生物多様性の損失及び汚染といった3つの世界的危機に対し、シナジーを活用し一体的に対応する『統合的アプローチ』が重要」と指摘。その上で「SDGSのウェディングケーキの図に示される通り、環境は経済・社会の基盤。ネットゼロ、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブを統合的に実現し、経済・社会の課題解決、新たな成長につなげていく」と強調した。環境省は統合的アプローチの一環として、今国会に再資源化事業等高度化法案、生物多様性増進活動促進法案、温暖化対策法改正案の3法案を提出している。〉
なお、環境新聞は閣議決定、衆議院可決といった節目ふしめでその動きを、付帯決議の内容まで含めて紹介している。