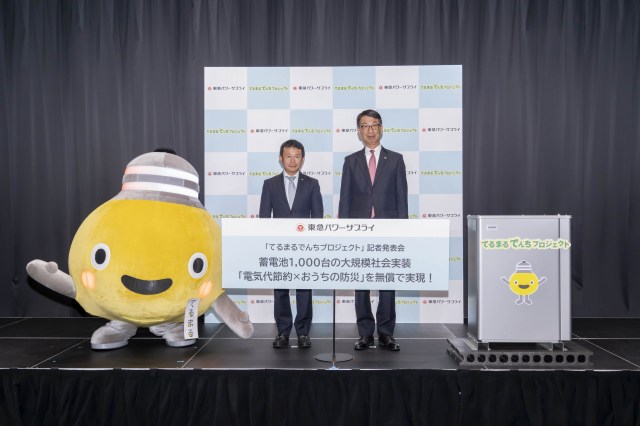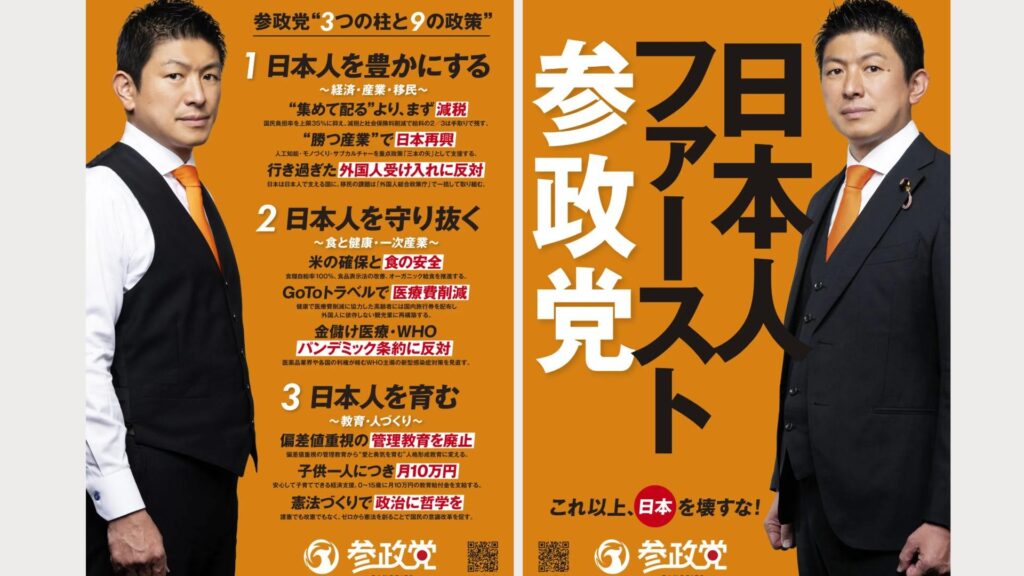7月の参院選後、政局が注目される状況が続いている。一方、社会保障、財政、安全保障、そして世界の経済秩序が大きく変わる中での経済成長など、中長期の視野で議論を深めるべき課題は多い。エネルギー政策もその一つと言えよう。2月18日、「第7次エネルギー基本計画」「地球温暖化対策計画改定」「GX2040ビジョン」が閣議決定され、また、日本の「NDC(国が決定する貢献)」が国連気候変動枠組み条約事務局に提出された。そこでは多くの課題も提示されており、その中で「脱炭素と経済の両立」という困難な命題に対処しなければならない状況にある。

例)
・当面のデータセンターなどの電力需要増加に対する系統などのインフラ整備
・核燃料サイクルの進捗、安全対策の高度化などに伴うイニシャルコスト増などへの対応が求められる中での原発活用の促進(再稼働、新増設)
・コストアップ、地元との共生など、太陽光や洋上風力などにおいていろいろな課題が表面化した再生可能エネルギーの拡大
◆「地方創生」と「地域脱炭素」
1.「地方創生」と「再生可能エネルギーの導入による地域脱炭素の推進」
ところで、エネルギー問題への取り組みは本来、国全体の経済社会の安定を支えるとともに、石破政権が重要テーマとした「地方創生」とも密接にかかわり、後押しするものである。6月に閣議決定された「地方創生2.0基本構想」では、「稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生」の一つとして「再生可能エネルギーの導入による地域脱炭素の推進」が掲げられている。
参考= 「地方創生2.0基本構想」(6月13日閣議決定、概要より抜粋)
●政策の5本柱
(1)安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
(2)稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生~地方イノベーション創生構想~
・再生可能エネルギーの導入による地域脱炭素の推進⇔「地球温暖化対策計画改定」(2月18日閣議決定)2030年度までに脱炭素先行地域を少なくとも100地域で実現し、先行的な取組を普遍化
(3)人や企業の地方分散~産官学の地方移転、都市と地方の交流などによる創生~
(4)新時代のインフラ整備とAI・デジタルなどの新技術の徹底活用
(5)広域リージョン連携
→都道府県域や市町村域を超えて、地方公共団体と企業や大学、研究機関などの多様な主体が広域的に連携し、地域経済の成長につながる施策を面的に展開
2.「地域循環共生圏」「地域脱炭素ロードマップ」から「脱炭素先行地域」へ
◎「地域循環共生圏」第五次環境基本計画(18年4月17日閣議決定)で提唱
地域循環共生圏とは、「各地域がその地域資源を活かして自立・分散型の社会を形成、補完し、支え合う」(環境省資料)ことで地域を活性化させるというものである。第五次環境基本計画では、新たなバリューチェーンを生み出し、地域の活力を最大限に発揮する地域循環共生圏の考え方を展開するとした。
参考= かつて、ある環境省幹部は次のように述べていた。
「地域循環共生圏では、まずは、エネルギー、文化・観光、食、自然、農林水産など、時に見過ごされがちだった各地域の地域資源を再認識し、価値を見出していくことが、地域における環境・経済・社会の統合的向上に向けた取り組みの第一歩となる。例えば、地域におけるバイオマスを活用した発電・熱利用は、化石資源の代替と長距離輸送の削減によって低炭素・省資源を実現しつつ、地域雇用の創出、災害時のエネルギー確保によるレジリエンスの強化といった経済・社会的な効用も生み出す。分散型エネルギーの収益を地域での再投資に向けるなど、地域資源で稼ぎながら課題解決をすることで、持続可能な形で地域循環共生圏の形成に取り組むことになる。地域循環共生圏の形成とは“地域の未来づくり”に他ならない」「分散型エネルギーシステムは、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの普及拡大、エネルギーシステムの強靭化に貢献する。それはまた、コンパクトシティや交通システムの構築など、まちづくりと一体として導入が進められることで、地域の活性化にも貢献し、“地域循環共生圏”の形成にも寄与するものである」
◎「地域脱炭素ロードマップ」21年6月9日 国・地方脱炭素実現会議で決定
●キーメッセージ
地方から始まる、次の時代への移行戦略(概要より抜粋)
・わが国は、限られた国土を賢く活用し、面積当たりの太陽光発電を世界一まで拡大してきた。他方で、再エネをめぐる現下の情勢は、課題が山積(コスト・適地確保・環境共生など)。国を挙げてこの課題を乗り越え、地域の豊富な再エネポテンシャルを有効利用していく。
・一方、環境省の試算によると、約9割の市町村で、エネルギー代金の域内外収支は、域外支出が上回っている。
・豊富な再エネポテンシャルを有効活用することで、地域内で経済を循環させることが重要。
↓
今後の5年間に政策を総動員し、人材・技術・情報・資金を積極支援して、
・30年度までに少なくとも100か所の脱炭素先行地域を創出
・全国で重点対策(自家消費型太陽光、省エネ住宅、電動車など)を実行
◎脱炭素先行地域の創出
「地球温暖化対策計画改定」(2月18日閣議決定)においても、30年度までに100以上の脱炭素先行地域の創出を掲げている。