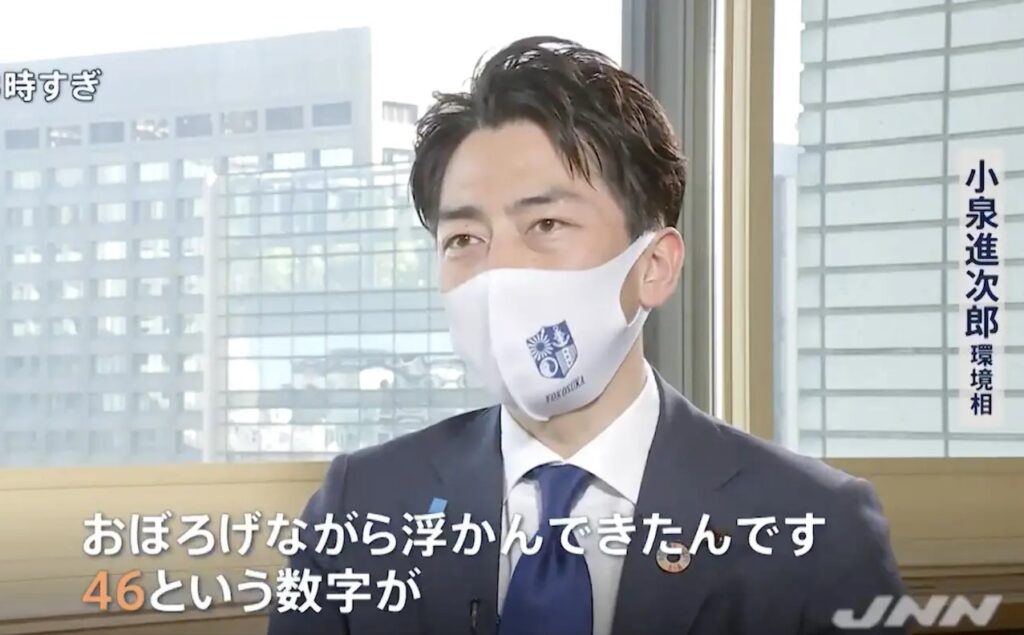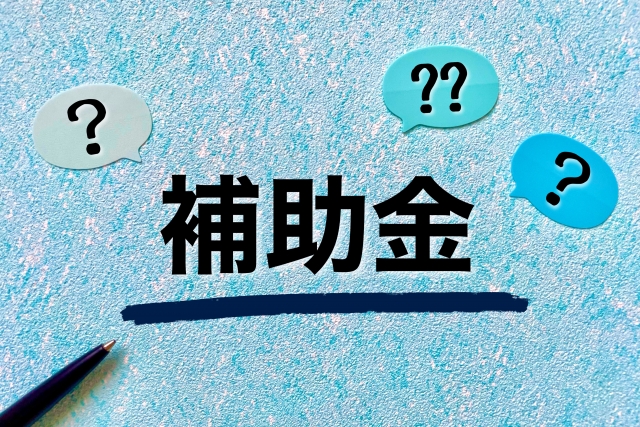7月20日に行われた参院選は自民、公明両党の連立与党が大敗し、非改選を合わせ参議院の過半数を失った。衆議院でも連立与党は過半数を失っている。これをきっかけに政治が流動する可能性がある。またエネルギー、特にこれまで政治の注目の的であった原子力政策が選挙で争点にならなくなった。これはエネルギーに関わる産業人などの実務家が声を上げ、状況を動かすチャンスにも見える。

◆自民党が自壊した選挙、エネルギーは争点にならず
石破茂首相(自民党総裁)は23日時点で退任の意向を示していない。その去就は不透明で、政治の先行きが見えなくなっている。
参院選挙では物価高などの経済問題が争点になったが、外国人問題などがSNSで盛り上がり、勢力を伸ばす参政党が「日本人ファースト」とスローガンを掲げた。それに左派のメディアや政治勢力が批判。移民促進など自民党のこれまでの政策が問題視され、左傾化批判の批判も重なり、これまで続いていた中道・保守層の自民党離れが広がったようだ。
そしてエネルギー問題は選挙中に大きく取り上げられなかった。各政党の公約には気候変動対策の言及はあるが選挙戦では強く主張されなかった。物価高対策では、各党とも具体的な決め手のある対策を打ち出せない中で、これまで政府が行ったガソリンの補助金政策が放置された。選挙前に再エネへの過剰補助金を疑問視する声が、国民民主党や日本保守党から出た。ただし、その問題での政党間の是正の協力は具体的な形にはなっていない。再エネ好きと言われる石破首相は、エネルギー問題を語らなかった。
エネルギーを巡る議論の低調さは、朝日新聞が社説で「参院選 エネルギー 原発論議が足りない」(7月17日)など叱る社説を掲載するほどだった。朝日はこれまで脱原発、エネルギー自由化の促進を主張してきた。
ただし、このエネルギーを巡る政治の変化は、民意の適切な動きを反映したものと捉えることもできる。原子力への好き嫌いでエネルギーを感情的に語る意見が減り、政治問題にする必要はないという人々の考えの変化も表しているのだろう。ちなみに、国民民主党、参政党は原子力推進を公約に掲げている。この両党が参院選で躍進した事実を見ても、原子力に対する有権者の抵抗感がなくなってきた証左ともいえよう。
◆「決められない政治」が再び
衆参両院ともに少数与党の政権運営は一段と不安定になる。原子力政策では与党の自民党、消極的な公明党の間では向き合い方に差がある。野党では脱原発を掲げる立憲民主党などの左派政党と、活用を掲げて再エネに批判的な国民民主党、参政党、日本保守党との間で距離がある。エネルギー政策で、まとまった政治の動きがつくられそうにない。民主党政権下で福島原発事故から始まったエネルギーシステム改革は、短期間で方向が決まった。これは福島原子力事故の衝撃が影響した、例外的な状況だったのだ。
比較的若い世代、そして勤労世代の支持があった新興政党の先行きは未知数だ。今回の選挙で躍進は著しい。国民民主党の得票数は762万票(選挙区との合計17議席)、参政党は742万票(同14議席)、日本保守党は298万票(同2議席)となった。自民党の得票数は919万票(同19議席)と、こうした新興政党の合計に及ばない。また既存政党の支持者は、自民党、立憲民主党、共産党、いずれも高齢層に傾いている。新しい政党が今後、議席や得票を大幅に減らすことは考えにくいし、彼らの考えがエネルギー政策にも反映していくだろう。
単独で過半数をとれない各党が、その時々の政治情勢に応じて連立を組んだり、合意で一時的に協力したりする。これは欧州の比例代表制を導入した国で頻繁に起きる政治状況だ。日本でも1990年代に次々と政権が変わり「何も決められない」政治状況になってしまった。
ただし欧米の場合には、エネルギー・原子力政策など、国の根本をなすことや安全保障政策では、国民的合意ができている国が多い。日本では、原子力、再エネでは、そのような合意ができていない。そこで多党化が進めば、大きな国策は何も決まらない状況になるだろう。
◆外部の意見に振り回されたエネルギー業界
一方で、世論や政治家の関心がエネルギー問題で薄れている状況は、逆にエネルギーの関係者にとっては存在感を増す好機かもしれない。福島原発事故からエネルギー業界、特に電力業界は、政治と行政と世論、そして専門家と称する人に振り回された。
そこで増幅された「民意」や「世論」と称するものの中には、エネルギー問題を使って政治主張をする活動家の主張もあった。原子力、再エネ、電力の地域独占解体と自由化、そして気候変動問題で、そうした理念先行の意見に影響された制度改革が行われた。
筆者はエネルギー業界の片隅で、そうした政治的動きを見てきた。そこでは電力・エネルギー業界側が、一方的に「あるべき姿」を押し付けられる場合が多かった。そしておとなしかった。福島原子力事故のため、また国民全部が顧客であるため、意見を言いづらかったのだろう。また各電力会社の企業文化として、おとなしく紳士的な面がある。こうした事情が重なって、実務家の意見の反映が少ない、奇妙な制度ばかりになった。
◆政治の関与の低下は実務家の存在感を増す
その状況が変わるかもしれない。エネルギー問題で政治が決められない一方で、口を出さなくなった。意見の押し付けがなくなり、専門家・実務家の意見が目立ちやすくなった状況でもある。この状況を、エネルギー関係者は活用してほしい。
筆者は米国の慈善活動家のビル・ゲイツ氏の著書「地球の未来のため僕が決断したこと 気候大災害は防げる」(早川書房)をこのほど読んだ。彼は成功したビジネスマンらしく、「まず形にする」ことに、こだわっていた。アイデアでも技術でも、プラントやビジネスにすることで、関係者に突きつけ社会や関係者を動かし、現実を変える。彼が新型原子炉などのビジネス化を急ぐのも、この理由だった。同じ発想が、今の日本のエネルギー問題に使えるかもしれない。
実務家の方から動き、提言し、ビジネスやプラントの形を作り、人々の意見を取り入れながらより良いものにしていく。社会からの要求に萎縮するのではなく、現場の実情を基にして具体的な物を見せて提案をする。どのようなエネルギーシステムを作るべきかをステークホルダーと語り合う。
このように適切な電力・エネルギーシステムの議論が始められる状況にある。これはガス、石油など、他のエネルギー産業においても同じだ。今回の選挙で力を得た新興政党は、そうした強い日本を作ることに、前向きな考えの議員や支持者が多い。
参議院選挙の結果を深読みすると、そのような変化の期待が、エネルギー関係者に抱かせるものになっているように思う。