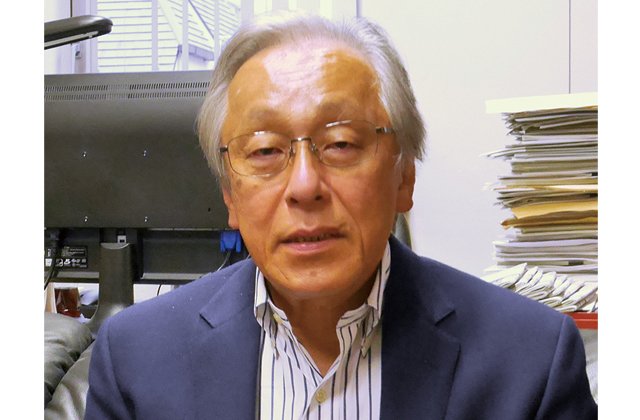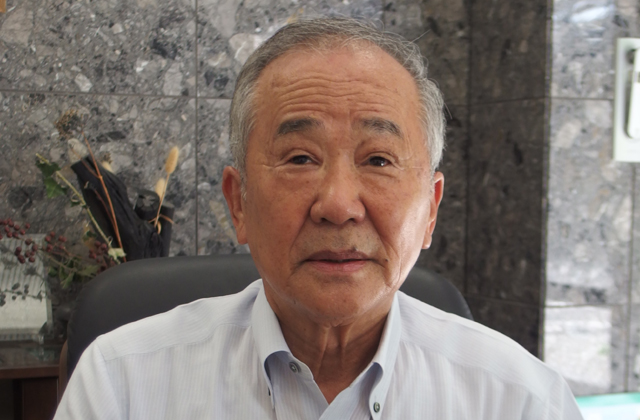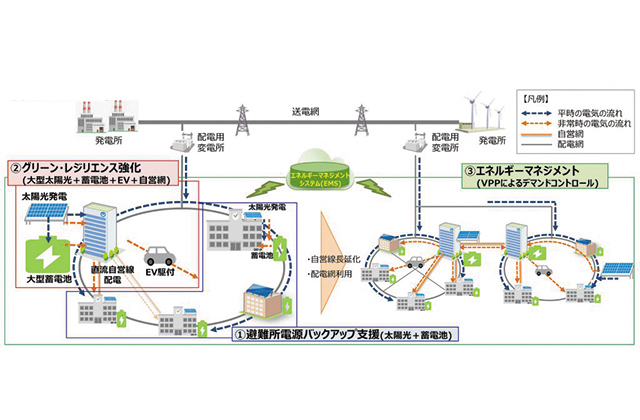発電小売部門に競争を導入する電力自由化がスタートし四半世紀が経過した。第一人者たちが歴史を振り返るとともに、未来のあるべき姿を提言する。
【座談会】井上雅晴/V-Power顧問、岩井博行/岩井レポート・アドバイス代表、本名 均/イーレックス社長、中井修一/電気新聞元編集局長、西村 陽/大阪大学大学院工学研究科招聘教授

下段左から中井氏、西村氏
―まずは、電力自由化四半世紀を振り返って率直な感想をお聞かせください。
井上 自由化以前は、大手電力会社にコスト削減の概念はほとんどなかったと聞いています。それが、競争にさらされ大きく変わりました。当時、電力会社の総売り上げは15兆円ありましたが、最初の5年で年間約2兆円下がったと記憶しています。そういう意味で、5年に限っては自由化の効果があったと思います。
岩井 もっとスピード感を持って改革を進めるべきであり、新規参入者側としてそういう働き掛けをしてこなかったことは大きな反省点です。安定供給への配慮もあり、ゆっくり進めたばかりに体制づくりもゆっくりとしたものになった。それが、「間違った」と思っても後戻りできない状況をつくり出してしまいました。
本名 2000年当時、新電力といえば通信事業者やガス事業者、商社など、資本がしっかりとした大企業が中心でした。供給力をいかに確保するかも含め、大手電力会社に対し不利な競争環境であることを覚悟の上での参入だったのです。当社も自前の供給力を確保しようと、LNG火力発電事業に乗り出しましたが、リーマンショックに伴う原油高につながるタイミングと重なり大失敗に終わりました。このように、自由化後は予想し得ないことが多々起きました。東日本大震災以降は、欧米のシステム改革を追う形でさまざまな制度改革が急速に進められ、あっという間で大変な20年間でした。
中井 取材してきた側から申し上げると、電力業界、中でも東京電力の力が大きくなりすぎたことに問題意識を持った官僚の行動が全ての改革の始まりでした。政治・経済情勢や米国との関係などさまざまなことが起因し、経済産業省は新事業者を参入させる規制緩和にかじを切ったわけです。市場を開放し電気料金を下げることが狙いでしたが、本当に国民経済的に良かったと言えるのか、答えが出るにはもう少し時間がかかりそうです。
西村 新電力の草創記は原油高で、メリットオーダー上、石油が市場価格を決めていたため市場には最も高い玉しか出ませんでした。原油高騰により08年ごろは新電力にとって最も厳しい時代でしたが、それでも電力供給システムを熟知した上で事業展開してくれたおかげで、電力業界はゆっくりと体質を改善することができたのです。12年以降のシステム改革であまりに電気事業について不勉強な市場参加者が増えてしまい、安定供給が崩壊しつつある現状との落差を考えると、最初に参入された皆さんの大きな貢献があらためて思い起こされます。