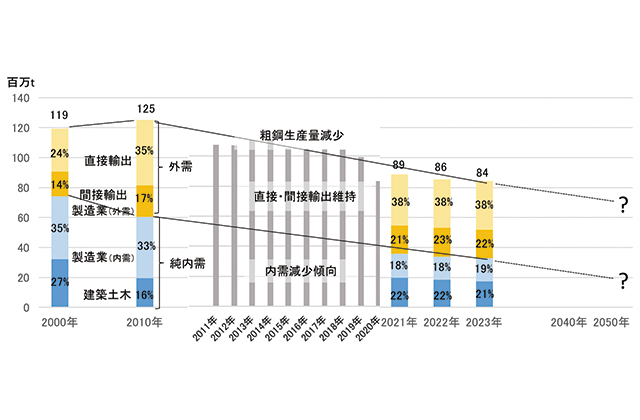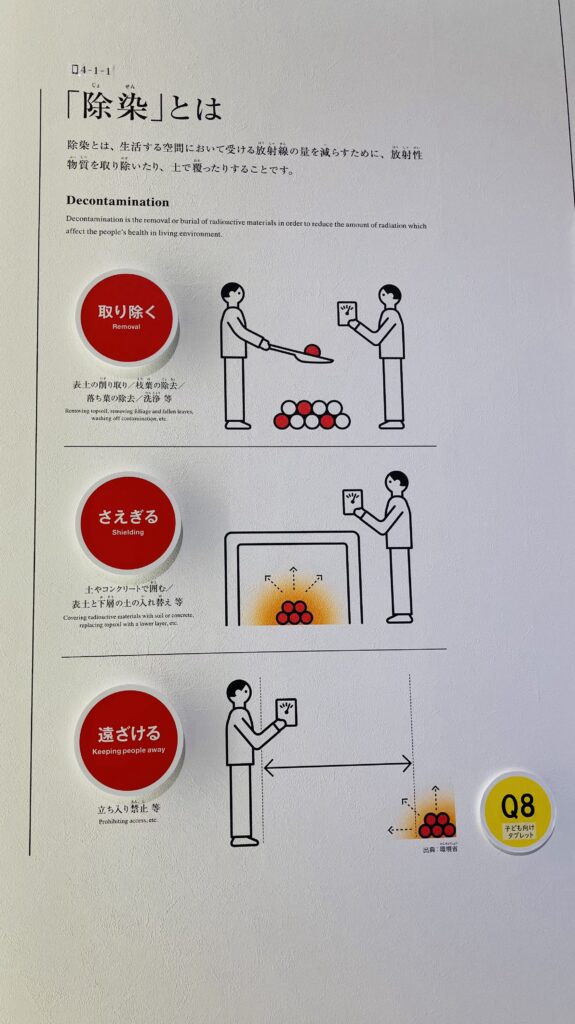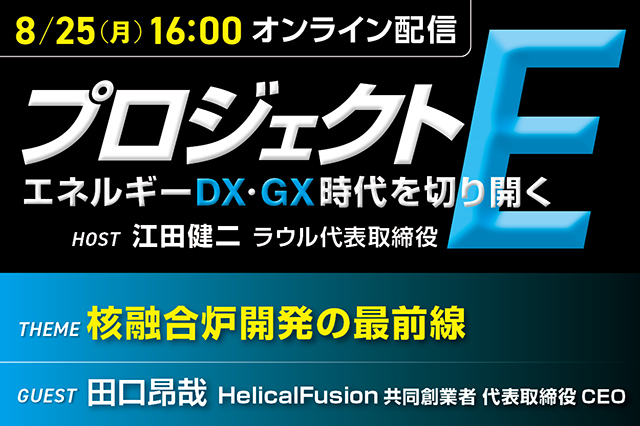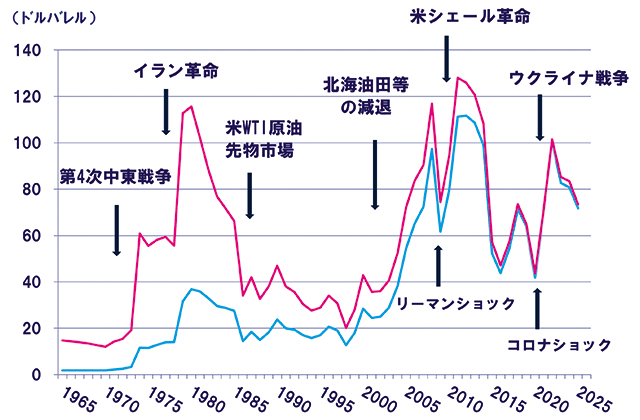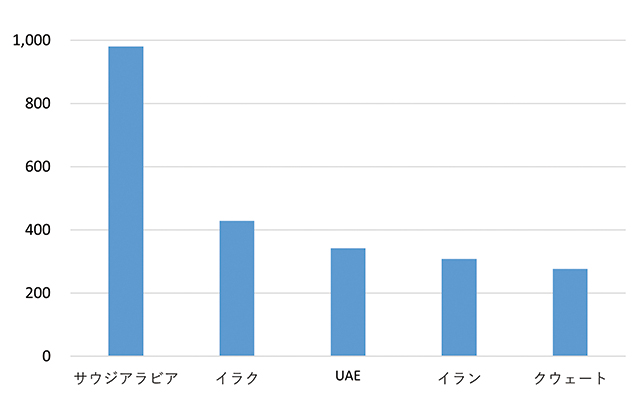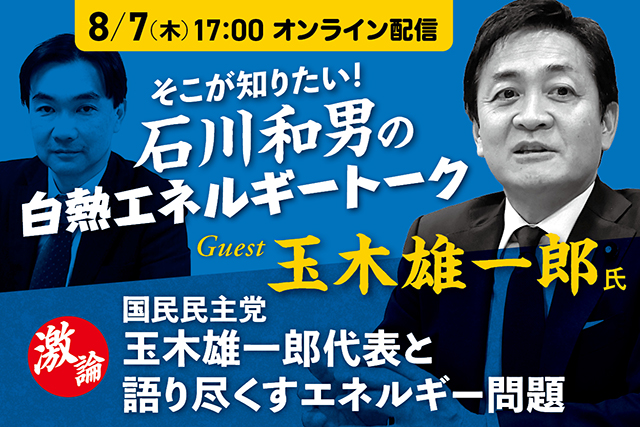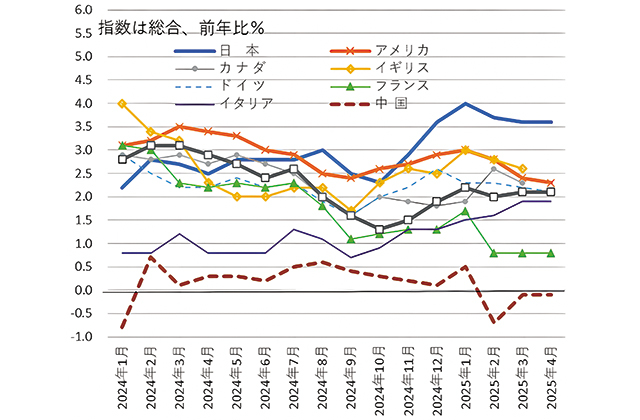シナリオは、電力需要の減少から増加へと局面が大きく変わることを知らしめた。
同時に火力や原子力といった安定電源が大きく不足するということも。政策路線の転換は待ったなしだ。
「電力業界に長らくいて、需要が伸びるという局面を経験したことがない。それだけに、事業環境が劇的に変化することを示唆したシナリオには明るい未来を感じずにはいられない」
大手電力会社の関係者の一人は、電力広域的運営推進機関が7月に公表した「将来の電力需給シナリオ」について、こう受け止めを語る。
とはいえ、シナリオは単に明るい兆しを予見させるようなものではない。省エネの進展と再生可能エネルギーの大量導入により、足元では火力電源の退出が続く。「今の事業環境のままでは、需要増に対応する供給力を十分に手当てできない。そうなれば国として経済成長のチャンスをみすみす逃すことになるという大問題を突き付けられたことは、業界にとって大きなインパクトだ」と、この関係者は表情を引き締める。
DXが需要をけん引 kW、kW時不足が顕著に
需給シナリオとは、2040年と50年の断面における需給バランスを試算したものだ。需要と供給力の想定モデルを複数組み合わせた計20通りのケースでkWバランスを評価し、安定供給に必要な予備率との差分を確認。その上で、仮にその差分を全て火力で補完した場合のkW時バランスを作成した。
需要面では、人口減少などを背景に民生部門は引き続き減少傾向が続くものの、全体では40年に9000億~1・1兆kW時、50年に9500億~1・25兆kW時と、いずれも19年度実績の8800億kW時を上回ることを想定している。
これをけん引するのが、データセンター(DC)や半導体工場の新設、そして自動車の電動化などのDX(デジタルトランスフォーメーション)・GX(グリーントランスフォーメーション)関連産業の進展であり、最も大きく伸長するモデルケースでは、DX・GX関連産業が総需要を約3割押し上げることが想定されている。
その結果、kWバランスはどうなるのかというと、全シナリオで、再エネの導入拡大が進んだとしても、経年火力が全てリプレースされない限り、供給力不足に陥ることに(図)。しかも、最も需給が厳しくなる夏季夜間には最大で8900万kW―、つまり大型火力約90基分もの供給力不足が発生しかねないというから衝撃的だ。
とりわけ、需要が大きく伸長する40年の1・1兆kW時、50年の1・15兆kW時以上のモデルケースでは、原子力が最大限活用され、経年火力が全てリプレースされたとしても供給力が不足する。つまり、電源を維持・リプレースするだけではなく、新設をしなければならないことを意味する。
発電事業関係者が警戒感をあらわにするのは、火力の設備容量kWの拡充が求められるにもかかわらず、設備利用率が33~43%という低水準にとどまることについてだ。現状でさえ、稼働率の低下で発電コストの回収が困難化している。その上、シナリオでは他の政策目標と整合を取る形で50年に脱炭素化対策が実施されていることを前提としている。CCS(CO2の分離・回収)や、水素・アンモニア燃焼といった新技術を採用するコストを回収する手段を講じない限り、電力需要の拡大とそれに対応する安定的な電源の確保は虚構に終わる。
シナリオの取りまとめを担当した広域機関の小林亮治企画部・マネージャーは、「事業者の投資判断がより難しくなる可能性を示唆しており、シナリオの結果を踏まえた政策措置の検討が行われることを期待する」と、電源投資を巡る検討材料を提起した意義を強調する。
そもそも、シナリオ策定の端緒は22年8月のGX実行会議にある。岸田文雄首相(当時)が「安定供給の再構築について検討を加速化」するよう指示したことを受け、翌年4月に資源エネルギー庁に「将来の電力需給に関する在り方勉強会」が発足。同年11月には広域機関にタスクアウトされ、「将来の電力需給シナリオに関する検討会」で策定作業に着手した。
これまでにも、電気事業者の届け出に基づく10年間の供給計画はあったが、10年を超えた長期の見通しを示すのは初めてのこと。需給モデルの作成を電力中央研究所、地球環境産業技術研究機構(RITE)、デロイトトーマツコンサルティングの3社が担当し、計10回にわたる検討の末、今年6月の取りまとめに至った。
将来見通しには不確実性が伴うため、その内容はどうしても幅広いレンジにならざるを得ない。JERAの平尾啓太経営環境部長は、「これまでDCや半導体需要が伸びることは確認されていたが、50年に向けた具体的な規模感が示されたことはなかった。需給シナリオには幅があるとは言っても、これから需要が伸びて供給力不足になる可能性が出てきたという認識を醸成するきっかけになるだろう」と、今後、政策議論を進める上での有力な材料の一つになるとと見る。