オンライン・コンテンツリスト
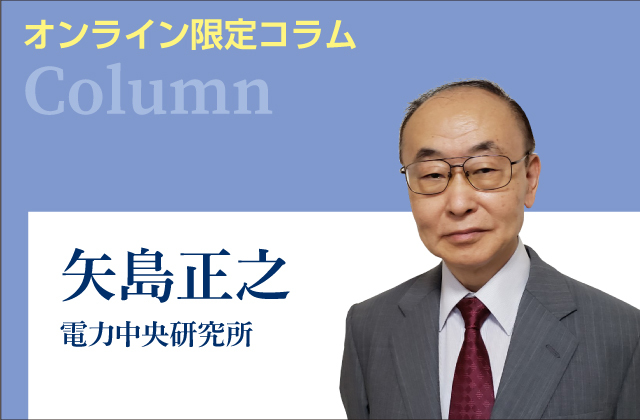 |
【コラム/4月20日】ウクライナ危機とEUのエネルギーセキュリティ政策
2022年4月20日
矢島正之/電力中央研究所名誉研究アドバイザー EUの一次エネルギーの域外依存度は、6割弱と高く、天然ガスは8割強、石油は10割弱、石炭は3割台半ばが輸入に頼っている。輸入元とし... |
 |
【記者通信/4月19日】太陽光発電の調整力費用 送配電会社の重い負担に
2022年4月19日
大手電力の送配電会社(一般送配電事業者)は、天候悪化などによる予測困難な太陽光発電の出力低下に備えて、必要な電源を調達している。一部の送配電会社にとって、この負担額がかなりの高額になり、見直しの動... |
 |
【マーケット情報/4月14日】原油急伸、需給緩和感が台頭
2022年4月18日
【アーガスメディア=週刊原油概況】 4月8日から14日までの原油価格は、前週から一転し、主要指標が軒並み急伸。需要回復の見通しと、供給の先行き不透明感で、価格が反発した。 ... |
 |
ドイツに学ぶエネルギー安全保障
2022年4月18日
【ワールドワイド/コラム】水上裕康 ヒロ・ミズカミ代表 ついにロシアのウクライナ侵攻が始まったが、これにより注目を集めるのがEUのロシアに対する天然ガス依存だ。ウクライナにはそ... |
 |
【記者通信/4月17日】CE戦略会合で原発推進論が続出 消費者委員も再稼働に理解
2022年4月17日
「可能な限りの依存度低減」から「最大限の活用」へ――。わが国の原子力政策が大きな転換点を迎えている。それを象徴するのが、4月15日に開かれた経済産業省のクリーンエネルギー戦略検討合同会合(座長=白石... |
 |
ドイツが悩む再エネ力不足 エネルギー安保の原点回帰へ
2022年4月17日
【ワールドワイド/環境】 ロシア軍によるウクライナ侵攻は今後の世界のエネルギー・温暖化政策動向に大きな影響を与えるだろう。とりわけ影響が大きいのはドイツである。 ドイツで... |
 |
70年排出ゼロ目指すインド 再エネ導入で送電投資拡大へ
2022年4月16日
【ワールドワイド/経営】 インドのモディ首相は2021年11月1日、英国で開催された第26回国連気候変動枠組み条約締国会議(COP26)の首脳級会合で演説し、70年までにカーボ... |
 |
ロシア財政の要である石油生産 迫られる新規フロンティア開発
2022年4月15日
【ワールドワイド/資源】 ロシアにとって石油天然ガス輸出は財政の要であることは疑いの余地がない。中でも、税収としての重要性は石油の方が大きい。輸出総額では原油および石油製品の輸... |
 |
【インフォメーション】 エネルギー企業の最新動向(2022年4月号)
2022年4月14日
【関西電力/福岡でバイオマス専焼発電所の運転開始】 関西電力グループが運営するバイオマス発電所「かんだ発電所」(福岡県苅田町)が営業運転を開始した。関電グループが関西エリア外でバイオマス専焼の... |
 |
再エネ100%で危機回避? あまりに能天気な東京新聞
2022年4月14日
【おやおやマスコミ】井川陽次郎/工房YOIKA代表 実用日本語表現辞典によると、「能天気」には相手をさげすむニュアンスがあるため「楽天的」と言い換えた方がいいらしい。東京3月3... |
 |
『太陽の都』*の幻想 ソーラーパネルの否定的側面
2022年4月13日
【オピニオン】セルゲイ・デミン/ロスアトム東南アジア日本支店代表 新型コロナウイルスによるパンデミック以前の15〜20年よりも、この2年間の方が世界は変わっている。原始的な消費... |
 |
【記者通信/4月12日】野田元首相「俺一人でやる」 原発再稼働表明の舞台裏
2022年4月12日
元民主党の経済産業大臣政務官で、現在は無所属会派「有志の会」の北神圭朗衆議院議員(京都4区)が4月12日、エネルギーフォーラムが主催するオンライン番組「そこが知りたい!石川和男の白熱エネルギートーク... |
 |
【目安箱/4月12日】急務の原発再稼動 なぜ岸田首相は動かないのか?
2022年4月12日
原子力をめぐる雰囲気が変化している。感情的な原子力の反発は少なくなり、SNSなどでは原子力の活用を主張する声が強まり、政治家も原子力発電所の再稼動を語るようになった。昨年からのエネルギー価格の上昇に... |
 |
大震災機に地産地消へ本腰 官民連携で目指す持続可能な地域
2022年4月12日
【地域エネルギー最前線】神奈川県小田原市 カーボンニュートラルの実現に向け、地域社会はそれぞれどんな戦略を描いているのか。 各地の挑戦を追う連載初回は、東日本大震災を機に... |
 |
【北神圭朗 有志の会 衆議院議員】「平和で豊かな日本を次世代に」
2022年4月11日
きたがみ・けいろう 1992年京都大学法学部卒、大蔵省(現財務省)入省。2005年衆院議員。拉致問題特別委員会筆頭理事、経済産業大臣政務官、内閣府大臣政務官(原子力損害賠償支援機構担当)、首... |



