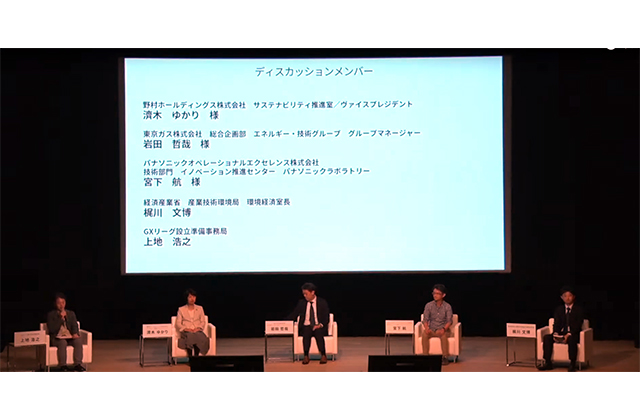【中部電力ほか/境港市で木質専焼バイオマス発電所を開発】
中部電力とNew Circle Energy社、稲畑産業、中部プラントサービス、NX境港海陸、三光の6社が出資する境港昭和町バイオマス発電合同会社はこのほど、プロジェクトファイナンスによる融資契約を結んだ。この合同会社は、木質専焼の「鳥取県境港市バイオマス発電所」の発電設備の開発、建設、運転、保守管理業務などを行う。発電出力は2万8110kW。想定する年間発電電力量は、一般家庭の約6万4000世帯分に相当する約2億kW時。燃料は、鳥取県や島根県など中国地方で調達する未利用間伐材や一般木材、建設廃材などからの木質チップと木質ペレットを活用する。今年11月に工事を開始し、2026年5月の運転開始を目指している。
【大阪ガス/カーボンニュートラル目指しガスビルをリノベーション】
大阪ガスは、大阪市中央区にあるガスビルのリノベーションとガスビル西館(複合ビル)の都市開発に着手する。都市再生特別地区制度により、ガスビル敷地と西側の社有地との間にある市道の上空を活用し、両敷地の一体的利用を図る。また、歴史的建築物であるガスビルの保存を中心とした都市再生への寄与による容積率の緩和を受け、敷地全体の高度利用を図る。商業施設を誘致し、周辺地域ににぎわいをもたらすと共に、上層階にはオフィスを整備し、高度な業務機能の集積と調和するビジネスゾーンの形成を進める。また、カーボンニュートラルビルの実現とガスビル・ガスビル西館、周辺地域のレジリエンス向上に取り組み、御堂筋周辺地域の活性化に貢献していく。
【東京ガス/レノバから太陽光発電と非化石価値を買い取り】
東京ガスは、レノバとの再エネ需給調整サービスを活用した電力購入契約に基づき、太陽光発電の電力と非化石価値の買い取りを開始した。買い取るのは三重県の四日市市と名張市にレノバが新設した、4カ所の太陽光発電所の電力約375kW。RE100に加入するなど環境意識の高い需要家に、この電力と環境価値を届ける。2023年度末までに最大1万3000kWの取引を計画しており、順次拡大する。東京ガスの再エネ需給調整サービスは、電力や非化石価値の買い取りのほか、再エネ発電予測・発電計画の作成・提出や、インバランスの費用負担を東京ガスが行う仕組み。再エネ発電所の開発と運営に強みを持つレノバと協業することで、FITに依存しない再エネの普及拡大を目指す。
【NTTスマイルエナジー/PPA導入でCO2削減を支援】
NTTスマイルエナジー(大阪市)はこのほど、浜松白洋舎(浜松市)の浜松白洋舎浜北工場に、法人向け太陽光発電設備PPAサービス「スマイルそらえるでんき」導入の契約を結んだと発表した。導入工事は、東海エリアで電気工事網の実績を持つスマートブルー社が担当する。発電した電力は工場内で自家消費する。年間発電量は約9万8000kW時を想定。これにより、同工場の使用電力のうち48%が太陽光発電由来となり、年間約40tのCO2削減を見込む。
【コスモエネルギーHD/トラックターミナル初 水素ステーション建設】
コスモエネルギーホールディングスのグループ会社、コスモ石油マーケティングは岩谷産業と共同で、水素ステーション事業を担う岩谷コスモ水素ステーション合同会社を設立した。同社が手掛ける最初のステーションは、京浜トラックターミナル内にある「京浜トラックターミナル平和島SS」に、2024年中の併設を予定している。今後の燃料電池(FC)商用車の増加を見据えて、短時間で充填可能な水素ステーションを計画している。脱炭素社会の実現に向けて、水素燃料の社会実装と水素の需要拡大を進めていく。
【スマートエネルギーWeek/新エネルギーの最前線 世界最大級の総合展】
国内外のエネルギー関連団体や企業が集まる世界最大級の総合展示会「スマートエネルギーWeek春2023」が、3月15日から3日間にわたり開かれた。水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、風力発電、バイオマス発電、ゼロエミッション火力の七つの展示会で構成し、多くの最新技術が並ぶ。世界各国から専門家も来場し、経済産業省や環境省、大手電力会社役員などによる講演会も開催。2050年カーボンニュートラル実現に向けて、エネルギービジネスを加速する商談の場にもなっている。
【東電設計/送電鉄塔の基礎工事を大幅簡略化】
東電設計は送電線の鉄塔の基礎をつくる際に使われる床板部分のプレキャスト(成形済み)化を実現し、製品の販売を始めた。送電鉄塔の基礎の施工は、鉄塔の組立に支障がないようにするため難易度が高く、専門の作業員が経験と技術を頼りに作業している。現場の条件に合わせたプレキャスト部材を工場で生産、現地では組み立てるだけにし、経験・技術不足の作業員でも基礎を構築できるようにした。既に東京電力が横浜市の現場で採用。他社も採用を検討している。
【三菱電機/系統安定化を支援 大規模停電の防止へ】
三菱電機は、北海道電力ネットワークから統合型系統安定化システム(IRAS)を受注した。IRASは電力系統の事故を瞬時に検知し、必要に応じ高速で制御を実施。大規模停電(ブラックアウト)を防止する。運用開始は2024年3月を予定している。同社は再エネの導入拡大のため、電力系統の安定化を支援し、安心して電気を利用できる社会の実現に貢献していく。
【損保ジャパンほか/財務影響分析サービス 洋上風力向けに開始】
損害保険ジャパンとSOMPOリスクマネジメントは、洋上風力発電事業者向けに、事業運営上の確率的なリスク評価に基づいたプロジェクトサイクルで保険料のシミュレーションを行い、財務への影響を分析するサービスを販売する。自然災害や故障などの発生や保険マーケットのトレンド、物価動向などを加味して保険料を算出できる。
【双日・日本製紙/バイオマス発電が稼働 燃料に未利用材を活用】
双日は日本製紙と共同でバイオマス発電事業会社「勇払ゆうふつエネルギーセンター合同会社」(北海道苫小牧市)を設立し、2020年5月から建設を進めてきた国内最大級のバイオマス専焼設備の営業運転を2月から開始した。発電出力は約7万5千kW。燃料は主に海外から調達する発電用木質チップとPKS(パームヤシ殻)のほか、北海道の未利用材(間伐材や林地残材の未利用資源)を積極的に使用する。未利用材の活用により、地域の森林環境の整備を促し、北海道の林業振興や雇用創出による地域活性化に貢献する。
【ENEOS/豪州でグリーンMCHの大量製造に向けた実証】
ENEOSはこのほど、水素キャリアの一種であるメチルシクロヘキサン(MCH)を製造する実証プラントを豪州に建設した。同社は、独自に開発した低コスト型有機ハイドライド電界合成法(Direct MCH)を活用。再エネ由来のMCH(グリーンMCH)の大量製造に向けて、電解槽の大型化に取り組んでいる。この実証プラントでは、中型電解槽と250kWの太陽光発電設備を組み合わせた製造を行う。今年2月から9月までの実証期間中に、製造効率最大化のため、亜熱帯環境下での電解槽の耐久性の確認や、太陽光の発電量に合わせた運転・制御技術を開発する。こうした知見を生かし、25年度をめどに商用化に使用する5000kW級の大型電解槽の開発を目指す方針だ。