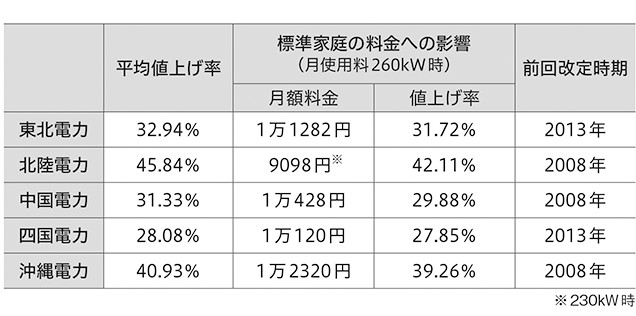TOKIOーBAの裏話 怪しいフィクサーの影
人気グループの「TOKIO」が、22年5月に福島県西郷村に「TOKIOーBA」という8ヘクタールの土地を購入し、新しい復興の場となる期待が出ている。ところが、この場所はかつて騒ぎを起こした「安愚楽牧場」の所有で、怪しいフィクサーが登場しているようだ。
安愚楽牧場は肉牛への出資者を一般人から募る和牛預託商法をしたが、経営が行き詰まった。総額4330億円の負債を抱え11年に倒産。社長は特定商品取引預託法違反で逮捕され、東京高裁で14年10月に懲役2年6月の実刑判決を受けた。
同社倒産後に畜産業のS社が資産の一部を購入。S社はそれを整理し、この地域の土地を売った。そこでMという東京のフィクサーが仲介に動いていたと、現地でうわさされている。Mは安愚楽の経営にも関わり、秋元司元衆議院のIR汚職事件で偽証し逮捕された人物だ。ちなみにTOKIOーBAの隣接地に、今話題になっている上海電力の太陽光発電所がある。
TOKIOは11年3月の福島第一原発事故の後に、農業を行う番組をしていた縁で福島復興を積極的に手伝い、県民に深く感謝をされた。20年に所属事務所から独立しメンバー3人が「株式会社TOKIO」を設立。今年5月に新プロジェクトとして「TOKIOーBA」を発表し、10月には現地で「フクシマBAマルシェ」という物産販売イベントを行った。各メディアが取り上げ、県も支援し好評だった。
TOKIOとMの関係の詳細は現時点で不明だ。しかし善意で復興に取り組む人々や県、自治体が怪しい人たちに取り込まれないかが心配だ。
小早川氏の次は誰? 東電次期社長を読む
東京電力ホールディングス(HD)の次期社長レースに暗雲が漂っている。「小早川智明社長の後任を務められる有力な人材が見当たらない」(元東電幹部X氏)という問題を抱えているようなのだ。

小早川氏は2017年に史上最年少となる53歳の若さで東電HD社長に就任し、現在6年目を迎えている。当初は、営業畑を歩み原子力部門の経験がない小早川氏に対し、電力経営の手腕を不安視する向きもあったが、「ポストが人を育てるという言葉通り、今や立派な経営者となり風格も出てきた。頭の良さと精神力の強さが生かされていると思う」(X氏)。問題は次だ。
現在、候補として名前が挙がっているのが、東電HD役員のY氏、S氏、N氏、東電グループ会社トップのN氏とA氏だ。X氏とは別の元東電幹部のZ氏が言う。
「まずY氏は頭が切れて有能だが、大電力会社の社長として経営を取り仕切るには力量不足。S氏は経営のセンスはあるものの、経産省の言いなりになる恐れがある。個人的には、N氏が社長になるとおもしろいと思うが、小早川氏と同様、原子力経験のないことが足かせに。もう一人のN氏も社長を務められるだけの実力を持っているが、小早川氏との人間関係がネックになりそう。A氏については、現職でミソを付けてしまったので、いっても東電HD副社長までだと思う。社内的にはいずれも決め手に欠けるのが実情だ」福島第一原発の廃炉・処理水放出、柏崎刈羽原発の再稼働、東電エナジーパートナーの増資に料金値上げなど、課題山積の東電。社長職の苦労も並大抵ではなさそうだ。
電事連会長人事が混とん 中部・関西に漂う暗雲
電気事業連合会の次期会長の行方が混とんとしてきた。現会長の池辺和弘・九州電力社長は異例の3年目を務め、23年春の交代がうわさされている。
後任として有力視されてきた一人が、林欣吾・中部電力社長。だが、①大手電力カルテルで公正取引委員会から課徴金275億円の処分案、②東邦ガスとのカルテルで公取委が立ち入り調査―といった事情から、雲行きが怪しくなりつつある。
もう一人の有力候補は森望・関西電力社長だ。「関電は会社として電事連会長のポストがほしいのではないか」と話すのは、大手電力会社幹部A氏。背景には、青森県むつ市での使用済み核燃料の中間貯蔵を巡る問題がある。

関電は21年2月、福井県内の原発から出る使用済み燃料についてむつ市の施設を共用する案を、杉本達治・福井県知事に提示。23年末を期限として確定させることを約束した。しかし宮下宗一郎・むつ市長は「可能性はゼロ」として共用案に反対の姿勢を明示している。このまま事態が進展しなければ、高浜1・2号機、美浜3号機が稼働停止を余儀なくされることになりかねない。
「電事連会長になれば、慣例として青森県と関係の深い日本原燃の会長も務めることになる。23年には県知事選があり、宮下市長が出馬する可能性が取りざたされている。関電としては、電事連・原燃の両会長の立場でこの問題を仕切りつつ、新知事との交渉を進めたい。そんな思いがあっても不思議ではない」(A氏)
ただ、11月下旬に明らかになった大手電力カルテルに対する公正取引委員会の処分を巡って、関電が課徴金減免制度を使って処分を免れたことへの批判が業界内で高まっている。「そんな時期に、関電が電事連会長を務めるのは現実的に難しいのではないか」(経産省関係者)
複数の事情通の話を踏まえると、現在は樋口康二郎・東北電力社長の可能性が急浮上している。「東北初の電事連会長が誕生するか、それとも池辺氏が異例の4年目で続投するか。いずれにしても、最後は両社の話し合いで決まるかも」(大手電力幹部)
太陽光条例は箔付け? 小池都知事の変節
「小池百合子都知事は『東京は国や世界に先駆け太陽光設置都市として名を馳せる』とまで言っていたのに、急にトーンダウンした」。
東京都議会で22年12月15日に可決された新築住宅の太陽光パネル設置義務化条例。恩恵を受けるはずの業界団体幹部はこう嘆いた。中国・新疆ウイグル自治区の人権問題などでネットを中心に「アンチ太陽光」の勢いが増す中、旗振り役だった小池都知事は12月の会見では批判に配慮するなど「変節」。背景に都民の反発があるかと思いきや、実情はそうでもないらしい。
前述の団体幹部は「反対派筆頭のS氏は、保守政治家F氏らとオピニオン誌などでつながりがある。S氏に同調するように、他の保守政治家も反対の姿勢を強めてきた」と話す。元自民党幹事長・二階俊博氏との親交を武器に国政復帰・女性初の首相を目指す小池氏にとって、保守派との対立は望むところではなく、先の変節は保守派議員に配慮した形というわけだ。
そもそも太陽光条例自体への思い入れもなさそうだ。「小池さんにとって太陽光条例は自身の箔付けに過ぎない。当時所属していた木下富美子都議の無免許運転事故問題を隠すためにぶち上げただけ」(都議K氏)。条例は25年4月実施を目指すが、さらなる変節はあるのか。
アカデミアの変化 T大で再エネ派存在
「気候危機」やカーボンニュートラルへの社会的関心の高まりが、アカデミアの顔ぶれにも影響を与えている。
これまで再生可能エネルギー推進派と言えば、洋上風力公募を巡る情報発信を積極的に繰り返したY・K特任教授、再エネ懐疑派だけでなく時に再エネ推進派とのバトルも辞さないY・Y特任教授を擁するK大というイメージが強かった。ただ、ここ数年は、T大も再エネ派の論客を続々教授などに招へいし始めた。「T大の左傾化が目立ち始めている」(気候危機慎重派)というのだ。
例えば、環境系や再エネ系委員として政府の数々の審議会メンバーを務めるT氏は、R大やN大を経て現在はT大教授を務める。また気候危機派の急先鋒のE氏も、つい最近T大教授に就任した。E氏は環境系の公的研究機関に所属し、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)評価報告書執筆者としても活躍した。なお、T氏もE氏も、T大の同じ研究センターの所属だ。
ちなみに、再エネ主力化のロビイストとしての役割を担い、大手電力などへの舌鋒鋭い批判も展開するO氏は、現時点ではT大にもK大にも属していない。